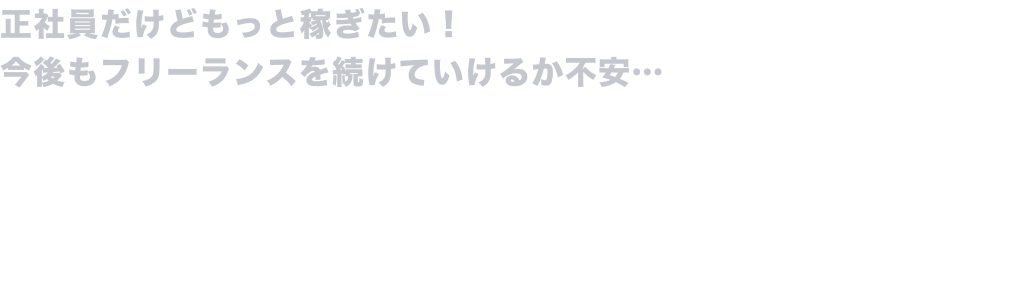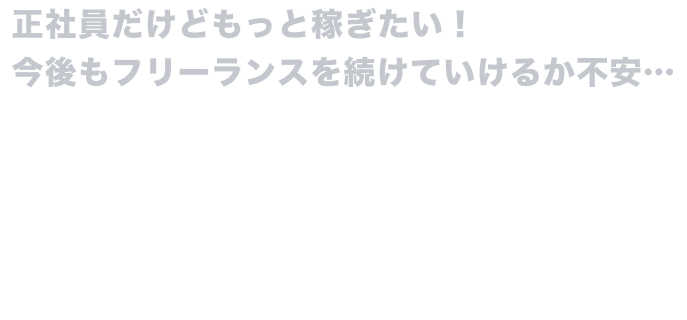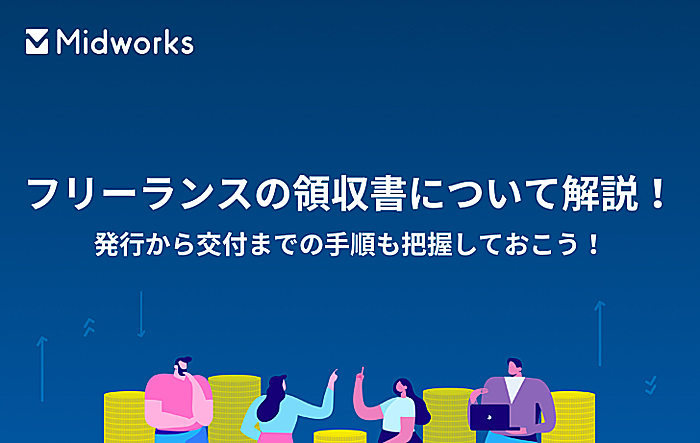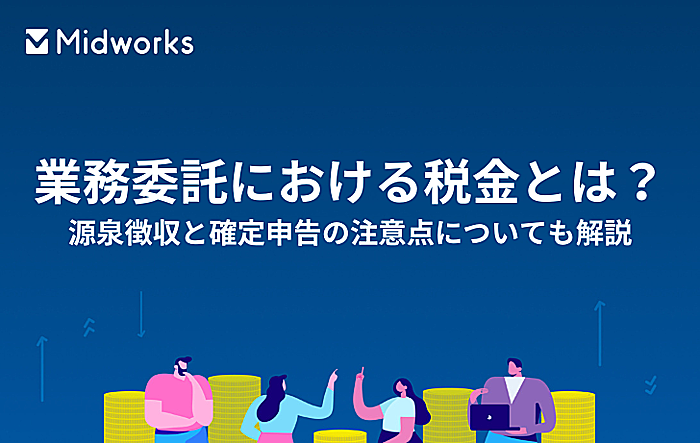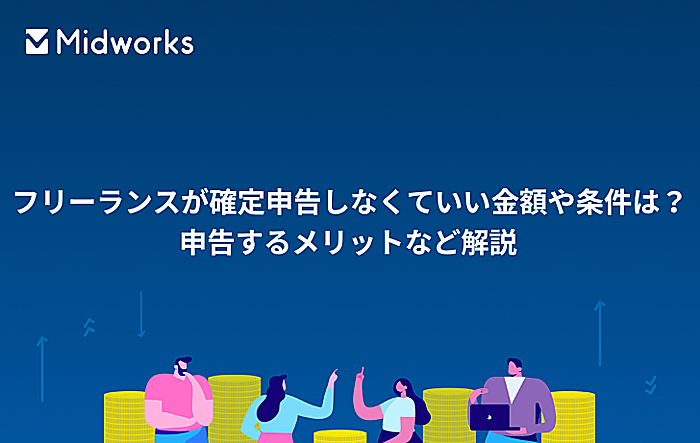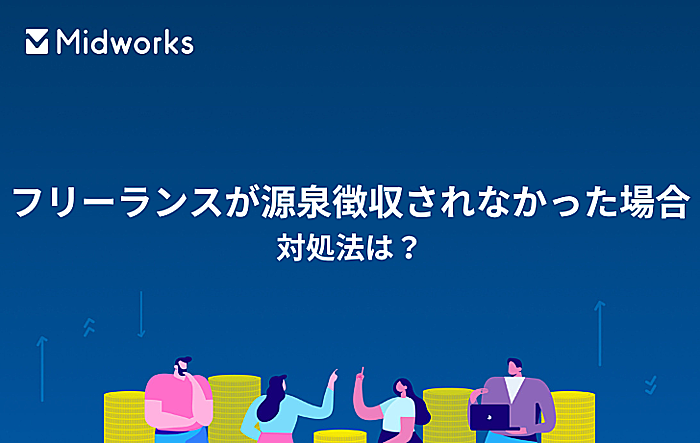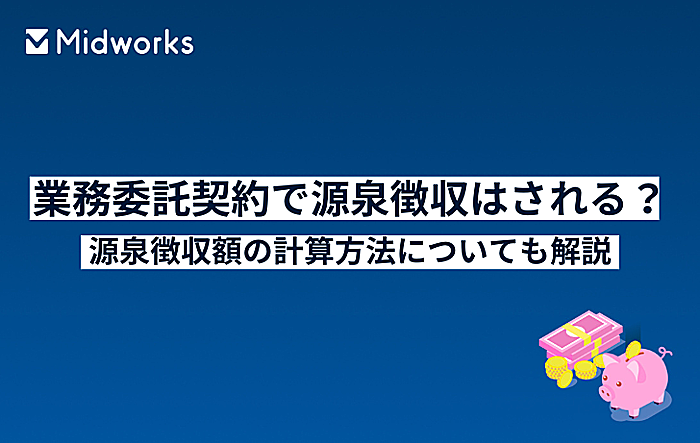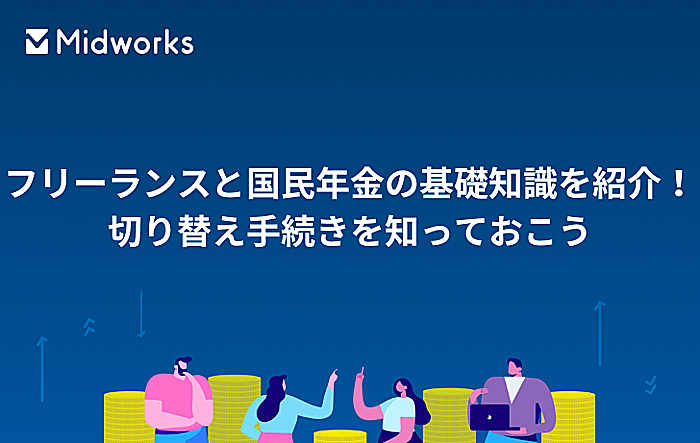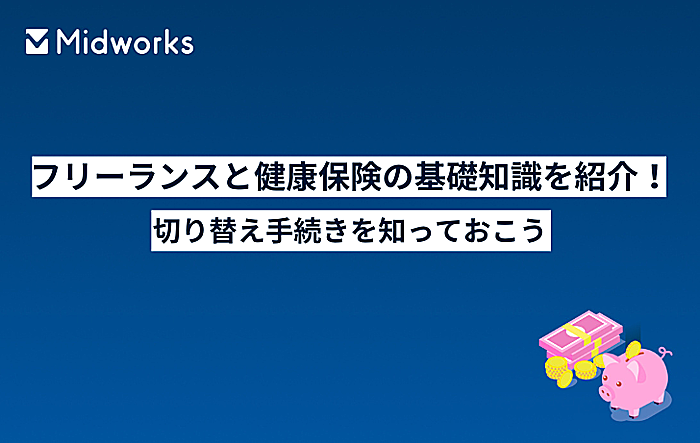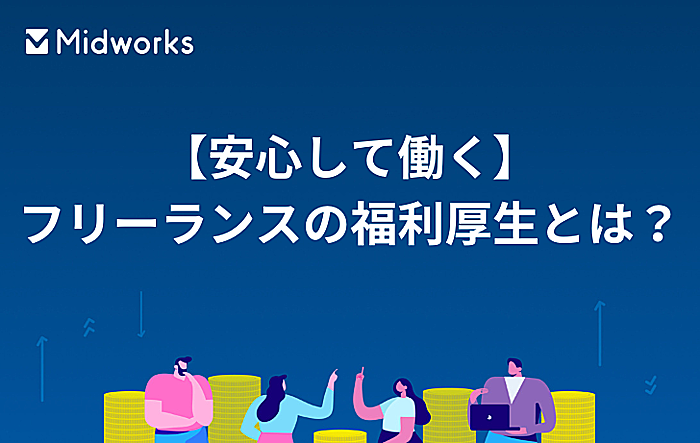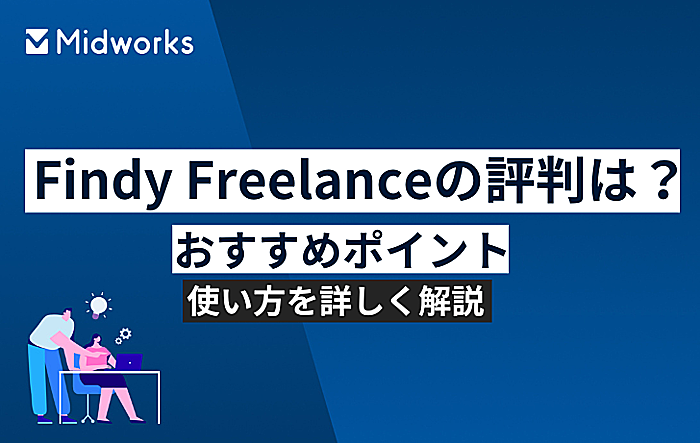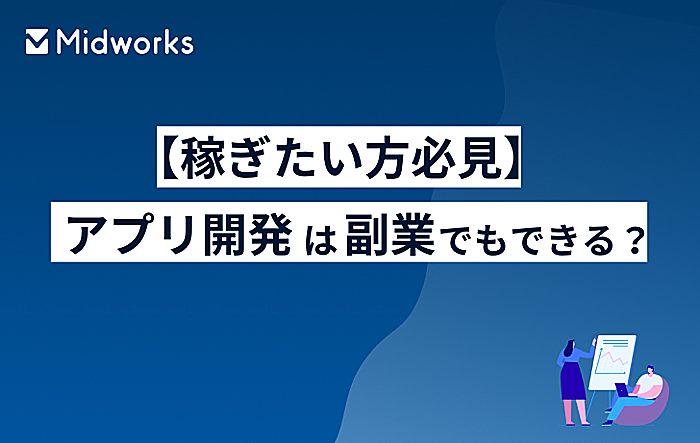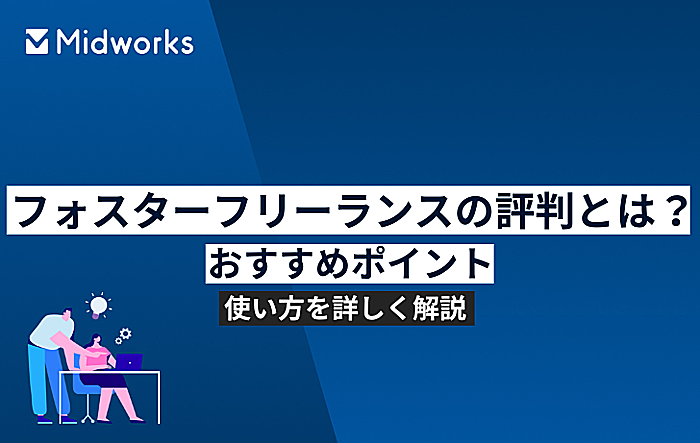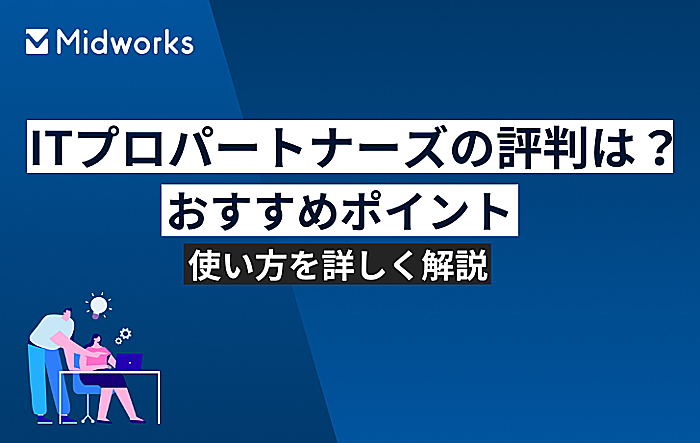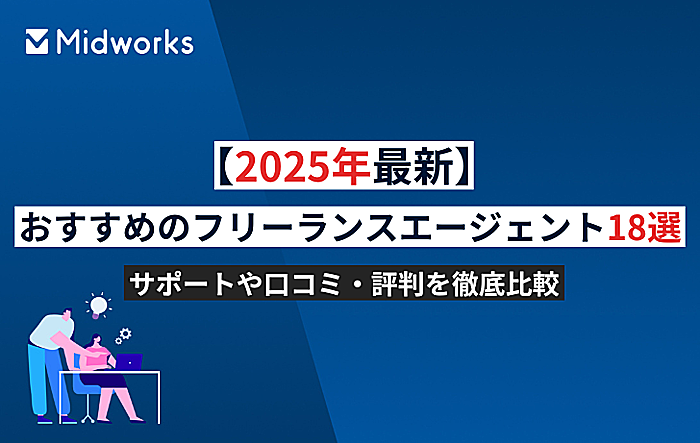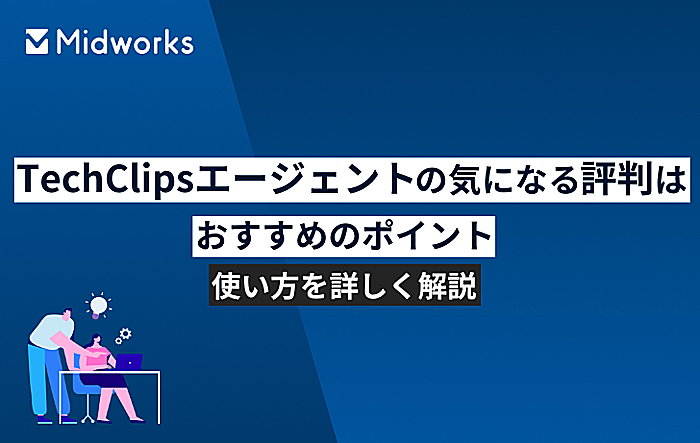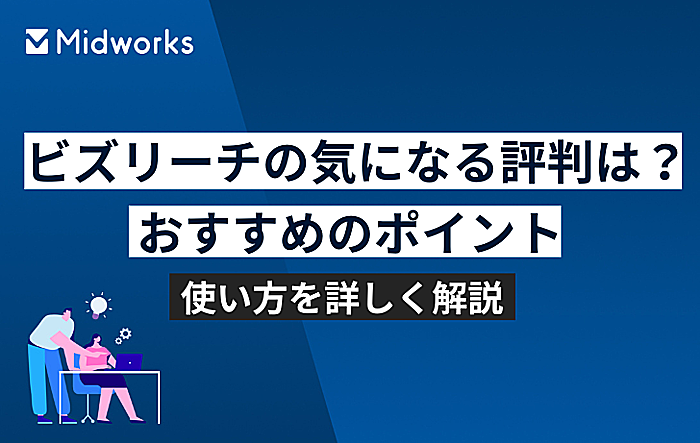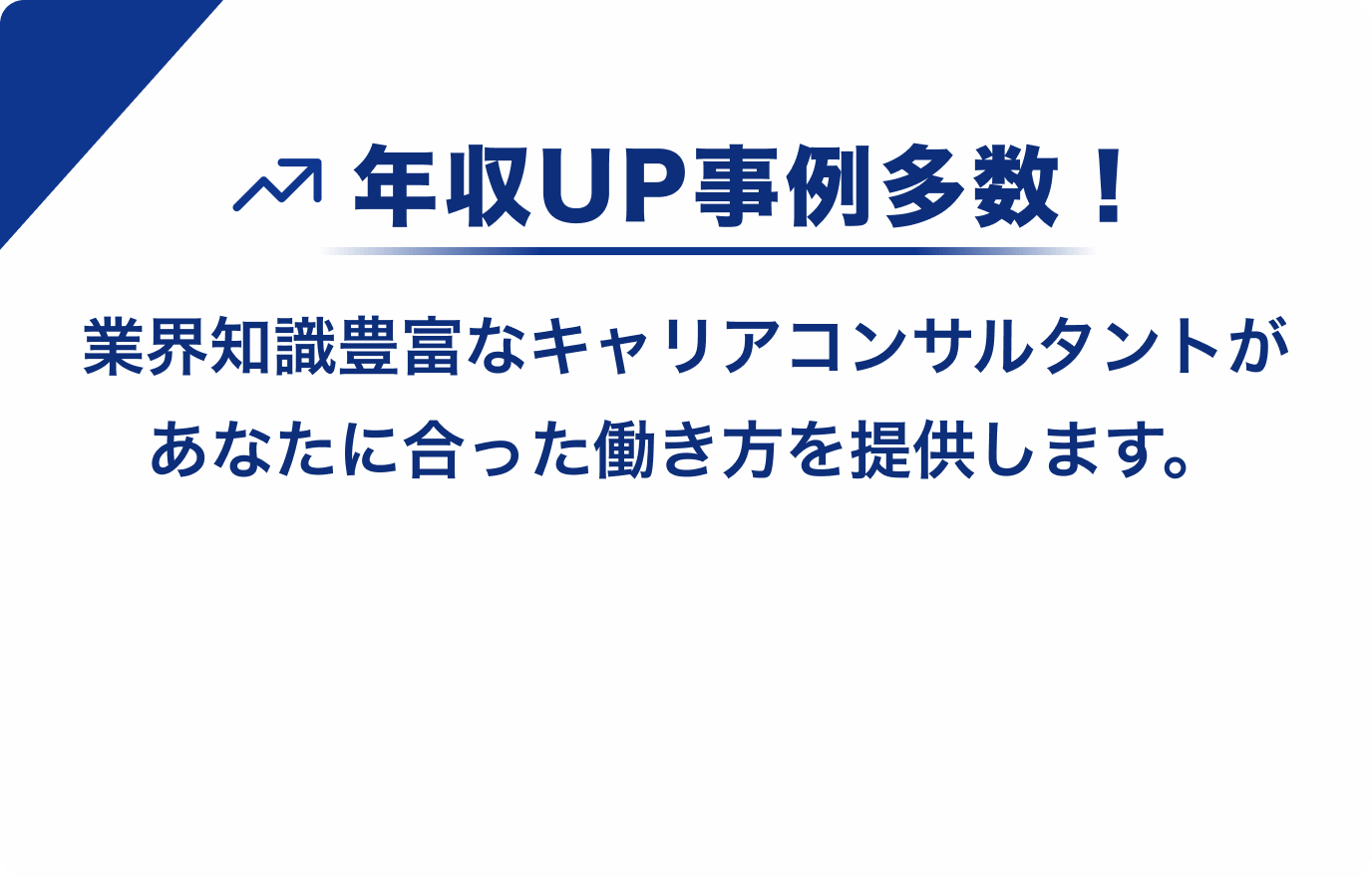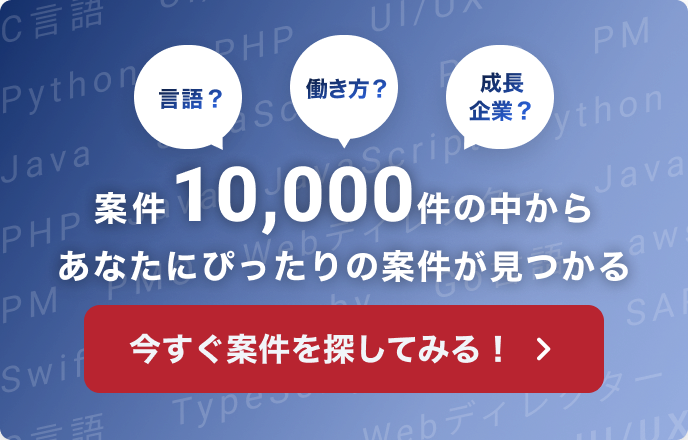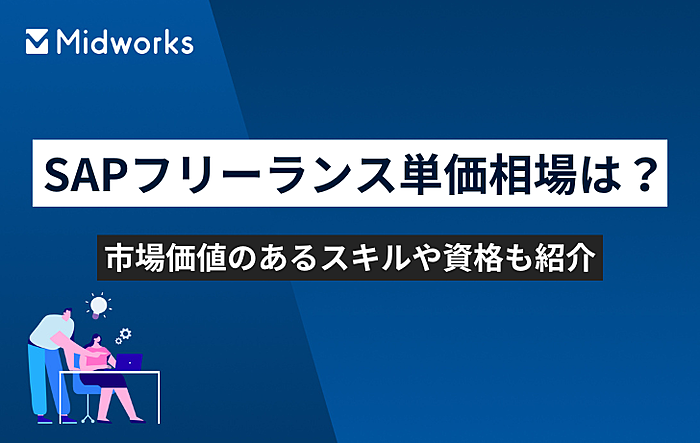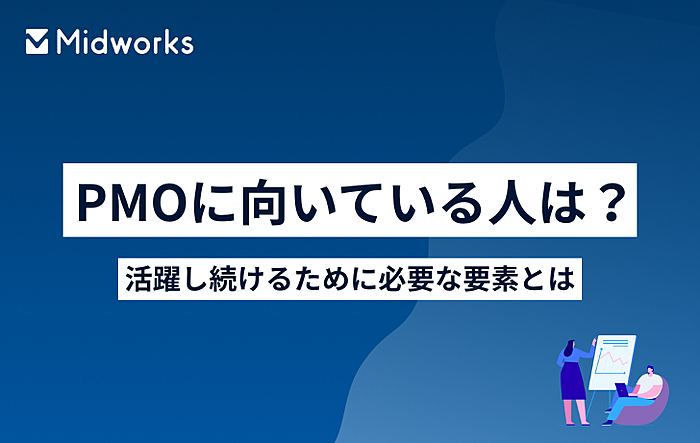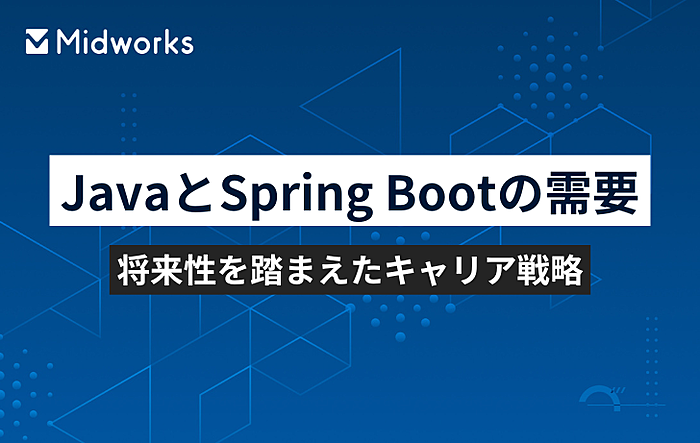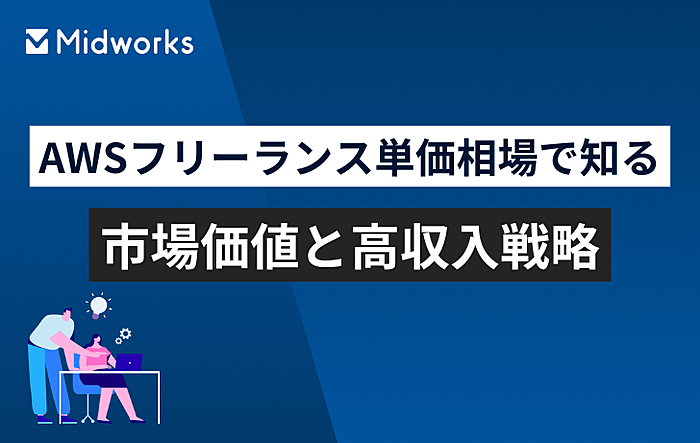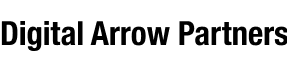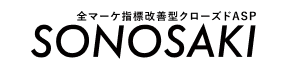「業務委託って何?」
「業務委託で働くにはどうしたらいいの?」
「業務委託ってどれくらい稼げるの?」
このように、業務委託の働き方についていくつか疑問を持っている方もいるのではないでしょうか?
本記事では、業務委託での働き方や、それぞれの契約形態との違い、メリット・デメリットなどについて解説しています。また、トラブル事例やトラブルを避けるポイントなども解説していますので、今後業務委託契約を結ぶ際の参考となるでしょう。
ワークライフバランスが重視される昨今、ワークスタイルも多様化されてきました。契約形態の知識がないと、自身に不利になる形で契約を結んでしまう可能性も考えられるため、しっかりと確認しておきましょう。
目次
目次を閉じる
業務委託とは?どんな働き方?

業務委託とは、企業や個人(委託者)が各々、業務に関することを別の企業や個人に委託することです。委託された側は、契約内容に基づいて委託された業務を行う必要があります。
受託する業務は、自分で取捨選択できることから、自らが希望する業務のみを仕事として受けて、報酬を得ることが可能です。
くわえて、業務委託の働き方は基本的に自由とされており、会社のように働く時間や仕事をする場所も指定されることはありません。このような業務委託としての働き方は、個人事業主やフリーランスとして働く人々にとっては一般的となっています。
また、業務委託は、お互い対等な立場にて契約を結ぶため、「雇用関係」には該当しません。この雇用関係の有無というのも、働き方の特徴の1つです。
業務委託の種類は3種類
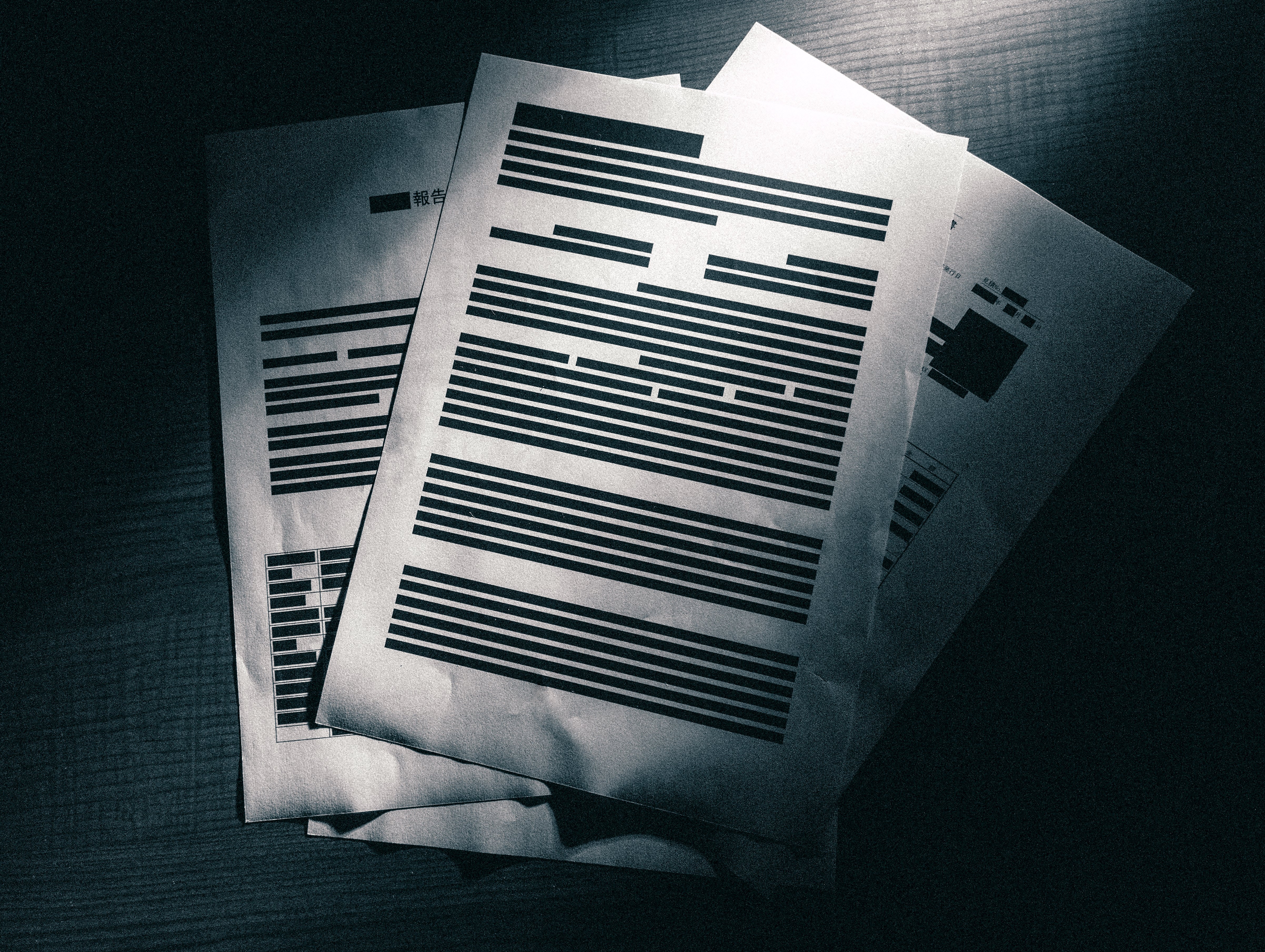
業務委託は、3種類に分類できます。それぞれ、「請負契約」「準委任契約」「委任契約」です。
ここでは、これら3つの業務委託の分類や特徴に関して解説していきますので、それぞれの契約形態について確認しておきましょう。
請負契約
請負契約とは、委託された業務の成果物を納品することで報酬が発生します。成果物を委託者に納品する過程や期間は関係ありません。成果物を納品すればよいということが特徴になります。
業務の完了日や納期が契約書に明記されている場合には、その条件を満たすように、業務を遂行していきます。その際の責任は、基本的に自己責任になる可能性があることを認識しておきましょう。
委任契約
委任契約というのは、委任者が受任者に一定の業務を、委託するという契約になります。この契約では、委託者の業務実行に対して、直接的な指揮命令権が基本的には存在しません。
また、委任契約では、善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)が課せられるという特徴があります。業務委託において仕事を行う場合には、当該職業または地位のある者として、通常要求される程度の注意義務を払うことであると定義されています。
準委任契約
準委任契約とは、委任契約のうち法律行為を伴わない業務を行う場合の契約のことになります。準委任契約は、業務を行うことに対して、報酬が発生します。
この準委任契約は、法律行為にあたらず、委託は幅広くあり、事務委託、保守管理業務などにおいて、用いられる契約です。たとえば、事務処理作業を行った「時間」「件数」によって報酬が決定されます。
準委任契約の具体例として次のようなものがあります。
・委託販売契約
・DM発送作業
・システム運営
・イベント運営委託契約
・ITシステムの保守・トラブル対応
・ITシステムの開発
業務委託と雇用契約別の違い

ここでは、業務委託と雇用契約の違いに関して詳しく解説していきます。
業務委託と雇用契約では働き方が大きく異なるため、業務委託を行おうとしている人は、要点を押さえておくことが重要です。
業務委託と正社員の違い
正社員が、企業、団体で雇用されて、雇用主と労働者の間で成立する契約であることに対して、業務委託では、委託者と委託を受けた者の間で成立する契約になります。
業務委託という契約形態には、雇用契約が含まれません。つまり、雇用関係にはなりません。互いが独立した立場で対等な関係で契約を結び、業務の遂行し報酬を得ることになります。
業務委託では、契約期間や契約条件は契約書によって決定されることも特徴的です。業務委託では、契約書に記されている内容に従って業務を行います。正社員の場合、労働基準法や労働契約に基づいた労働条件が適応されるのです。
正社員は雇用主の従業員として、社会保険などの福利厚生といったシステムも適応されます。しかし業務委託では独立した事業主として見なされるため、すべて自分で対応することが必要です。
このように、業務委託は正社員とはまったく異なる雇用形態、待遇で業務を遂行することになります。
出典|参照:労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)|厚生労働省
業務委託と派遣の違い
派遣労働者は、派遣会社と雇用関係にあるため、業務委託と比較した際には正社員と似たような違いがあります。
派遣社員の場合でも、派遣会社と派遣労働者の間で雇用契約が成立します。そのため、派遣社員は労働基準法などの法律によって守られるのです。一方で、業務委託の場合には、契約書に従うことになります。
社会保障や福利厚生に関しては、派遣会社によって提供されます。業務委託では、社会保障などを自分で対応しなければならないのが大きな違いです。
出典|参照:さまざまな雇用形態|厚生労働省
出典|参照:労働基準部 監督課 労働者派遣における労働基準法等の適用について | 静岡労働局
業務委託とアルバイト・パートの違い
業務委託とアルバイト・パートでも、正社員や派遣労働者と同様の違いがあります。パート・アルバイトも雇用関係があり、立場的には臨時従業員という扱いです。
雇用条件も、雇用主によって一定の労働時間・労働環境で雇用され、社会保障や福利厚生が適応されることも、業務委託との違いになります。
パートやアルバイトでは、一定時間、雇用主の下で労働するという特徴があります。それに対して業務委託では、特定の業務を代理で行うことになり、担当する業務は、専門性が求められることが多いです。
出典|参照:さまざまな雇用形態|厚生労働省
業務委託契約を結ぶ際の具体的な内容

業務委託契約を締結する際には、基本契約書と個別契約書という2つの契約書を用いて契約を行います。
ここでは、この2つの契約書についてや具体的な内容を解説していきます。
基本契約書
基本契約書は、委託者と受託者の間で締結される、一般的な契約条件および、取引条件を規定するための書類です。
基本契約書は、業務委託の総合的な条件を定め、委託された業務を行う際の詳細な内容や、基本的なルールなどを定めることが目的とされています。
具体的に記述されている内容は、委託者と受託者の氏名および住所、業務委託の範囲や目的などです。その他、報酬や支払い条件なども記載されています。
基本契約書は、フォーマットがあり基本的にはそのフォーマットに従って作成します。契約当事者間の関係や、業務内容によってカスタマイズされることもありますが、基本的な枠組みや各種条件(支払い、契約解除など)が一括で定められているのです。
個別契約
個別契約は、基本契約者に基づく具体的な業務委託を行うための条件や、その詳細に関する取り決めをしている契約書です。
基本契約書に記載されている一般的な条件にくわえて、具体的な内容や各種スケジュール、報酬の詳細などを決定していきます。これら契約の詳細を話し合い、決定したことを個別契約書に記載していくのです。
この個別契約は具体的な業務委託を行う際に使用されるため、立ち位置としては基本契約書の詳細を補足する契約書です。
そのため、基本契約書の内容と整合性が保たれる必要があります。整合性が保たれていない場合には、再度契約書を作成し直し、お互いが協議し意見が合致する場所を見つけることが必要です。
業務委託と個人事業主・フリーランスは同じ意味?

業務委託とは、委託者が受託者に一定の業務を委託し、報酬を支払う形になります。
一方で、個人事業主やフリーランスは、経済的な立場や雇用形態を示す言葉です。個人事業主とは、個人が独自の事業を営むことを指しており、フリーランスは、専門的な能力を活かして、自らの労働力を個人や企業に対して自由に提供している形態を指しています。
つまり、業務委託とは契約形態を指していることに対して、個人事業主やフリーランスは経済的な立場や雇用形態を指しているため、まったく別物であるといえます。
個人事業主やフリーランスが業務委託契約を結んで業務を行うことになるのです。
【受注者側】業務委託のメリット
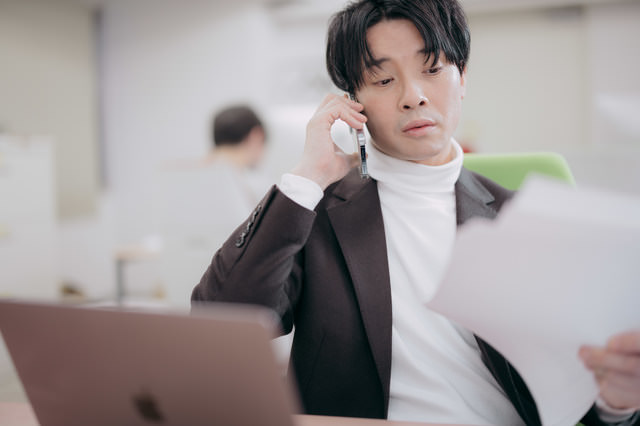
仕事を受ける側には、主に4つのメリットがあると考えられます。
人によってそのメリットの感じ方は異なりますが、ひとつひとつを吟味して自分が業務委託に向いているのか判断する材料にしてみてください。
特技や専門性を活かして働ける
委託業務では、自分の専門性を活かして仕事ができるというメリットがあります。契約書に記されている業務内容のみに専念すれば報酬を得られるのです。正社員とは違い、転勤もなく、自分が苦手である業務を行う必要はありません。
自分の得意分野や好きな分野の業務のみを遂行すればいいため、レベルの高い業務にも挑戦することが可能です。自分がスキルアップしていくことで、高単価案件も受注できれば、報酬は増えていきます。
場合によっては、好きなことをして、正社員よりもお金を稼げることは大きなメリットです。
働き方の融通が利きやすい
働き方の自由度が高いことが大きなメリットです。働く場所、働く時間に基本的には制限がありません。プライベートの時間や育児、家事などに重点を置いた働き方も可能です。期日が定められている場合でも、期限を守ればその間の行動に制限はありません。
業務委託では、業務単位で受注するため、仕事量も自由に調整することが可能です。自分の好きな業務や、得意な業務を選んで仕事ができます。
注意事項としては、秘密保持契約を締結した場合は、機密漏洩には最大限注意を払う必要があります。働く時間、場所をいくら自由にできるとはいえ、公共の場などで業務を行うと、情報が漏洩するリスクが非常に大きいです。
情報が漏洩するリスクはどこで作業してもありますが、リスクを回避するための工夫をする必要はあります。
実力が評価や報酬額に結びつきやすい
業務委託の場合、正社員として働くよりも実力が評価されやすいことが特徴です。請負契約では、成果物の納品が業務完了になります。この場合、契約を履行した時点で自分の実績になり、自分の実力としてアピールしやすいです。
業務委託は、成果物のクオリティや業務遂行能力で評価されます。その実力が認められれば、高い技術、知識が求められる案件も受託できるようになるのです。
求められる知識や技術が高度なほど、高単価案件にもなります。正当に実力を評価されやすいのが業務委託で働くメリットです。
人間関係の悩みが少ない
業務委託で仕事をする場合、正社員として勤務するより、人とのつきあいが少ない傾向にあります。
また、委託者と受託者はあくまで業務上の関係であるため、深くつながりを持つ必要もありません。そのため、人間関係で悩みを抱えるリスクは少ないです。
プロジェクトや業務内容によっては、委託者や関係者間でコミュニケーションが必要な場合もあります。人間関係が苦手であれば、そういった業務を選択しなければ人間関係の悩みからは解放されるでしょう。
【発注者側】業務委託のメリット

受注者側だけではなく、発注者にもメリットがあります。ここからは、業務委託として業務を発注する側のメリットを2つ紹介していきます。業務委託として依頼を検討している企業は参考にしてください。
社内だけでは対応できない仕事を遂行できる
自社の社員だけでは、対応できないような案件の場合も、業務委託という形で委託すれば業務が遂行できるようになります。
人材を募ったり、育成したりする場合よりも迅速に対応できます。業務委託の受託者は、その実力で正当に評価されるため、評価の高い方に委託することで、高レベルの仕事を遂行することも可能です。
人件費や教育コストの削減につながる
新しく人材を雇用すると、教育期間や事務仕事など生じ人件費が発生してしまいます。社員に対して、新しく教育する場合には、雇用は続いているにもかかわらず、その間に成果は上がらないのです。
その間のコストなどを考えると、業務委託で発注して、成果物を納品してもらう方が、金銭的に安上りで済む場合があります。
教育する場合には、教育期間が必要になるため、成果物ができ上がるまでにかなりの時間が必要になることもあるでしょう。業務委託では、技術や知識の高い人に委託することで、教育するよりも早く、高品質な成果物を得ることができます。
また、給与や福利厚生、社会保険費などの人件費を節約することも可能です。社内に人員が増えることもないので、社内インフラの整備をする必要もありません。人件費や、インフラ費用といった観点でも、コストを削減できます。
【受注者側】業務委託のデメリット

受注者側のデメリットは、主に4つあります。ビジネスをスムーズに進めるためには、これらのデメリットを理解し、適切に対応することが不可欠です。それぞれに関して、詳しく解説していきましょう。
労働基準法で保護されない
会社員やアルバイトであれば、労働環境や労働時間に関して労働基準法により労働者は守られています。
しかし業務委託では、この法律が適応されないため、自分で自分の身を守る必要があります。ただし例外もあり、適応される場合もあります。
業務委託で契約を結ぶ際には、契約期間や、自身の業務範囲、報酬の発生条件などを入念に確認し、必要に応じて交渉する必要があるでしょう。
出典|参照:労働基準法 | e-Gov法令検索
出典|参照:業務委託の場合、労働法では保護されない? 実質的判断基準について|ベリーベスト法律事務所 高崎オフィス
自己管理が必要
業務委託では、自分で仕事量を調整し、自分の仕事を自分で取ってくる必要があります。そのため、自由度がある反面その仕事量の管理と仕事の期限管理は自分で行わなければなりません。
また、万が一自分が体調不良などに陥っても誰もカバーしてくれません。仕事面でも、私生活面でも、自己管理を徹底して行う必要があります。
雇用保険や厚生年金に加入できない
業務委託は雇用契約ではないため、基本的には雇用保険や厚生年金には加入できないでしょう。
そのため失業や出産、障害などがあった際に、社会保障の手当や給付を受けられない可能性があり、ケガや病気をした時の際に経済的なリスクが伴ってしまうのです。
また、厚生年金に加入しないため、年金受給額が低下してしまうでしょう。他にも、福祉制度、住宅ローンや教育委支援制度といった面で、支援を受けられない可能性があるのです。
安定して収入を得られない可能性がある
業務委託では、よくも悪くも自分で仕事を取ってくる必要があります。さらに、その仕事は基本的に固定給で支払われるものではなく、一定の成果をあげなければいけません。そのため、業務の量に増減があり、契約の数が減れば収入が激減する可能性があります。
また、自分で企業と交渉して契約を勝ち取るための営業力も必要になります。営業力がないと、どれだけ実力があっても業務を獲得できないため、収入が減ってしまう可能性があります。
【発注者側】業務委託のデメリット

次に発注者側のデメリットを3つ紹介します。
発注する際には、コスト削減の面で大きな効果がある業務委託ですが、デメリットもあるため、事前に把握しておき利用しましょう。
人材育成やノウハウの蓄積が滞る
業務委託にしてしまうと、人材育成が行われずノウハウの蓄積も行われません。とくに、人材が育成されない場合、さらに業務委託に依存してしまうことになるため注意が必要です。
長期的な観点では、ずっと業務委託に依存するわけにはいきません。そのため、業務委託に完全に頼るのではなく、自社でもその分野に関する人材を育成し社内でノウハウを持つ人材を作る必要があります。
新規人材を育成したり知識者を雇用したりと、適切な対策を講じることによって業務委託に依存する環境を脱出する必要があります。
進捗等の管理が難しくなる
業務委託の場合、委託先の都合で作業が進行するので、進捗管理等が難しくなります。進捗管理を行うには、メールなどを用いて確認しなければならず、事務的な手間が発生します。
受託者によっては、期日までに仕上げて提出すればいいと考えており、提出まで連絡がないケースもあるでしょう。しかし、それでは委託者としては、いつ頃完成品が提出されるのかがわかりません。
委託者は契約書で契約している関係上、納品日を変更したり、契約書に記載事項のない要望を伝えたりできないのです。予定変更や、仕事がどれくらい進んでいるのかなどを確認して把握したければ、その旨を契約書に記載しておかねばなりません。
製品やサービスの質の低下につながる可能性がある
業務委託の管理が適切に行われていない場合や、委託契約が不適切な内容である場合には、成果物が要求しているレベルに到達しないことが考えられます。
委託契約の契約内容に、不明確な点が残っている場合や、解釈に相違がある場合、また、委託者とのコミュニケーションが不足しているなどの原因が考えられます。
業務を委託する際には、あらかじめ受注者の情報を調べますが、その調査が不足していることもあるでしょう。とくに、事前調査が不足している場合には、専門知識が不足しており、品質の低下や納期の遅延が考えられます。
これらの問題を回避するには、業務委託契約を行う際に作成する契約書を適切に作成し、内容や要件、期日などを明確に示す必要があります。
また、お互いが密なコミュニケーションを取れる体制を構築し、音信不通やコミュニケーション不足による齟齬を減らす工夫が必要になります。
受注者を選定する際には、「信頼できるか」「専門知識は十分か」という点を重視して、適切なスキルを所持している人を選定することが重要です。
業務委託契約で働くのに向いている人の特徴4つ

ここでは、業務委託で働くことが向いている人の特徴を紹介していきます。
もし、紹介している特徴に1つまたは複数個該当する場合には、業務委託が向いているかもしれません。
セルフマネジメントが得意な人
業務委託契約で働くのに向いている人の特徴の1つは、セルフマネジメントが得意な人です。セルフマネジメントが得意な人は、業務委託として自分で仕事を受注する際にも、無理のない範囲で仕事を受けられます。
また、仕事の納期や内容の把握、自分自身の体調管理まで適切に行うことが可能です。業務委託では、よくも悪くも自己責任になります。適切なプランニングと時間管理能力、コミュニケーション能力が必要です。
セルフマネジメントが疎かになり、納期を過ぎてしまうようなことがあれば、信頼関係に大きく響いてきます。セルフマネジメントが適切にできない人は、業務委託で仕事を行うことは非常に難しいでしょう。
変化にも柔軟に対応できる人
案件や月ごとで、関わるクライアントが変わってしまうからです。長期案件では、同じクライアントでも、途中で担当者が変わることがあります。その変化を楽しめるくらいの余裕があることが望ましいです。
また、案件の量も時々刻々と変化していきます。毎日仕事量と、行う業務内容が異なるため、そうした変化にも柔軟に対応する必要があります。
関わる人が頻繁に変わることが煩わしい方や、各種サービス(ChatWork、Slack等)で連絡することが面倒に感じる人、新しい人間関係を構築することが嫌な人は、難しいかもしれません。
仕事に活かせるスキルや知識を持っている人
何か1つでも、仕事に活用できるスキルがあれば、業務を受託して仕事ができます。
業務委託で働く場合は、その知識や技術を売っているので、専門性が高く、深い知識であることが望ましいです。高い専門性と深い知識を活用することで、より高品質でレベルの高い業務を提供できます。
求められるスキルは業務によって異なりますが、たとえばプログラミング、グラフィックデザイン、マーケティングなどが例としてあげられるでしょう。どれも、専門性を高めるための学習やトレーニング、豊富な経験が必要になります。
自由な働き方を求めている人
業務委託は、自由な働き方を求めている人にはとくにおすすめです。業務委託では時間・場所などの自由度が非常に高いです。機密管理を徹底して行える場所であれば、家でなくともワークスペースやカフェ、レンタルオフィスなど、どこでも作業できるでしょう。
一方で、クライアントの契約や納期を遵守するなどの責任を負うことになります。自由に働くことができますが、契約を守ることは必要です。
業務委託で仕事を始める前に準備しておくこと

業務委託で仕事を始める前に、準備しておくべきことがいくつかあります。
ここでは、業務委託で仕事を開始するまでに準備しておくことを3つ紹介します。事前に確認しておき、準備を整えておきましょう。
業務内容・価格表を作成しておく
業務内容と、価格表をあらかじめ作成しておくことは非常に重要です。業務委託といっても、何の業務を、どのような期間で行うことができるか、多種多様ありますあります。大きなプロジェクトの経験はあるのかや、自分の得意なことを明確にしておきましょう。
自分がどのような仕事を受けられるのか、業務内容を自身で把握しておくことは重要です。また、業務内容ごとに価格表を用意しておけば、価格交渉もスムーズに進めることができます。
ヒアリング項目を作成しておく
準備しておくべきことの2つ目は、ヒアリング項目の設定です。ヒアリング項目をあらかじめ設定しておくことで、クライアントの現状、要望を事前に把握できます。
実際にヒアリングを行うことで、価格や成果物の納品期間、成果物の提出方法などを調査していきましょう。ヒアリングを行いお互いの疑問点をできる限りなくし、質の高い商談や会談を行うことが可能です。
受託する前に確認しておくことで、契約締結後に契約不履行になり、違約金が発生したりする問題を避けられます。
ポートフォリオを作成しておく
ポートフォリオを作成しておくことは、非常に重要です。自分自身を営業する際にも、業務依頼を受ける際にも必要となります。
ポートフォリオは自分の実績を証明するものです。業務委託という、実績を重要視される環境では非常に重宝されます。ポートフォリオがなければ、能力を証明するものがなく、委託する側も信用して業務を委託できません。
また、ポートフォリオは自身のイメージやブランディングを行うツールとしても活用可能です。自分の得意分野や長所を強調してPRし、何ができるのか、どのようなことが得意なのかを、委託者側に印象付けを行うことができます。
ポートフォリオには、過去の実績を一覧で載せることがあります。過去の実績を振り返ることで、自己評価や改善点を発見し、さらなるレベルアップをすることも可能です。
業務委託にまつわるトラブル事例6つ

契約で守られているといえ、業務委託では過去さまざまな問題が発生しています。知識が不十分なまま業務委託契約を締結してしまうと、トラブルにつながりやすくなるでしょう。
偽装請負のトラブル
偽装請負のトラブルとは、請負契約において委託者が「請負契約で認められていない行為」を行った、というトラブルです。
請負契約では、委託者に指揮命令権が存在しないという特徴があります。これにより受託者は、業務の進行方法や、作業時間、作業場所などに関して、委託者から指示を出されることはないのです。
しかし、この請負契約の特徴を無視して、細かな指示を委託者が受託者に対して行う場合があります。これは、契約違反です。
このような、請負契約にもかかわらず、契約書にないような細かい指示や管理を委託者が受託者に行った際には、偽装契約と認定されることがあります。
出典|参照:偽装請負とは?【違反例とポイントを弁護士が解説】 | 労働問題の相談はデイライト法律事務所
二重派遣のトラブル
二重派遣とは、自社で受け入れた派遣労働者がさらに別の企業に派遣されていることを指します。二重派遣が行われると、労働者が本来の雇用契約にない業務を行うことになり、派遣労働者が不利益を被る可能性があり、法で禁止されていることです。
委託業務でも、このケースと同じような状況が発生する可能性があります。たとえば、委託契約を結んだ受託者が、さらにその業務を別の受託先に業務委託している場合に生じるのです。
この時に、最初に業務委託をした委託元と最終的に業務を受けた受託者との間に、コミュニケーション不足が原因で、納品物が品質を満たせていなかったり、納期を守れなかったりすることがあります。
二重派遣を行う場合には、法的な規制を遵守して、適切な契約内容を取り決めることが重要です。また、委託先とのコミュニケーションを密に行い、委託の条件や、目標などの共有を行うことで、このようなトラブルを未然に防ぐことができます。
出典|参照:二重派遣は派遣法違反ですか|厚生労働省
中途解約のトラブル
「業務委託契約を結んだが、期待していたような成果が出ない」
「別の業者に依頼した方が、効率や品質がよい」
このような理由から、委託者は現在の業者とは別の業者に切り替えたくなることがあるかもしれません。
この際に委託者は、受託者との間に締結した契約を解約する必要が出てきます。契約を一方的に解約する場合には、違約金を請求されたり、損害賠償請求をされたりするトラブルが発生することがあるため注意が必要です。
民法641条では、注文者に対して、請負人が仕事を完成する前である限り、いつでも請負契約を解除することを認めています。請負人が、仕事を完了している場合には、契約解除ができないことに注意しましょう。
民法上では、いつでも解約できるとされていますが、仕事をしているにもかかわらず、一方的に契約を切られると、受託者の損害が出てしまいます。
受託者側としては、この損害を出さないために、契約時に、完成度に応じて報酬を貰えるようにしたり、働いた日数に応じて報酬を出したりすることが必要になるでしょう。
中途解約を行う場合には、自分の都合で解約して、契約している相手に迷惑をかけてしまうということを、忘れないようにしましょう。
出典|参照:民法 | e-Gov法令検索
損害賠償請求に関するトラブル
業務委託の際に、損害賠償請求に発展するトラブルはいくつかのケースが考えられます。たとえば、「契約違反が見つかった場合」「知的財産権を侵害してしまった場合」「情報漏洩・流出が見られた場合」などです。
契約書に記載されている条件や約束事を履行することなく、委託先が契約違反を起こした場合には、委託先に損害賠償請求を行えます。
受託者が納品した成果物が、他者の著作権や特許などの知的財産権を侵害した場合には、その知的財産権を持っている者から、損害賠償請求を受けるケースがあります。
たとえば、受託者が無断で他人の著作物を使用したり、特許権を侵害したりすることで知的財産権を侵害し、問題になることもあるのです。
情報漏洩や、情報流出がある場合、これは機密漏洩の契約違反になります。
委託先が秘密保持義務を守らなかった場合とは、委託者の機密情報が漏洩したり流出したりしてしまった場合です。これにより、委託者が損害を被った時には委託先に対して損害賠償請求を行うことができます。
業務遂行中に事故やトラブルを起こし、それによって委託者に損害が生じた時には委託先に対して損害賠償を請求することが可能です。これらのトラブルを回避するために、委託契約書を十分に検討し契約内容を明確にして、リスク管理を行う必要があります。
出典|参照:秘密保持契約(NDA)を違反するとどうなる? 弁護士が法的な観点から解説|ベリーベスト法律事務所
出典|参照:スッキリわかる知的財産権 | 経済産業省 特許庁
出典|参照:知的財産権と刑事罰|経済産業省 特許庁
出典|参照:知的財産権を侵害されたらどうすべき? 過去の事例と対応方法を解説|顧問弁護士・企業法務ならベリーベスト法律事務所
報酬の支払いに関するトラブル
業務委託では、支払いのタイミングや、仕事の内容に対して委託者が期待する基準に達していない場合の可否などといった報酬に関するトラブルが発生する可能性があります。
報酬の支払いに関してのトラブルは、業務委託契約書に報酬に関する情報が明記されていないことによって、問題になるのです。業務委託契約書を作成する時に、「報酬額」「報酬発生条件」などを明記しておくことで、このトラブルを回避できるでしょう。
再委託に関するトラブル
委任契約や準委任契約を行う際には、委任者がさらに別の業者や個人に対して、同様の業務を委託することが可能です。これを、再委託といいます。
再委託が許されると、再委託が繰り返して行われる危険があるのです。繰り返し再委託が行われると、情報統制が機能せず情報漏洩を起こす可能性があります。
他にも、品質コントロールができず、劣悪品が納品される、コミュニケーションの乱れなどの問題が発生してしまう危険性がありますので注意しましょう。
出典|参照:相手の同意なく再委託はできるか 再委託条項の定め方 | 米重法律事務所
下請法違反のトラブル
下請法とは、資本金の大きな企業が資本金の小さな企業または個人に対して発注した商品やサービスの取引について規定しているものです。
具体的には、取引の報酬を不当に減額したり、支払いを遅延したりすることを禁止する法律となります。正式名称は、「下請代金支払遅延等防止法」です。
下請法違反のトラブルとしては、「納品物を受け取ってもらえない」「納品後に報酬の減額がなされた」「いつも口約束で仕事を引き受ける」などのケースがあります。
出典|参照:下請法の概要 | 公正取引委員会
業務委託契約のトラブルを避けるために押さえるべきポイント

業務委託によるトラブルに巻き込まれたり、意図せず自身がトラブルを起こしたりしないためには何をしたらいいのでしょうか。
ここでは、トラブルを避けるのに必要なポイントを解説していきます。
下請法を理解する
下請法は、委託者と受託者の間で公平な取引を実現するための法律です。資本の大きな企業が、資本の小さな企業や個人を不当に虐げないための法律となります。
下請法の特徴は、「資本金の金額」という、客観的な基準で適用対象となる企業が決まることです。たとえば、フリーランスであれば、資本金が1000万円越えの法人クライアントとの取引を行う場合には「下請法の対象」となります。
下請法が適用対象となった受託者には、さまざまな義務が発生します。取引内容に関する書類を交付する義務、支払いの遅延禁止などです。下請法に違反した場合、その契約は無効化されますし、違反行為をした委託者は行政から処分を受けることもあります。
出典|参照:下請法の概要 | 公正取引委員会
契約内容は明確に定める
契約内容を明確に定めることは非常に重要です。金銭に関することだけではなく、業務内容やその範囲に関して、できる限り明確に定める必要があります。
以下に、ポイントごとに細分化して解説していきます。
業務内容・範囲
業務内容や業務の範囲に関して、明記する必要があります。業務内容の明確化とは、具体的な業務内容や、業務の種類、目標や、納期などに関して具体的に表記するということです。
また、委託する業務の範囲を明確に限定することが重要になります。業務の範囲を明確にすることで、委託者と受託者の業務に関する理解を一致させることが可能です。責任の所在や権限を明確化すること、作業方法や提出物に関しても取り決めしておくことが重要です。
必要に応じて、契約内容の変更事項や追加業務に関することも取り決めしておきましょう。変更手続きや、報酬の調整に関して、明確なルールを示しておくことで、スムーズに手続きを進められます。
指揮命令権の所在
業務委託を行う場合には、指揮命令権は非常に重要です。指揮命令権は、委託者が受託者の業務方法や進行について、指示を出す権利のことを指します。
業務委託では、すべての契約において、指揮命令権は委託側が持つことは不可能です。業務委託契約において、委託側が指揮命令を行うと、偽装請負と判断される場合もあります。
契約書に指揮命令権を明記しておくメリットは、責任と透明性を確保できることです。指揮命令権がある方に、業務遂行に関する直接的な責任が発生します。委託者は、委託した業務の責任の行栄を不明確にしないためにも、明記しておく必要があります。
報酬の金額や支払い方法、経費の取り扱い
報酬金額や、支払い方法、経費に関してもあらかじめ明確にしておきましょう。報酬金額だけでなく、支払い方法も明記しておくことも重要です。
委託者が支払い方法を明確にしておくことで、どのタイミングで、どのような手法で取引が行われるのかが、受託者がわかるようになります。これにより、支払いに関するトラブルを未然に回避することが可能です。
また依頼内容によっては、受託者が必要物資を購入したり、移動したりする必要があります。委託者が、どの程度経費で負担できるのかを明記しておかなければ、精算の際に問題が発生するのです。
金銭に関することは、問題になりやすいことですので、委託者は可能な限りすべてを明確にしておく必要があります。
知的財産権の所在
人の知的活動で生み出されたアイデアや創作物には、知的財産と呼ばれる、財産的な価値を持つものがあります。
この中には、特許権などの法律で定められた権利や法律上保護され、利益に関わる権利として保護されるものがあるのです。これら、法律上で保護されている権利を、知的財産権といいます。
業務委託では、成果物に関する知的財産権が、最終的に誰にあるのかを明確にしておくことも重要です。知的財産権の所在を明確化していなければ、意図せず知的財産権を侵害してしまうこともあります。
知的財産権に該当するものとしては、文書、デザイン、ソフトウェア、製品、発明などさまざまな知的財産が含まれる可能性があるので注意が必要です。
成果物の著作権や特許権などの知的財産権が誰に帰属するのかを明確に記述することが重要です。知的財産権の所在に関しては、契約に明記されることによって決定します。
成果物の知的財産権を委託者に移転する場合、契約書に明確な権利移転の取り決めを記述することが重要です。権利移転には手続きや条件が必要な場合があります。
そのため、契約書で詳細に規定することで、お互いに条件を明確にして共有しておくことが重要です。その他、保護期間と利用範囲、第三者への権利譲渡なども考慮しなければなりません。
業務委託においては、成果物に対する知的財産権を適切に取り扱うことが、双方の利益と信頼関係を守るために、必要不可欠です。契約書に、知的財産権の所在を明確に取り決め、記載しておくことで、この問題を回避できます。
出典|参照:知的財産権について | 経済産業省 特許庁
契約解除の条件
契約解除の条件を明らかにしておくことは、「トラブル防止」「解除の手続き」「責任範囲の明確化」「納期や品質管理」の観点で、重要です。
たとえば、契約違反があった場合や、納期の遅延が生じた場合です。品質不良などの問題が生じた場合には、契約解除の条件に基づいて解除が可能になります。
また、解除手続きに関して明記して、双方が把握していれば、スムーズに手続きを行うことが可能です。明確にルールが定められていることで、契約解除の混乱や誤解を避け、トラブルを未然に回避できるでしょう。
損害賠償請求の有無と条件
損害賠償の有無に関しては、契約内容によって異なります。損害賠償がある場合には、業務委託契約書にて、どのような場合に損害賠償を請求する権利があるのかを明記しておくことが必要です。
その他、損害賠償の金額とその適応範囲に関しても、契約書に明記するべきです。具体的な金額や損害の種類について明確な取り決めを行い、どのような状況や行為が損害賠償を引き起こすかをお互いに共有しましょう。
また、明確に共有することで、委託者と受託者がお互いに損害賠償について注意深く行動するように、意識を促すことが可能です。これにより、委託者と受託者の双方が契約を履行するようになります。
損害賠償に関しては、契約内容の条件次第で大きく異なるのです。契約書には、損害賠償への取り決めに関して、あいまいな表現を用いることなく、明確に記述しましょう。これにより、双方が潜在的なリスクに対する理解を深めて、トラブルを回避することが可能です。
業務委託はスキルを活かして柔軟に働ける契約形態

業務委託は、自分の持っている専門的なスキルを活用して、柔軟に働くことができる契約形態です。
専門的なスキル以外にも、自己管理能力やコミュニケーション能力などが求められますが、正社員をやめて自由に働きたい、好きなことをして今よりも高い給料を獲得したいと考えている場合には非常に有効な手段です。
この記事を読んで、業務委託をしてみたいと思った方は、挑戦してみてもよいでしょう。
また、Midworksでも業務委託の案件を複数取り扱っております。2024年5月時点では、業務委託の案件が794件もあるため、豊富な案件の中から自身のスキルにマッチした案件を探せます。最短1日で案件参画できる案件もあるので、ご気軽にご相談ください。
関連記事
フリーランスのキャリア


SAPフリーランス単価相場は?市場価値のあるスキルや資格も紹介

AWSフリーランス単価相場で知る|市場価値と高収入戦略
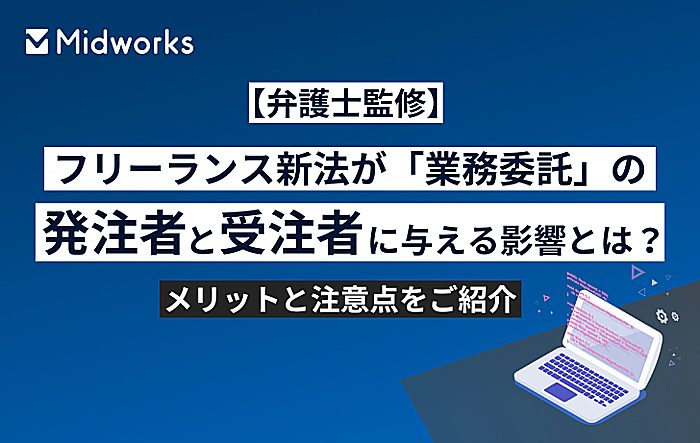
【弁護士監修】フリーランス新法が「業務委託」の発注者と受注者に与える影響とは?メリットと注意点をご紹介
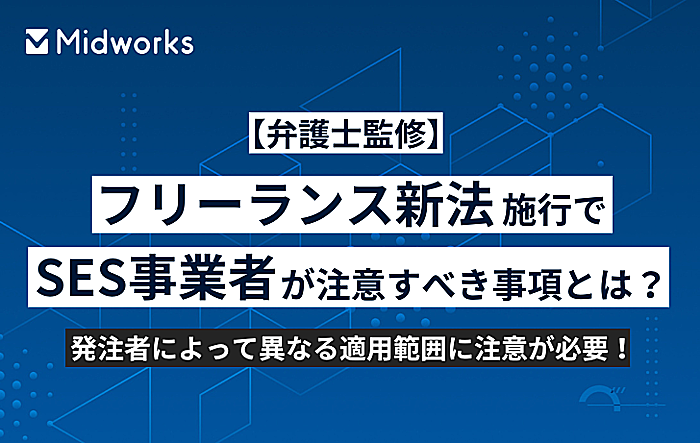
【弁護士監修】フリーランス新法施行でSES事業者が注意すべき事項とは?発注者によって異なる適用範囲に注意が必要!
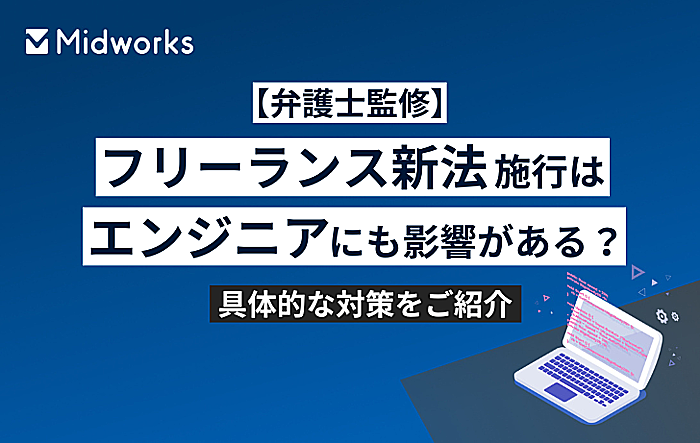
【弁護士監修】フリーランス新法施行はエンジニアにも影響がある?具体的な対策をご紹介
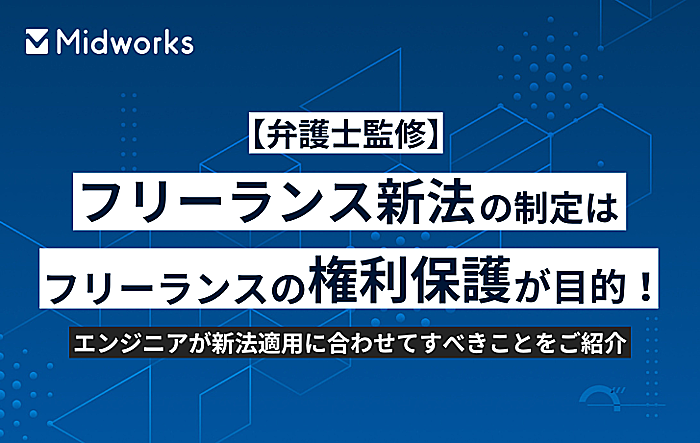
【弁護士監修】フリーランス新法の制定はフリーランスの権利保護が目的!エンジニアが新法適用に合わせてすべきことをご紹介
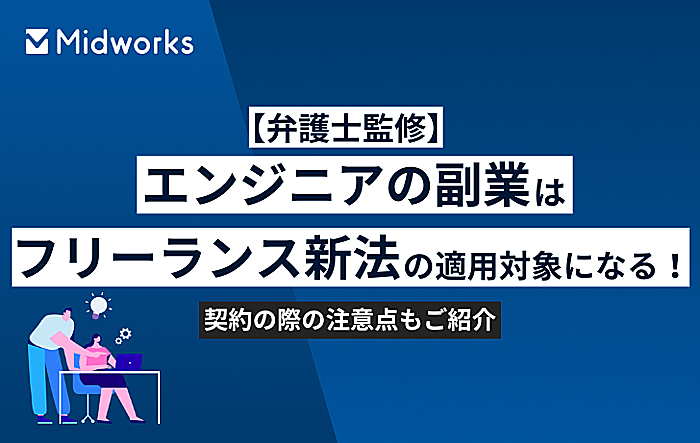
【弁護士監修】エンジニアの副業はフリーランス新法の適用対象になる!契約の際の注意点もご紹介
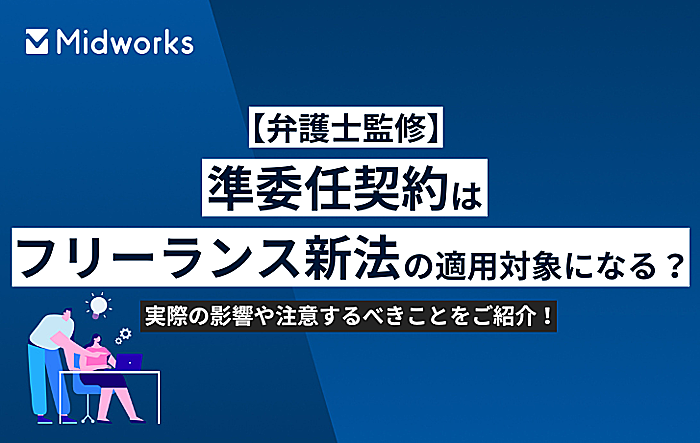
【弁護士監修】準委任契約はフリーランス新法の適用対象になる?実際の影響や注意するべきことをご紹介!
インタビュー


紹介からたった1週間で現場にフリーランスが参画!スピード感で人手不足を解消-株式会社アイスリーデザイン様
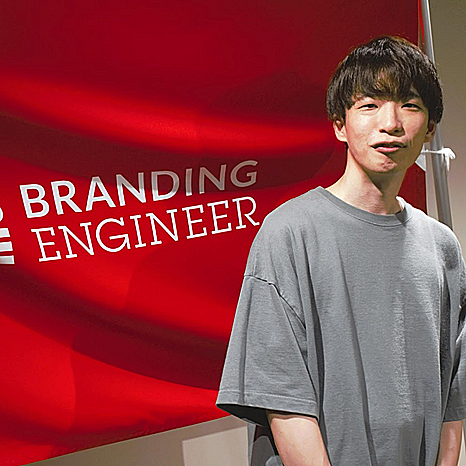
受託開発企業から、フリーランスで自社開発企業へ!

事業の成長スピードに現場が追い付かないという悩みをMidworks活用で解決-株式会社Algoage様
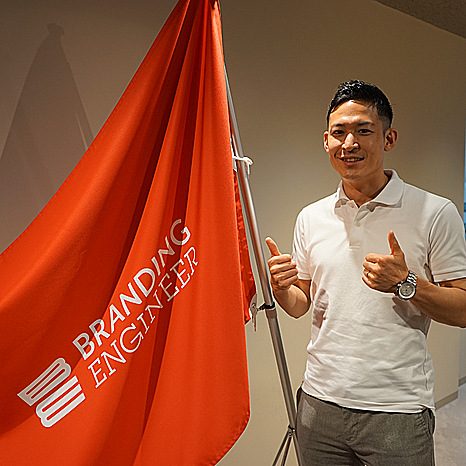
30代でも遅くない!未経験からエンジニアへのジョブチェンジで天職と巡り合った、英語が喋れる元消防士のフリーランスへの挑戦

フリーランスに転向し収入も生活も向上 アップデートを続けるエンジニアの情報収集方法を公開
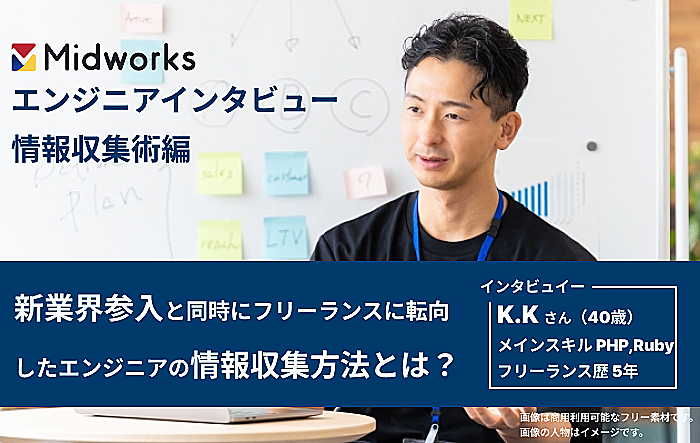
新業界参入と同時にフリーランスに転向したエンジニアの情報収集方法とは?
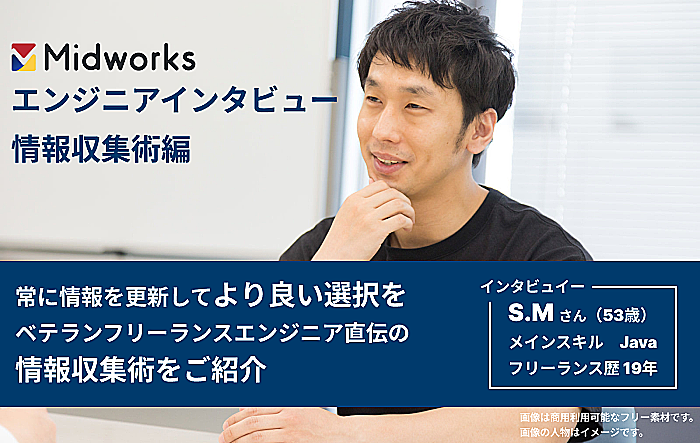
常に情報を更新してより良い選択を ベテランフリーランスエンジニア直伝の情報収集術をご紹介
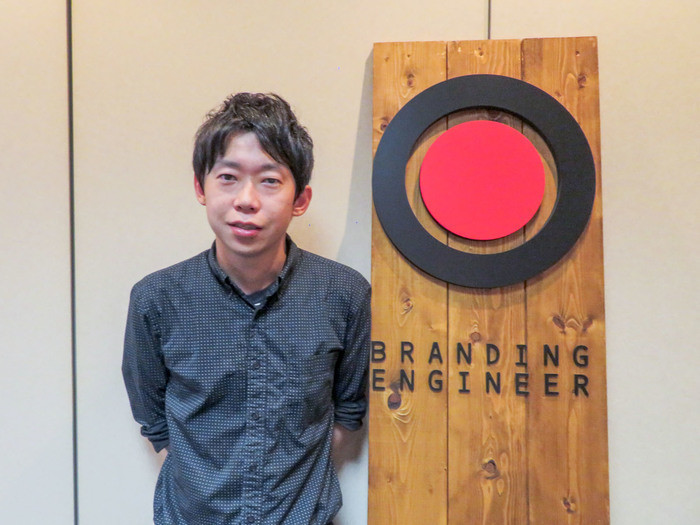
理想的なエンジニア像を描き、自由な働き方を求めてフリーランスへ。
フリーランスの基礎知識


何年の経験でフリーランスエンジニアは案件を獲得できる?未経験の場合についても解説

20代前半でもフリーランスエンジニアになれる?平均年収やメリット・デメリット

副業フリーランスはおすすめ?未経験からの始め方やメリット・デメリットを解説

【初心者におすすめ】ITパスポート試験で合格点は?合格に近づく勉強法

IT業界の現状は?市場規模や今後の動向についても解説!

フリーランスのソフトウェア開発に求められる「12のこと」をご紹介!必要なスキルも解説

【職種別】フリーランスエンジニアの年収一覧!年代やプログラマーの言語別にも紹介
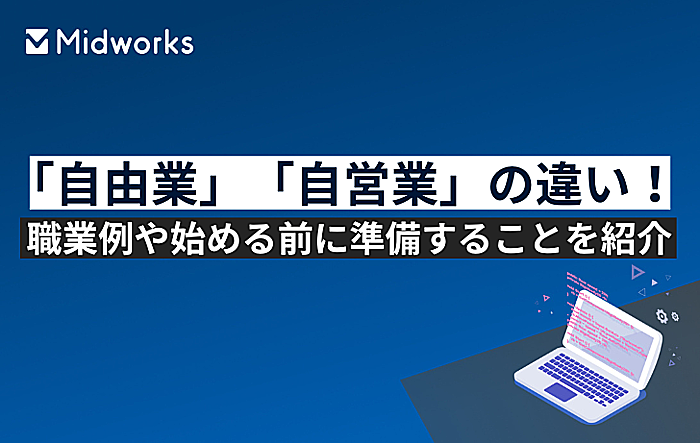
実は知られていない「自由業」「自営業」の違い!職業例や始める前に準備することを紹介
プログラミング言語

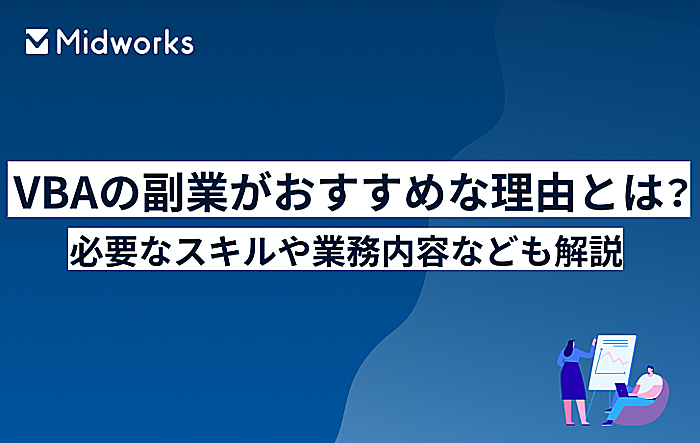
VBAの副業がおすすめな理由とは?必要なスキルと業務内容・案件の探し方も解説
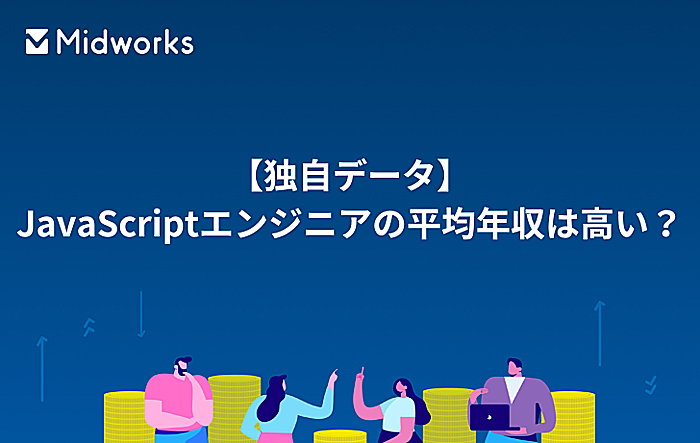
【独自データ】JavaScriptエンジニアの平均年収は高い?年収を上げる方法もご紹介
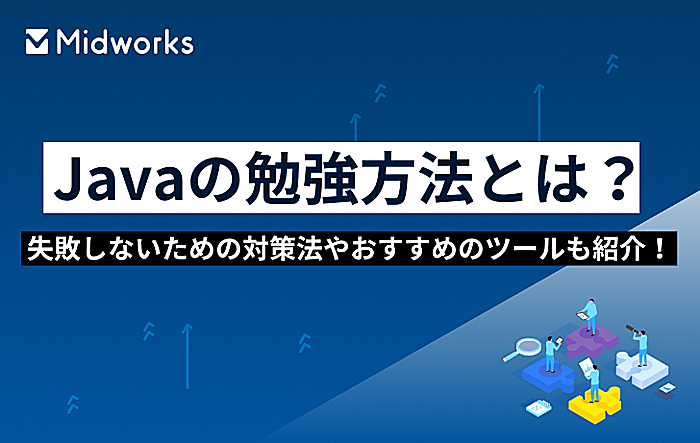
Javaの勉強方法とは?失敗しないための対策法やおすすめのツールも紹介!

【独自データ】PHPエンジニアの年収は高い?年収を上げるための方法もご紹介!
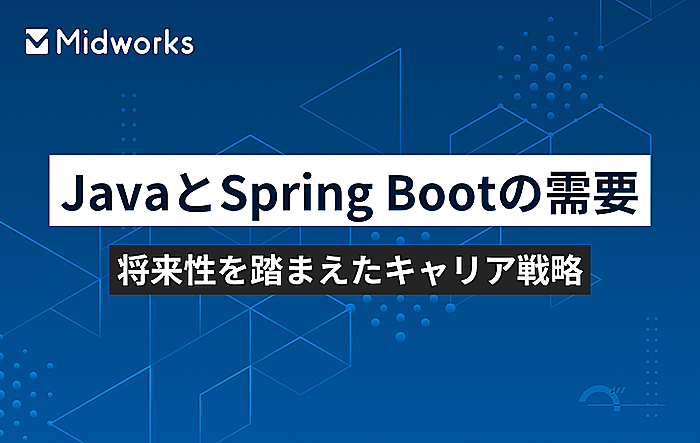
Title JavaとSpring Bootの需要|将来性を踏まえたキャリア戦略

Java Gold資格の難易度とキャリア価値を徹底解説
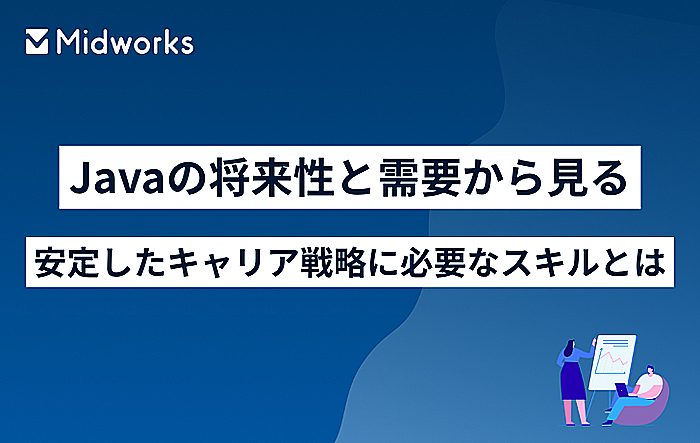
Javaの将来性と需要から見る|安定したキャリア戦略に必要なスキルとは
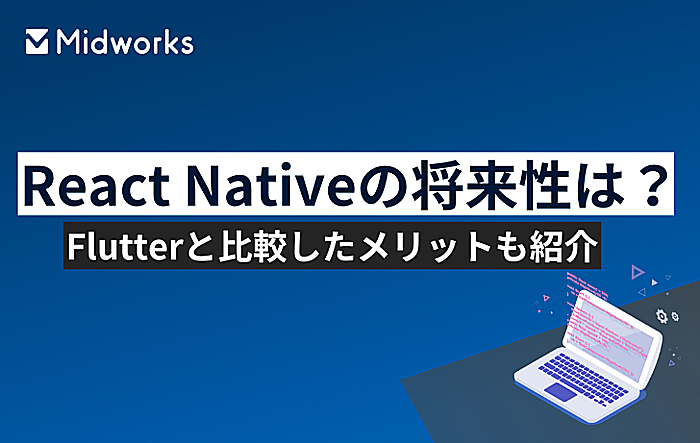
React Nativeの将来性は?Flutterと比較したメリットも紹介
企業向け情報

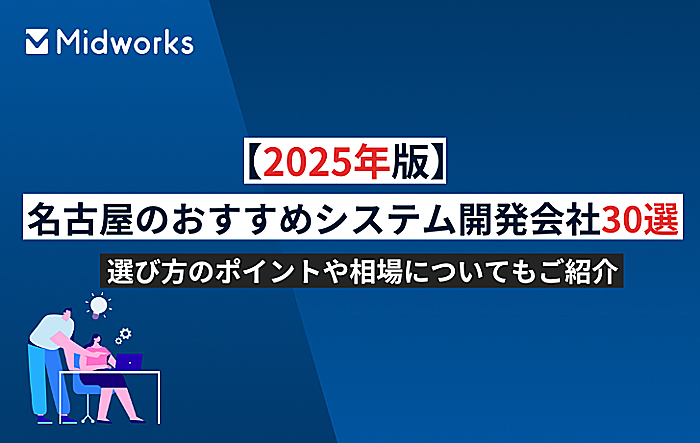
【2025年版】名古屋のおすすめシステム開発会社30選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
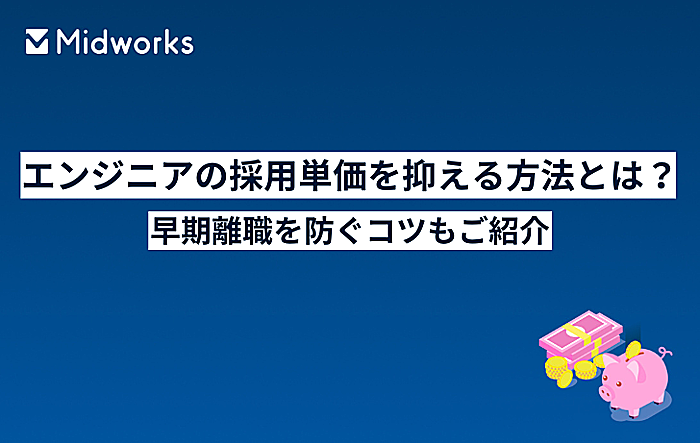
エンジニアの採用単価を抑える方法とは?早期離職を防ぐコツもご紹介
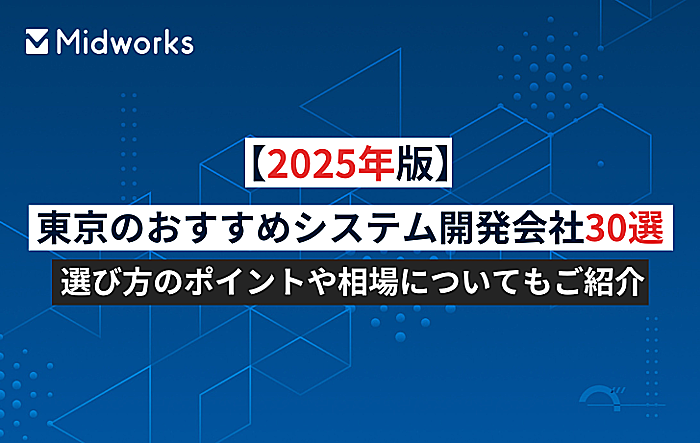
【2025年版】東京のおすすめシステム開発会社30選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
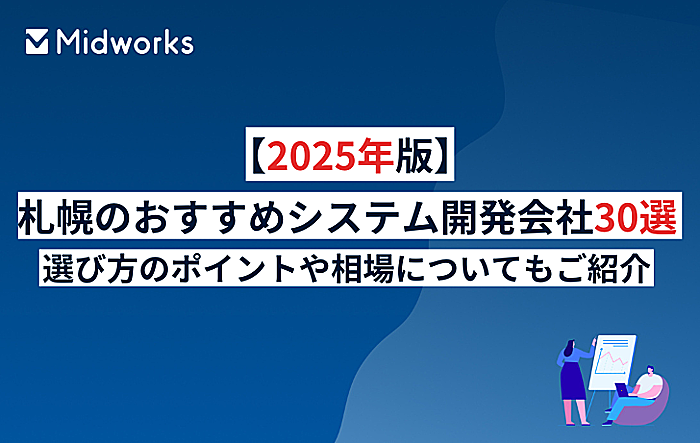
【2025年版】札幌のおすすめシステム開発会社30選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
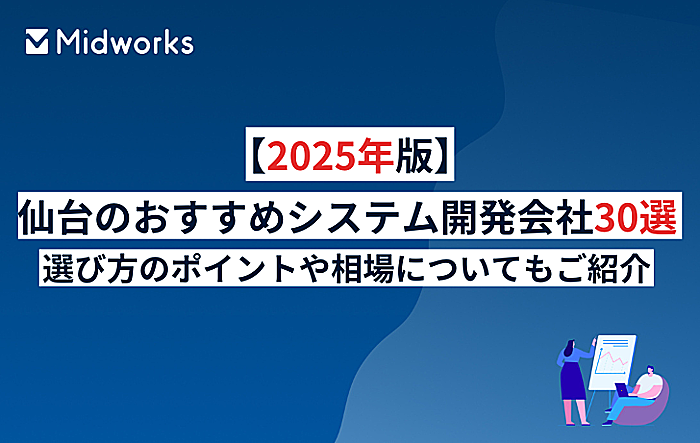
【2025年版】仙台のおすすめシステム開発会社30選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
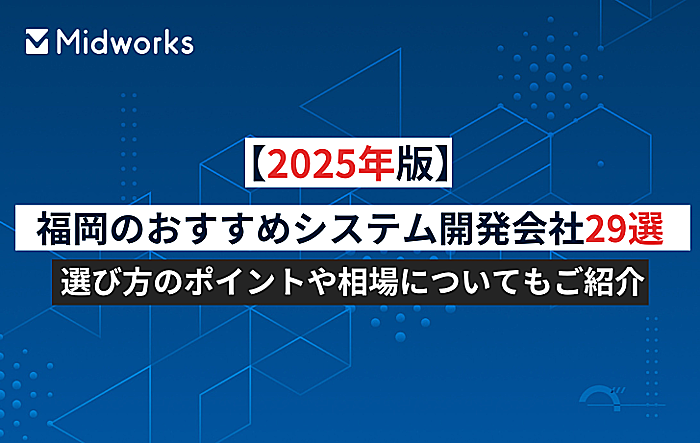
【2025年版】福岡のおすすめシステム開発会社29選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
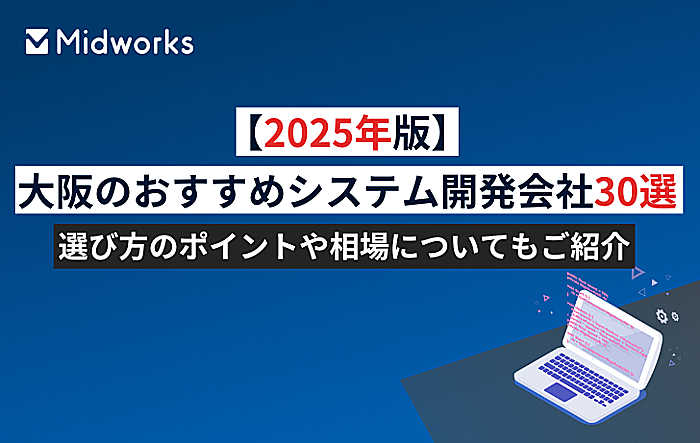
【2025年版】大阪のおすすめシステム開発会社30選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
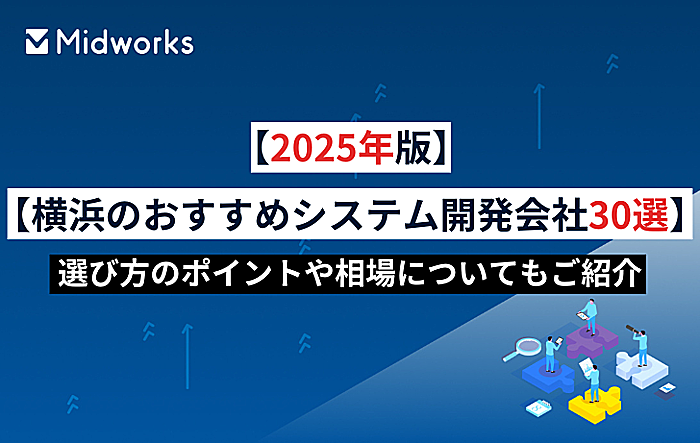
【2025年版】横浜のおすすめシステム開発会社30選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
業界特集


医療業界のフリーランスエンジニア向け案件特集|DX化が進む成長市場で求められるスキルと働き方のポイント

自動車業界フリーランスエンジニア案件特集|CASE時代の開発をリード!求められる技術とプロジェクト事例

EC業界のフリーランスエンジニア向け案件特集|急成長業界で必要とされるスキルや働き方のポイントもご紹介

セキュリティ業界のフリーランスエンジニア向け案件特集|案件参画で身につくスキルや参画の際に役立つ資格もご紹介

金融業界(Fintech領域)のフリーランスエンジニア向け案件特集|業界未経験でも活躍する方法もご紹介

生成AI分野フリーランスエンジニア案件特集|最先端技術を駆使!注目スキルと開発プロジェクト事例

小売業界フリーランスエンジニア案件|年収アップとキャリアアップを実現!最新トレンドと案件獲得のコツ