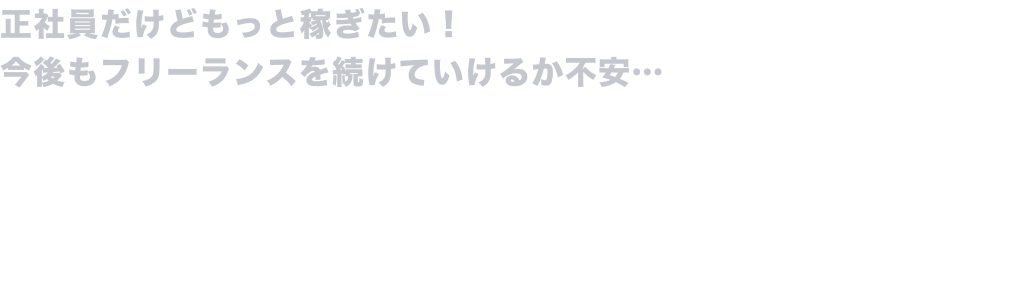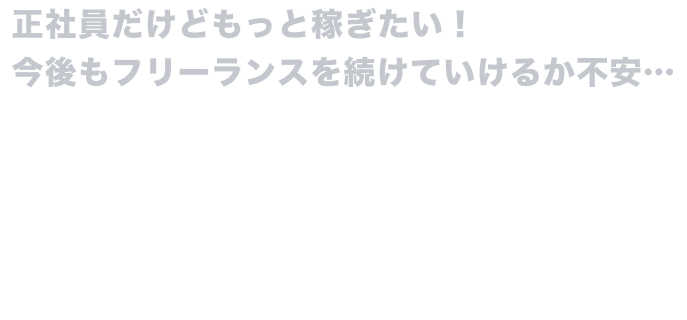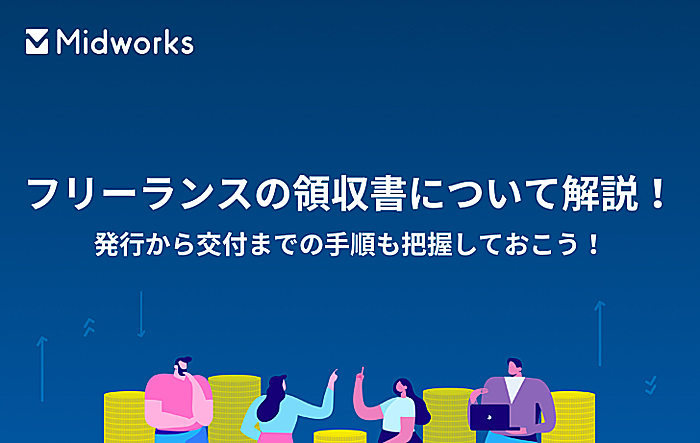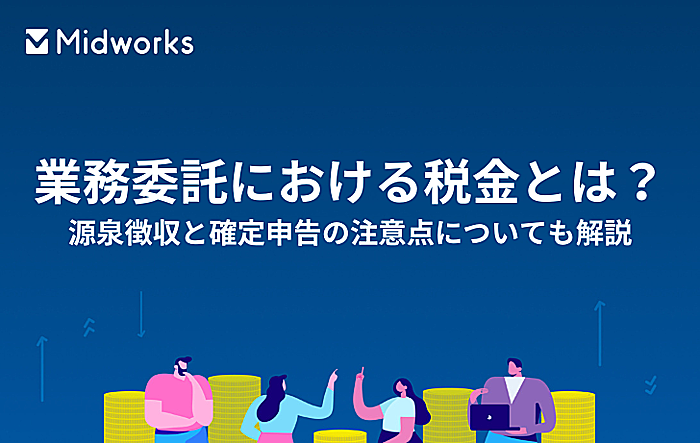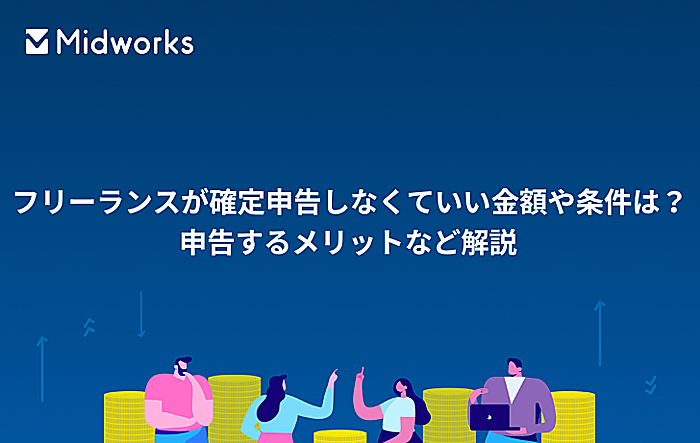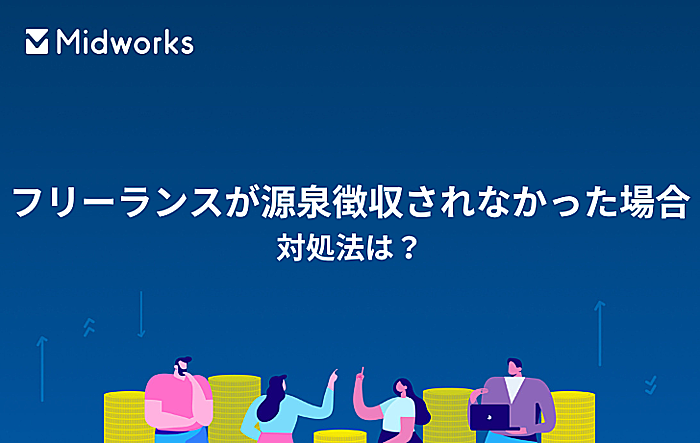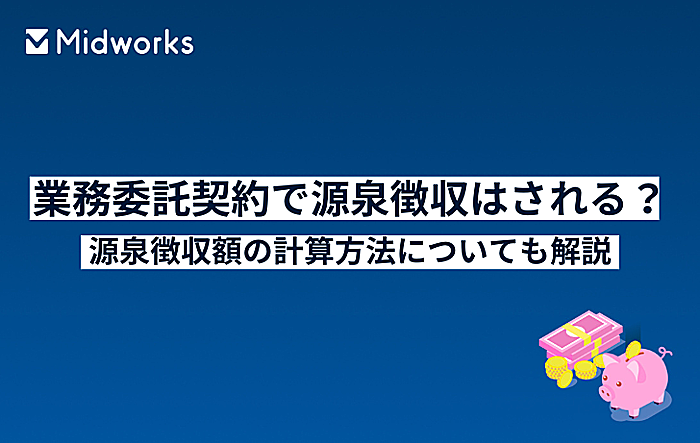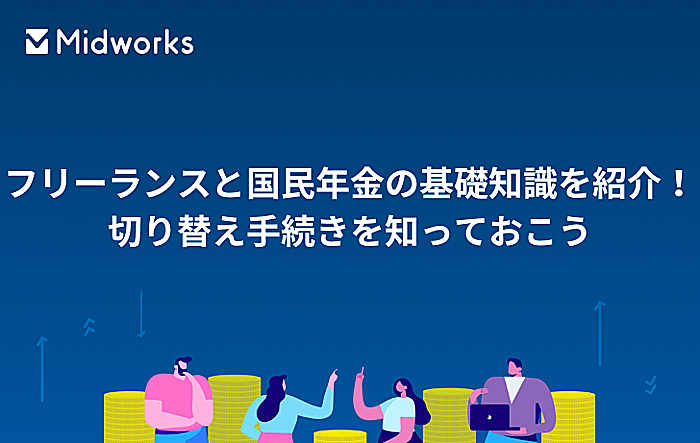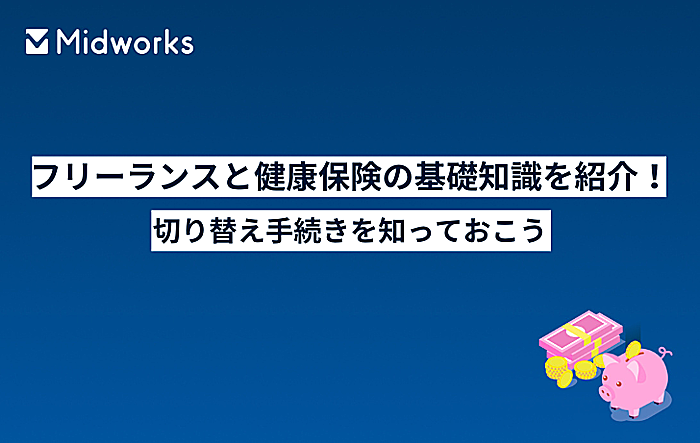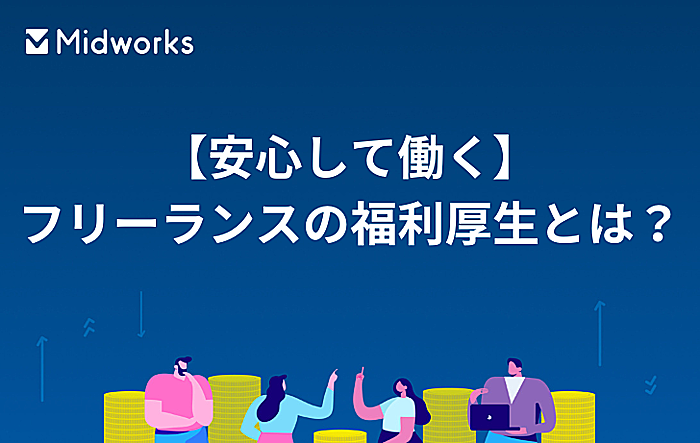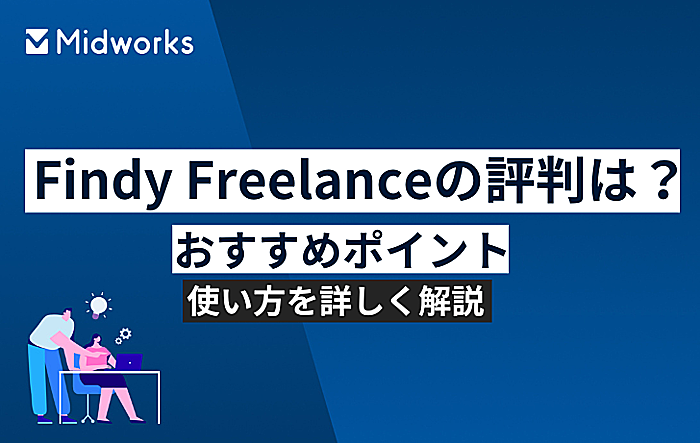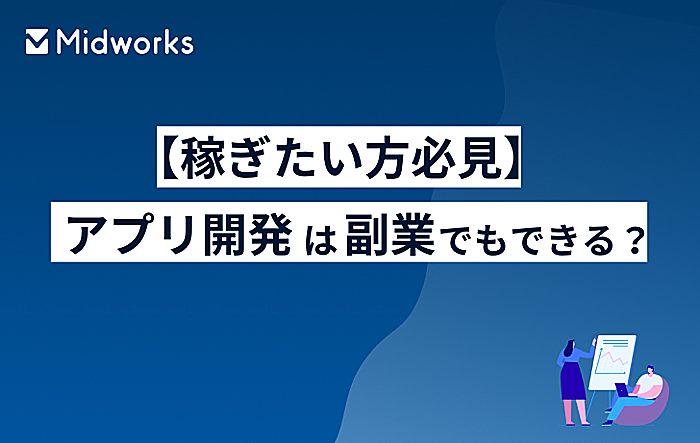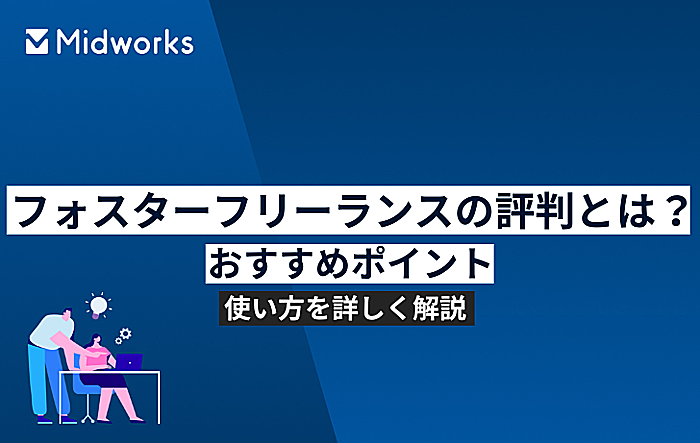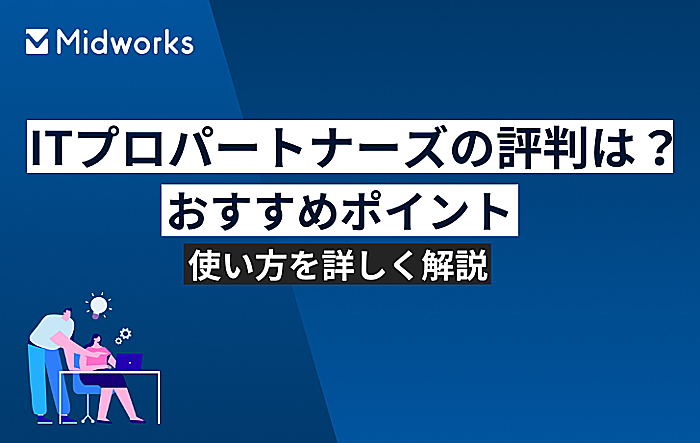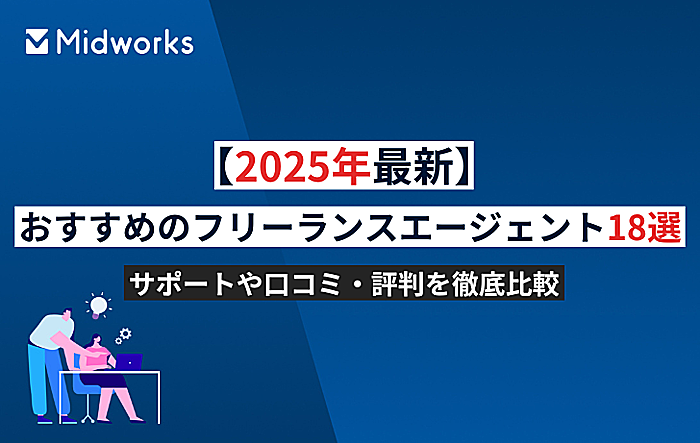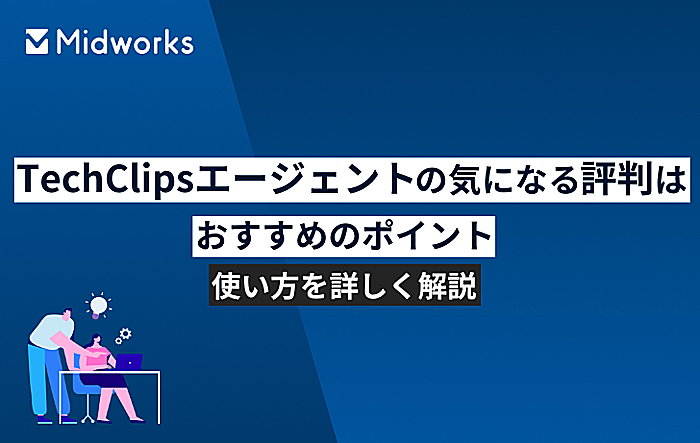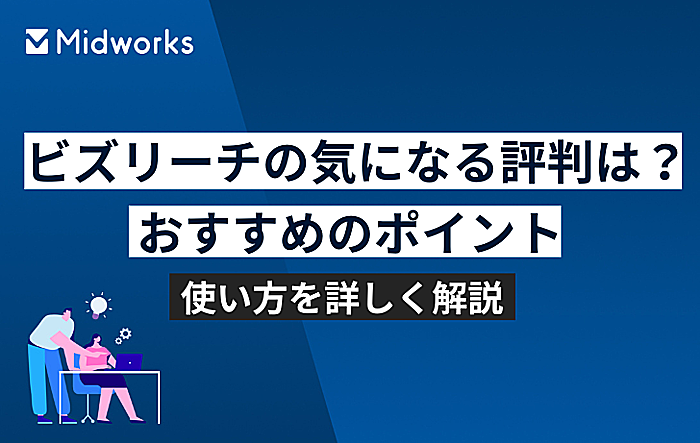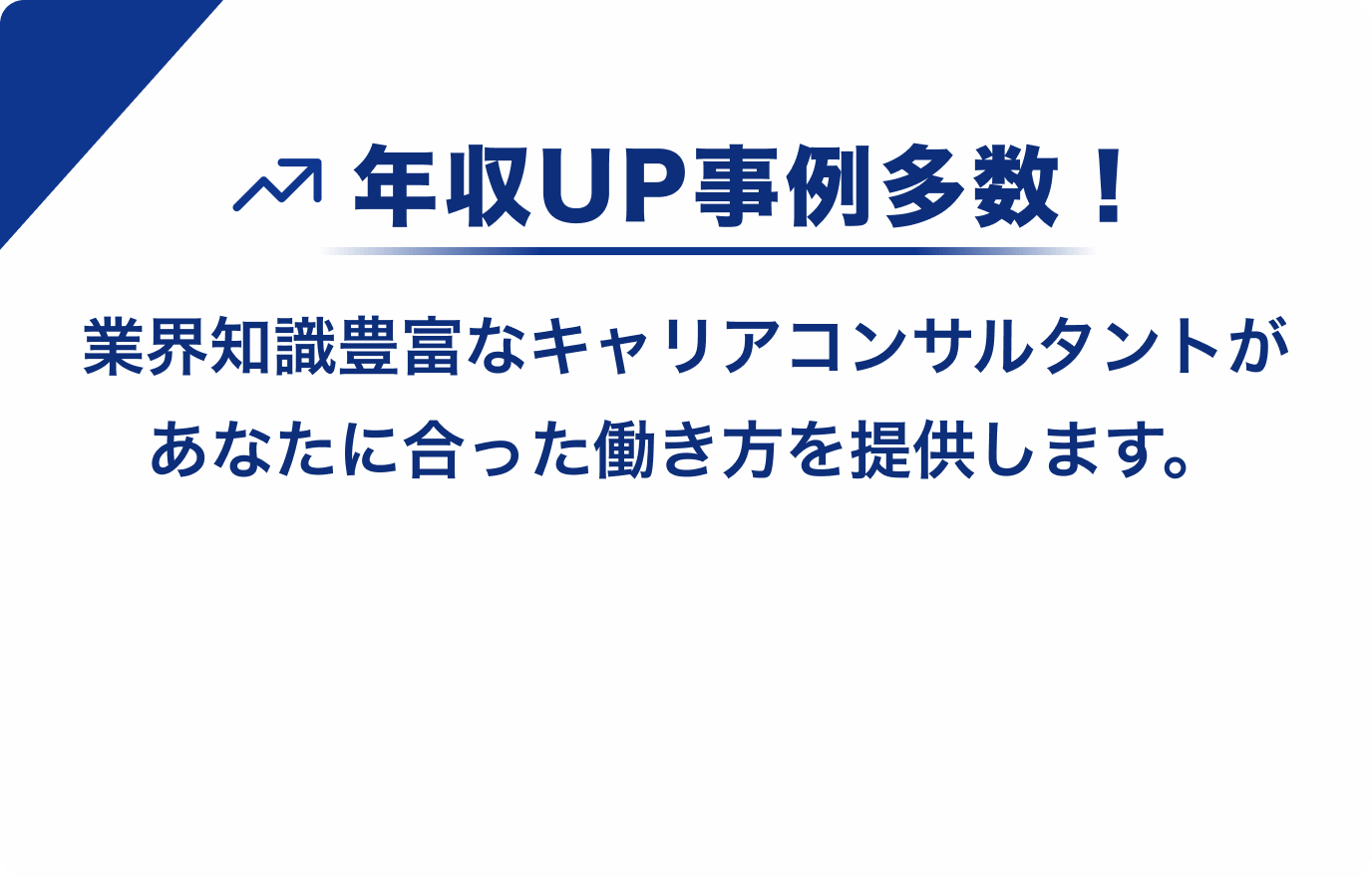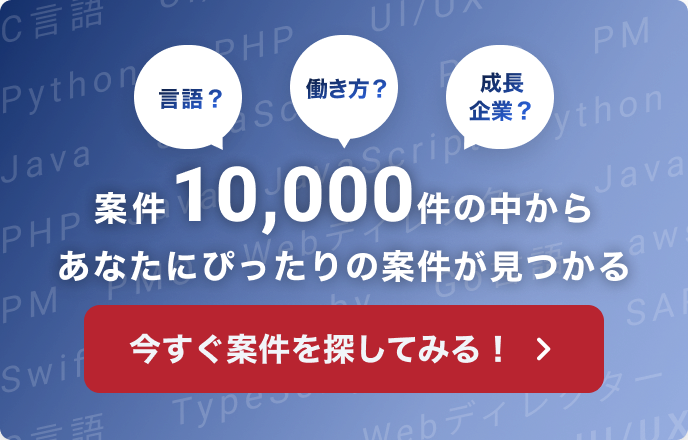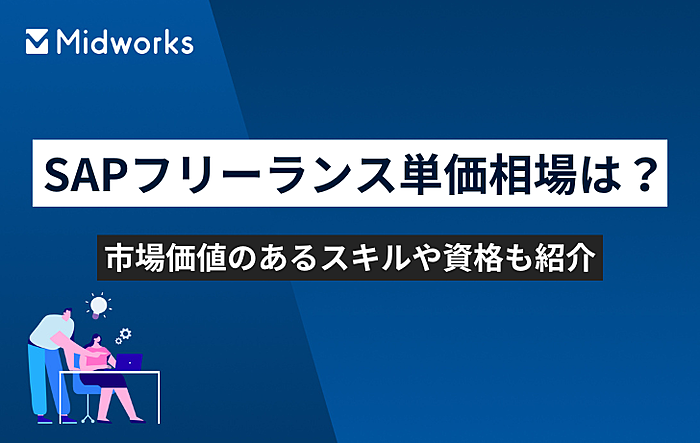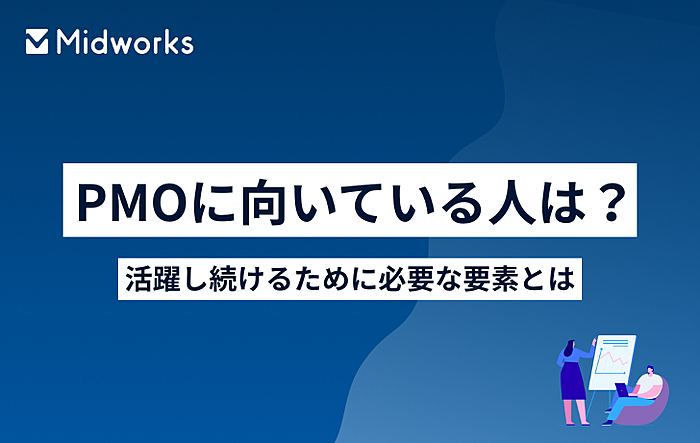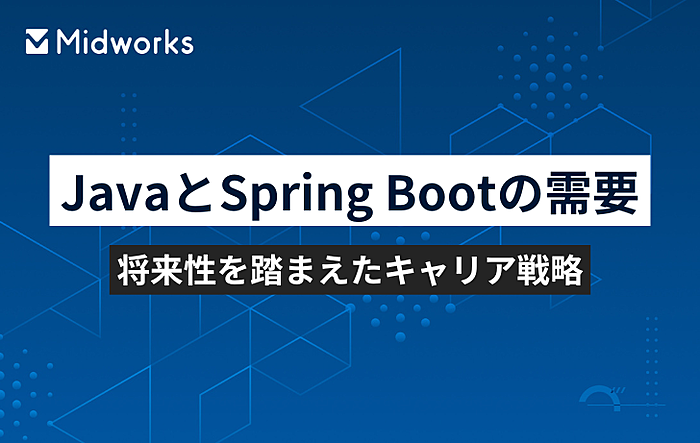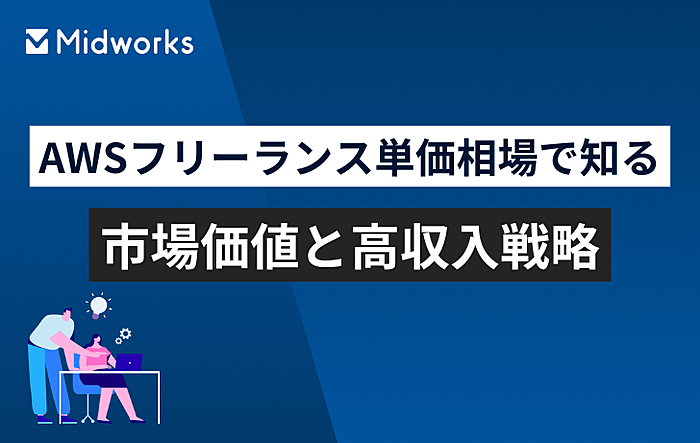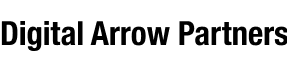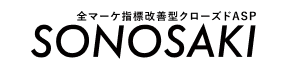「Linux関係の資格の取得にはどんなメリットがあるの?」
「種類が多くて何を取得するべきかよく分からない」
「どうやって勉強すればいいの?」
このように、Linux関係の資格の取得を検討している方には多くの疑問や悩みがあるのではないでしょうか。
本記事では、Linux関係の資格を取得するメリットや主な資格の種類と詳細、有効期限などを紹介します。
この記事を読むことで、資格を取得する意義やLinux関係の資格の概要について知ることができるでしょう。また、取得に向けた勉強方法も紹介しているので、実際に勉強を始める際の参考にもなります。
エンジニアとしてスキル・キャリアアップを目指している方は、ぜひチェックしてみてください。
目次
目次を閉じる
Linux関係の資格を取得するメリット

Linux関係の資格を取得するメリットとして以下の内容が挙げられます。それでは、それぞれのメリットについて詳しくみていきましょう。
- Linuxの技術力向上が見込める
- キャリアアップなどにつながる
- 資格によってはグローバルな活躍を目指せる
Linuxの技術力向上が見込める
資格の取得に向けて勉強する過程で、Linuxの技術力向上が見込めます。また、Linuxだけでなく、ネットワークやセキュリティなどすべてのIT技術者に求められる知識やスキルも習得できるでしょう。
キャリアアップなどにつながる
Linuxは高いシェア率を誇るOSであり、利用が進むクラウドに多く採用されていることから、今後も高い需要が続くと予想されます。
それに伴い、Linuxを扱うエンジニアの需要の高まりにも期待できるため、Linuxのスキルを証明できる資格の取得は、キャリアアップにつながるといえるでしょう。
資格によってはグローバルな活躍を目指せる
LPICは世界共通の資格で日本国外でも知名度が高いため、海外への転職活動に活かすことができます。また、LPICやLinux Foundation認定システム管理者資格、Red Hatの認定資格はグローバルな団体が運営しています。
以上から、Linux関係の資格を取得することで、グローバルな活躍に期待できるといえるでしょう。
Linuxの主な資格

ここからは、Linuxに関する4種類の資格について詳しく見ていきます。どの資格を取得するべきか迷っている方は、自身のキャリアプランと照らし合わせて、最適な資格を選ぶ際の参考にしてみてください。
世界共通資格の「LPIC」
LPICは、LPI(Linux Professional Institute)が運営する認定資格で、取得することでLinuxに関する知識とスキルを証明できます。
LPIC-1からLPIC-3の3つのレベルが存在し、LPIC-1とLPIC-2では2種類の試験の両方に合格すると認定されます。LPIC-3では4種類の試験ごとに専門の認定資格が用意されており、いずれかに合格すると、その分野のLPIC-3資格を取得できます。
LPIは180ヵ国以上で試験を実施しているため、LPICは国際的な知名度の高い認定資格といえるでしょう。
出典:Linux Professional Institute|Linux Professional Institute
参照:https://www.lpi.org/ja
| レベル | LPIC-1 | LPIC-2 | LPIC-3 |
|---|---|---|---|
| 対象試験 | 101試験、102試験 | 201試験、202試験 | 300試験(混在環境)<br>303試験(セキュリティ)<br>305試験(仮想化とコンテナ化)<br>306試験(高可用性とストレージ) |
| 試験時間 | 各90分 | 各90分 | 各90分 |
| 受験資格 | なし | LPIC-1認定の取得 | LPIC-2認定の取得 |
| 認定要件 | 101試験と102試験に合格 | 201試験と202試験に合格 | いずれかの試験に合格 |
国内向け資格の「LinuC」
LinuCは、LPI-Japanが運営する国内向けのLinux技術者認定資格です。オープンソースへの理解が求められる昨今において、LinuCを取得することは、Linux技術者に限らず、すべてのIT技術者に必要とされるスキルの証明になります。
LPICと同様にレベル1からレベル3までの3つのレベルが存在しますが、受験資格と認定要件は異なります。例えばレベル2の場合、レベル1認定を取得していなくても受験できますが、合格してもレベル1認定を取得するまで認定されません。
| レベル | LinuCレベル1 | LinuCレベル2 | LinuCレベル3 |
|---|---|---|---|
| 対象試験 | 101試験、102試験 | 201試験、202試験 | 300試験(Mixed Environment)<br>303試験(Security)<br>304試験(Virtualization & High Availability) |
| 試験時間 | 90分 | 90分 | 90分 |
| 受験資格 | なし | なし | なし |
| 認定要件 | 101試験と102試験に合格 | LinuCレベル1認定の取得<br>201試験と202試験に合格 | LinuCレベル2認定の取得<br>いずれかの試験に合格 |
世界で評価対象となり得る「Linux Foundation認定システム管理者」
Linux Foundation認定システム管理者(LFCS-JP)は、非営利の共同事業体「Linux Foundation」により開発された認定資格です。Linux Foundationはグローバルな団体であるため、世界で評価対象となり得ます。
Linux管理やオープンソースのキャリアを積みたい方を対象としており、認定を受けることで、Linuxシステム管理者に必要なシステムの設計や構成、管理のスキルを証明できます。受験するための前提条件はなく、日本語を話せる試験監督のもとで受験可能です。
難易度が高めの「Red Hat」の認定資格
Red Hat Enterprise Linuxを販売する会社「Red Hat」によっても、Linux関係の技術者認定が用意されています。認定試験の種類は豊富ですが、今回は人気の高いRHCSA(EX200)とRHCE(EX294)について紹介します。
RHCSA(EX200)は、すべてのRed Hat製品に必要なシステム管理の知識を問われる試験です。Red Hat Enterprise Linuxを用いたシステムを管理する経験豊富なエンジニアを対象としています。
RHCE(EX294)は、Red Hat Ansible Engineを使用したシステム管理の知識とスキルが問われる試験です。Red Hat Enterprise Linuxを用いたシステムを管理する熟練したエンジニアが対象で、RHCSA(EX200)の取得が受験の前提条件となります。
以上の試験はどちらも実技形式であるため、難易度が高く、座学で習得した知識よりも実践的なスキルが重要です。
LPICとLinuCで注意したい5年という期限

LPICのLPIC-1とLPIC-2では、取得から5年以内に再受験もしくは上位の資格を取得しないと有効期限が切れてしまいます。LPIC-3でも有効期限は5年です。
LinuCに関しては、認定の有効期限はありませんが、その代わり有意性の期限が存在します。有意性を維持するには、レベル1とレベル2の場合は認定日から5年以内に再認定もしくは上位の認定を取得、レベル3の場合は認定日から5年以内に再認定が必要です。
このように、LPICとLinuCでは5年という期限に注意しましょう。
出典:Linux Professional Institute LPIC-1 | Linux Professional Institute
参照:https://www.lpi.org/ja/our-certifications/lpic-1-overview
Linux関係の資格を取得するための勉強方法

ここからは、Linux関係の資格を取得するための勉強方法を紹介していきます。効率よく学習するためにも、ぜひ自分に合った勉強方法を見つけてみてください。
各資格の教材や制度を活用する
LPICではパートナーから学習サポートを受けられる制度「トレーニングパートナー」を設けています。また、LinuCでは講師から学べる「LPI-Japanアカデミック認定校制度」や自分のペースで学べる「LPI-Japan認定教材」が用意されています。
以上のような各資格で提供している教材や制度を活用すると、効率よく勉強が進むのでおすすめです。
書籍やオンライン学習サービスを利用する
Linux関係の資格を対象とした参考書は数多く出版されています。また、Red HatやLinux Foundationではオンラインで利用可能なトレーニングが無料から提供されています。
独学で資格の取得を目指したい方は、書籍やオンライン学習サービスの利用を検討してはどうでしょうか。
スクールに通う
講師から直接学びたい方には、スクールへ通うのがおすすめです。受講期間が定められているため、期間を決めて取得を目指すことができます。
Linuxを学べるスクールは数多くありますが、中にはLinuCのLPI-Japanアカデミック認定校になっているスクールも存在します。信頼性を重視する方は利用を検討してみてください。
Linux関係の資格取得を目指してみよう

今回は、Linux関係の資格を取得するメリットや資格の種類、取得するための勉強方法を紹介しました。取得したいと思える資格を見つけられたでしょうか。
取得に向けた勉強を通じて、Linux技術者だけでなく、すべてのIT技術者に必要な知識やスキルも身につきます。
Linuxは高いシェアを誇るOSであり、Linux関係の資格取得はキャリアアップに効果的なので、ぜひ取得を目指してみてください。
関連記事
フリーランスのキャリア


SAPフリーランス単価相場は?市場価値のあるスキルや資格も紹介

AWSフリーランス単価相場で知る|市場価値と高収入戦略
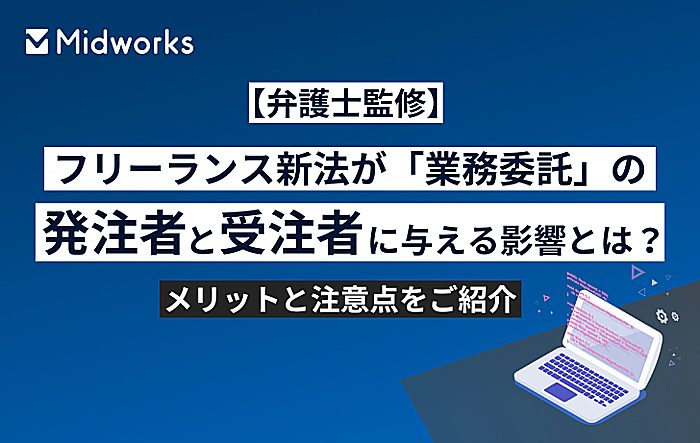
【弁護士監修】フリーランス新法が「業務委託」の発注者と受注者に与える影響とは?メリットと注意点をご紹介
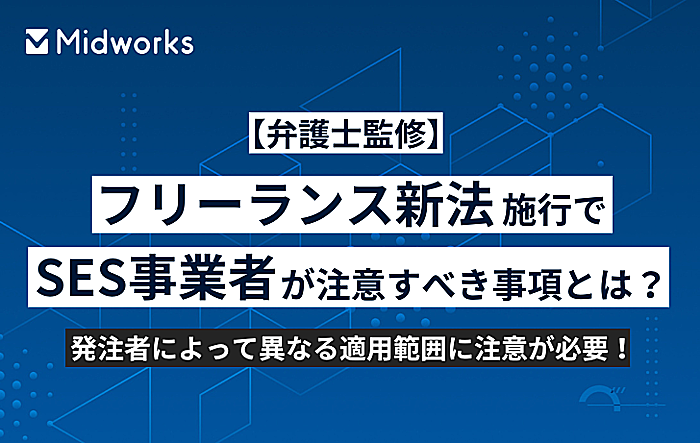
【弁護士監修】フリーランス新法施行でSES事業者が注意すべき事項とは?発注者によって異なる適用範囲に注意が必要!
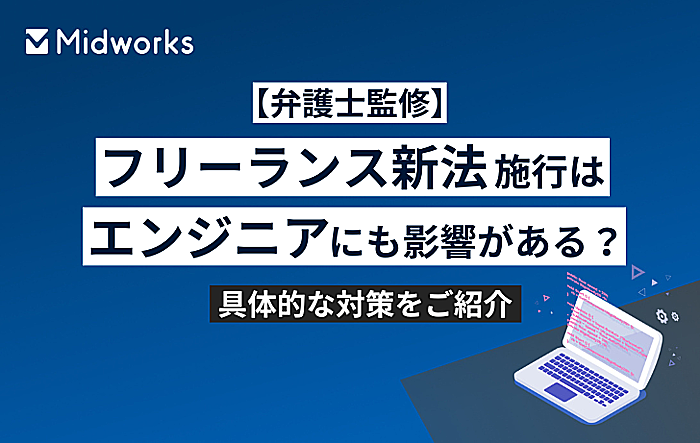
【弁護士監修】フリーランス新法施行はエンジニアにも影響がある?具体的な対策をご紹介
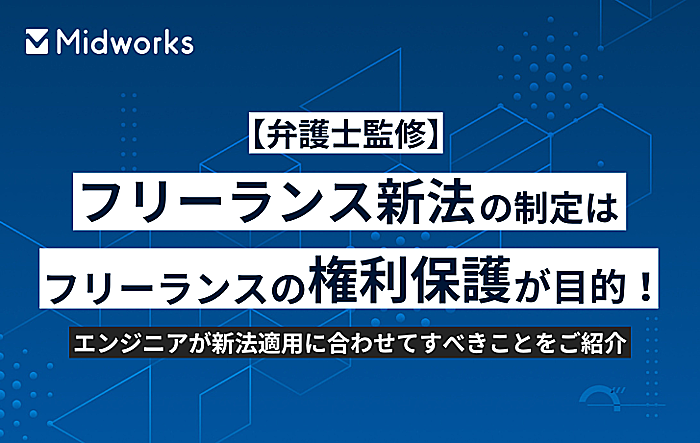
【弁護士監修】フリーランス新法の制定はフリーランスの権利保護が目的!エンジニアが新法適用に合わせてすべきことをご紹介
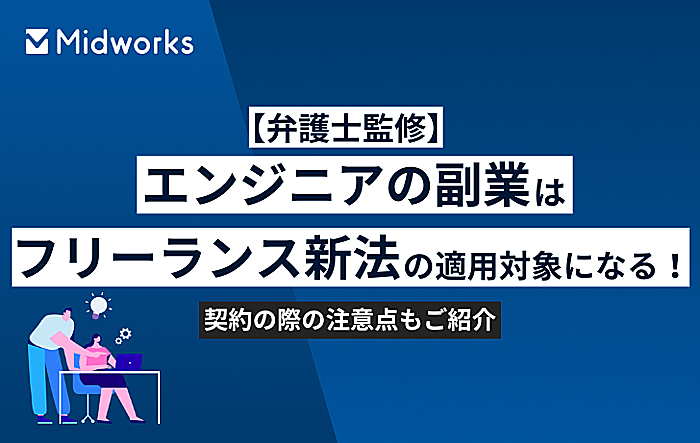
【弁護士監修】エンジニアの副業はフリーランス新法の適用対象になる!契約の際の注意点もご紹介
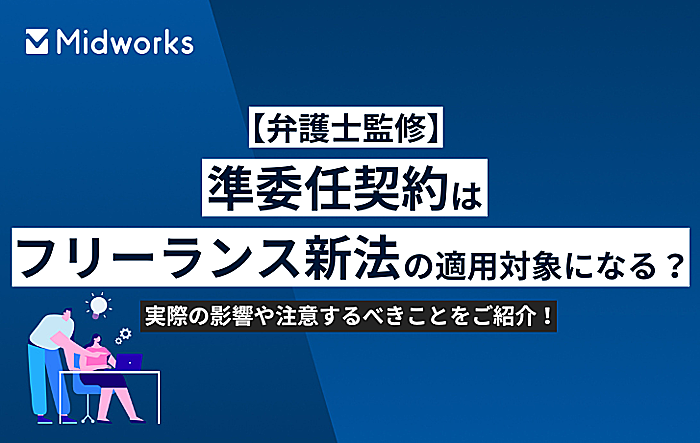
【弁護士監修】準委任契約はフリーランス新法の適用対象になる?実際の影響や注意するべきことをご紹介!
インタビュー


紹介からたった1週間で現場にフリーランスが参画!スピード感で人手不足を解消-株式会社アイスリーデザイン様
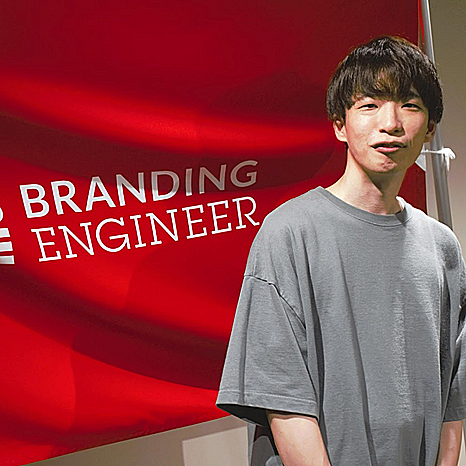
受託開発企業から、フリーランスで自社開発企業へ!

事業の成長スピードに現場が追い付かないという悩みをMidworks活用で解決-株式会社Algoage様
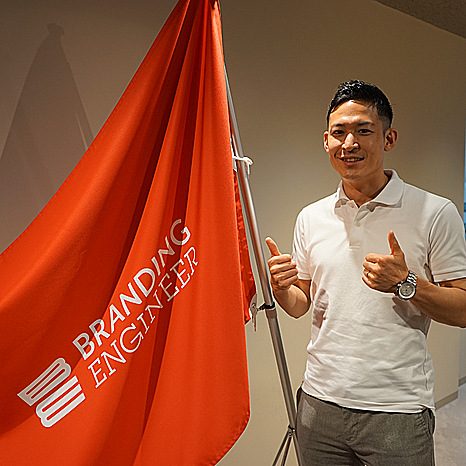
30代でも遅くない!未経験からエンジニアへのジョブチェンジで天職と巡り合った、英語が喋れる元消防士のフリーランスへの挑戦

フリーランスに転向し収入も生活も向上 アップデートを続けるエンジニアの情報収集方法を公開
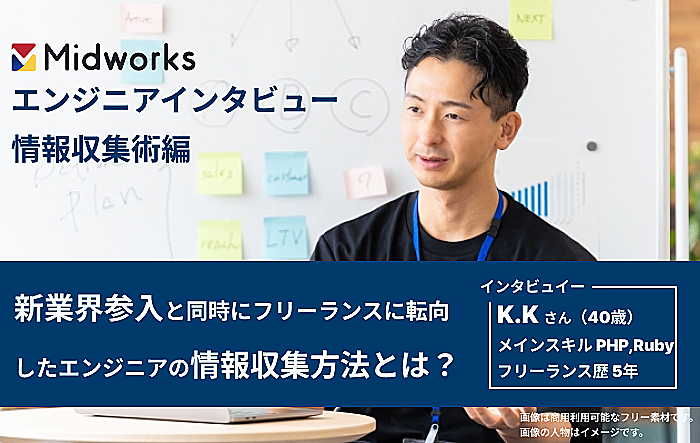
新業界参入と同時にフリーランスに転向したエンジニアの情報収集方法とは?
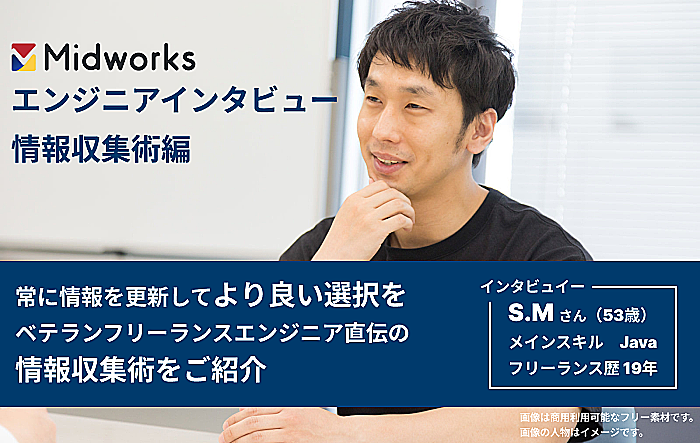
常に情報を更新してより良い選択を ベテランフリーランスエンジニア直伝の情報収集術をご紹介
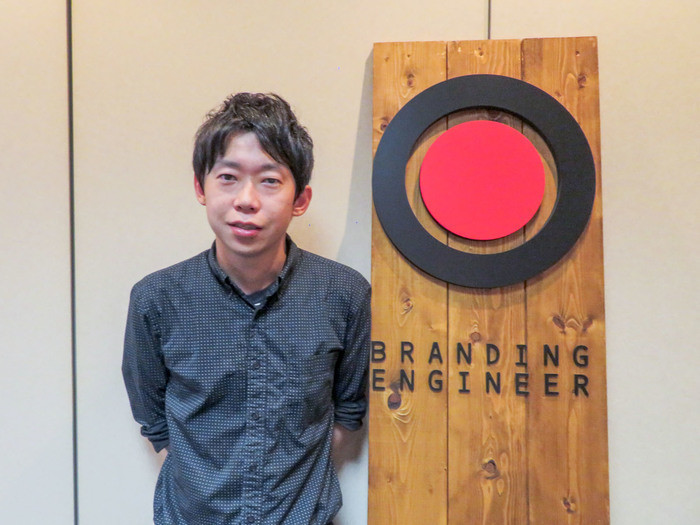
理想的なエンジニア像を描き、自由な働き方を求めてフリーランスへ。
フリーランスの基礎知識


何年の経験でフリーランスエンジニアは案件を獲得できる?未経験の場合についても解説

20代前半でもフリーランスエンジニアになれる?平均年収やメリット・デメリット

副業フリーランスはおすすめ?未経験からの始め方やメリット・デメリットを解説

【初心者におすすめ】ITパスポート試験で合格点は?合格に近づく勉強法

IT業界の現状は?市場規模や今後の動向についても解説!

フリーランスのソフトウェア開発に求められる「12のこと」をご紹介!必要なスキルも解説

【職種別】フリーランスエンジニアの年収一覧!年代やプログラマーの言語別にも紹介
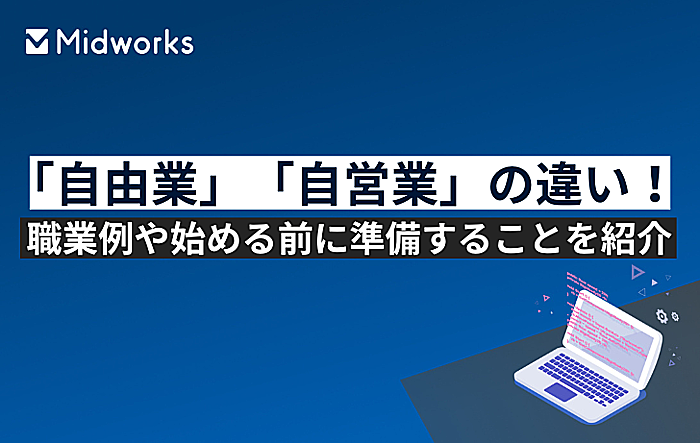
実は知られていない「自由業」「自営業」の違い!職業例や始める前に準備することを紹介
プログラミング言語

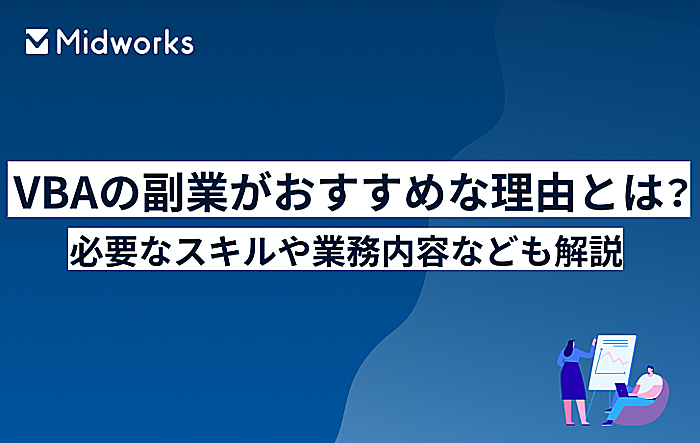
VBAの副業がおすすめな理由とは?必要なスキルと業務内容・案件の探し方も解説
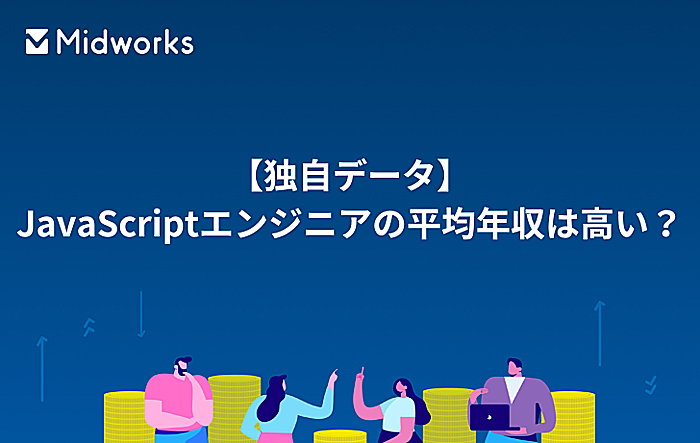
【独自データ】JavaScriptエンジニアの平均年収は高い?年収を上げる方法もご紹介
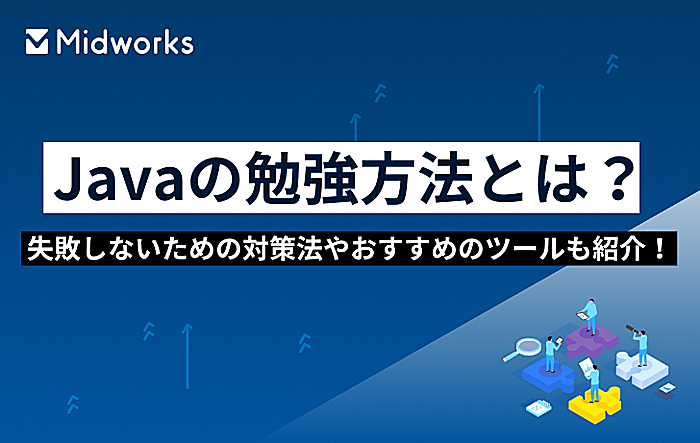
Javaの勉強方法とは?失敗しないための対策法やおすすめのツールも紹介!

【独自データ】PHPエンジニアの年収は高い?年収を上げるための方法もご紹介!
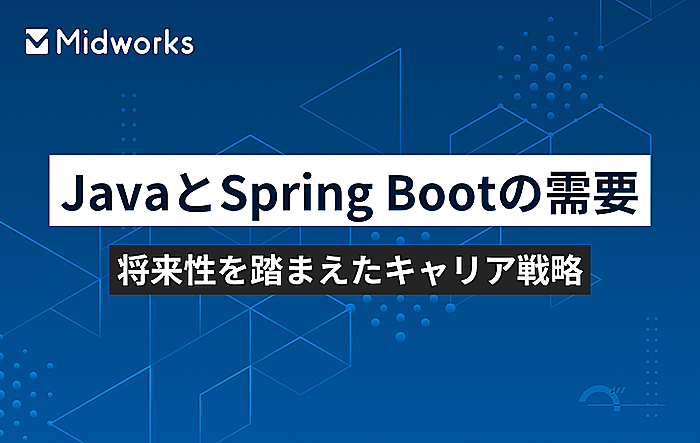
Title JavaとSpring Bootの需要|将来性を踏まえたキャリア戦略

Java Gold資格の難易度とキャリア価値を徹底解説
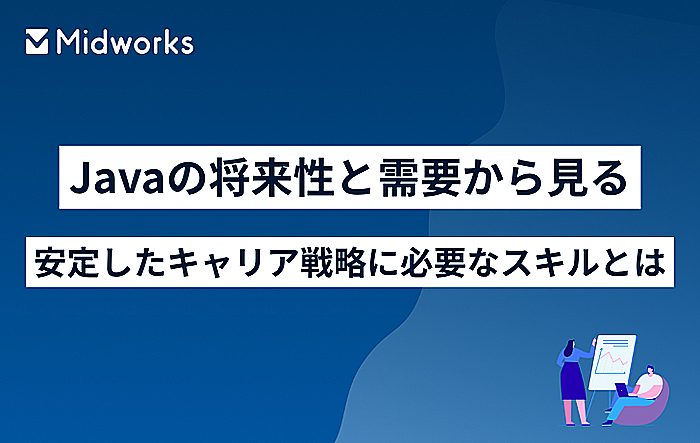
Javaの将来性と需要から見る|安定したキャリア戦略に必要なスキルとは
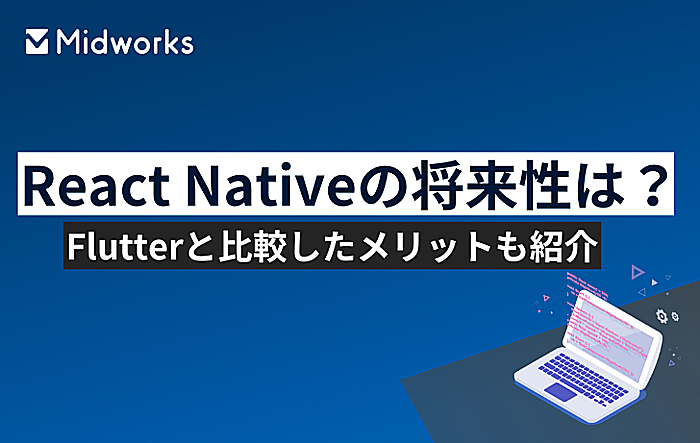
React Nativeの将来性は?Flutterと比較したメリットも紹介
企業向け情報

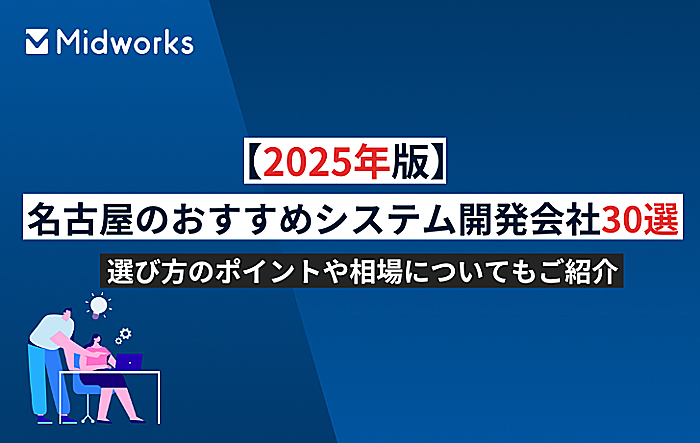
【2025年版】名古屋のおすすめシステム開発会社30選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
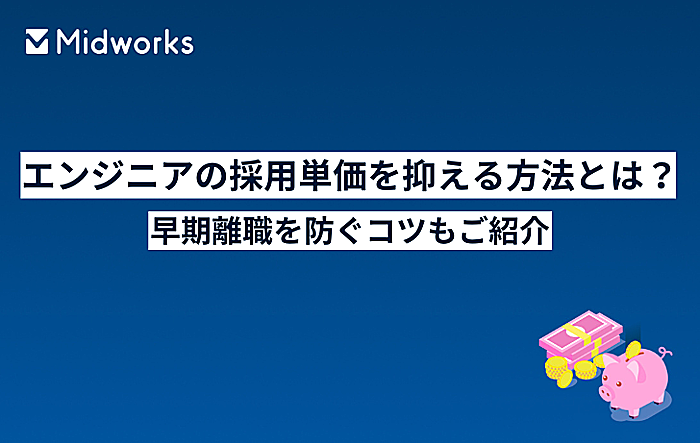
エンジニアの採用単価を抑える方法とは?早期離職を防ぐコツもご紹介
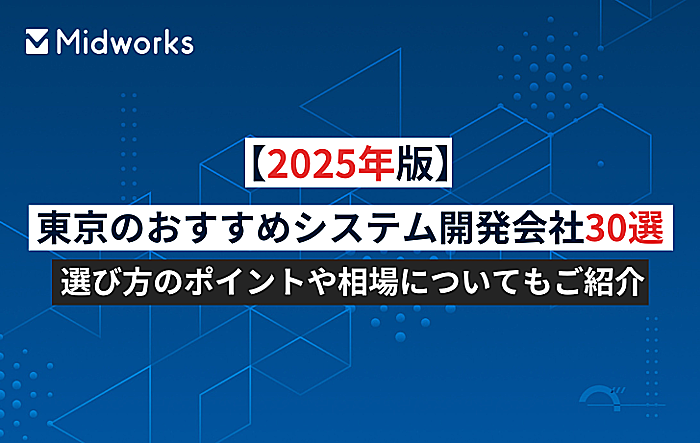
【2025年版】東京のおすすめシステム開発会社30選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
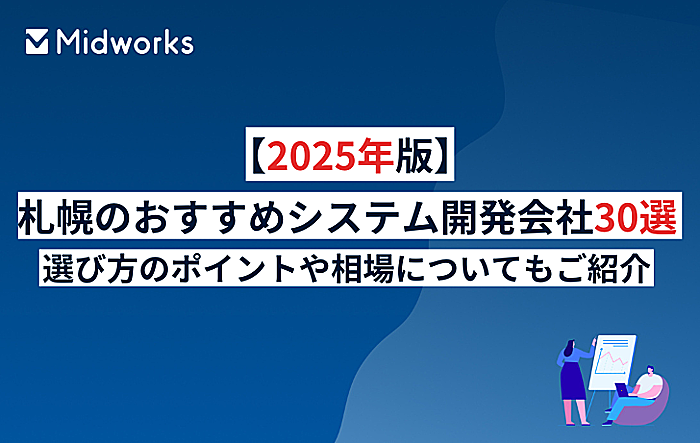
【2025年版】札幌のおすすめシステム開発会社30選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
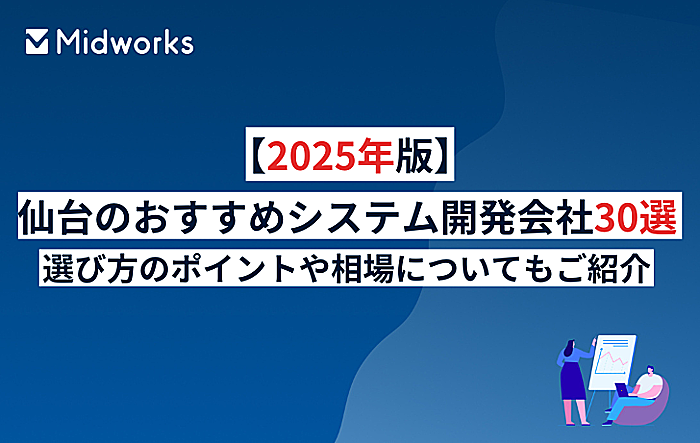
【2025年版】仙台のおすすめシステム開発会社30選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
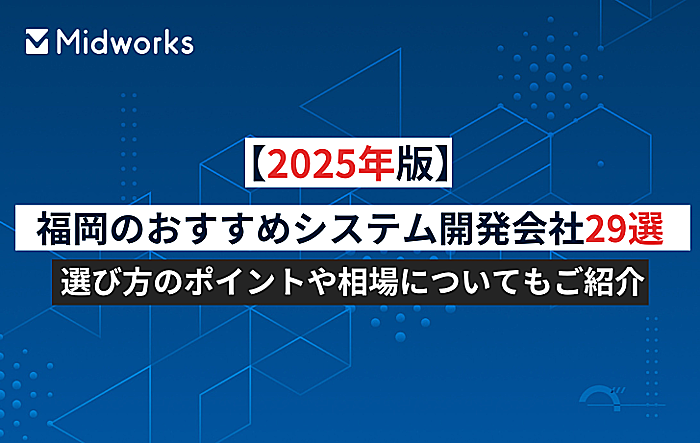
【2025年版】福岡のおすすめシステム開発会社29選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
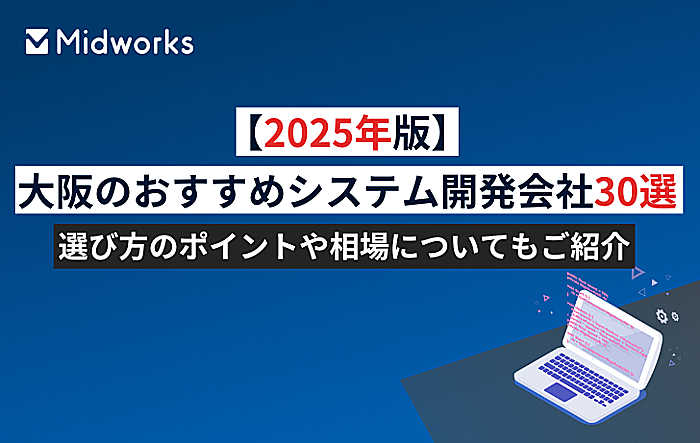
【2025年版】大阪のおすすめシステム開発会社30選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
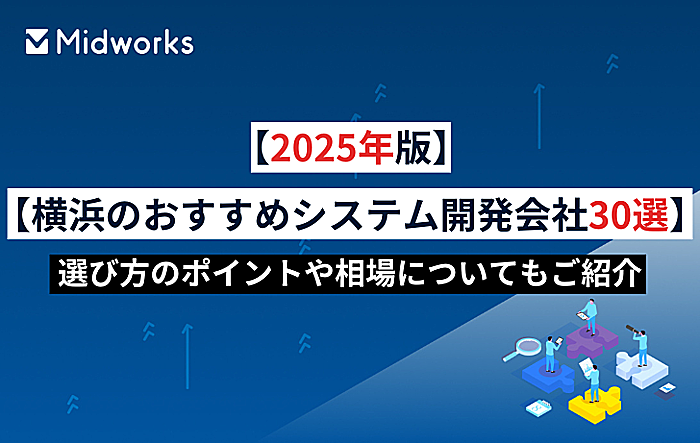
【2025年版】横浜のおすすめシステム開発会社30選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
業界特集


医療業界のフリーランスエンジニア向け案件特集|DX化が進む成長市場で求められるスキルと働き方のポイント

自動車業界フリーランスエンジニア案件特集|CASE時代の開発をリード!求められる技術とプロジェクト事例

EC業界のフリーランスエンジニア向け案件特集|急成長業界で必要とされるスキルや働き方のポイントもご紹介

セキュリティ業界のフリーランスエンジニア向け案件特集|案件参画で身につくスキルや参画の際に役立つ資格もご紹介

金融業界(Fintech領域)のフリーランスエンジニア向け案件特集|業界未経験でも活躍する方法もご紹介

生成AI分野フリーランスエンジニア案件特集|最先端技術を駆使!注目スキルと開発プロジェクト事例

小売業界フリーランスエンジニア案件|年収アップとキャリアアップを実現!最新トレンドと案件獲得のコツ