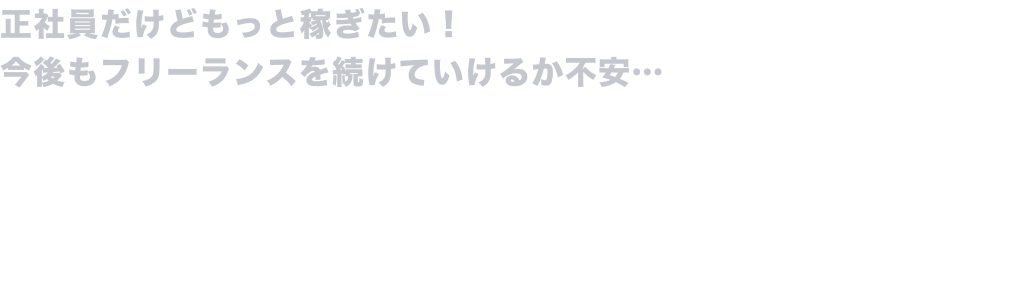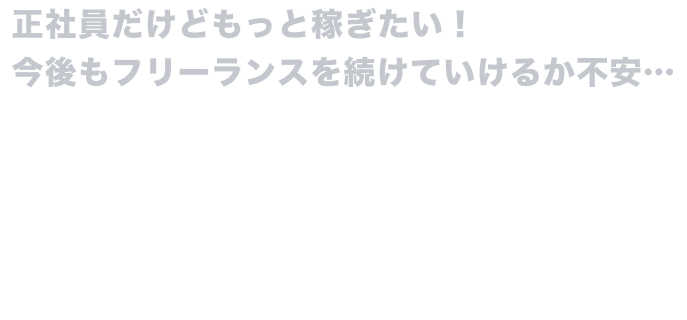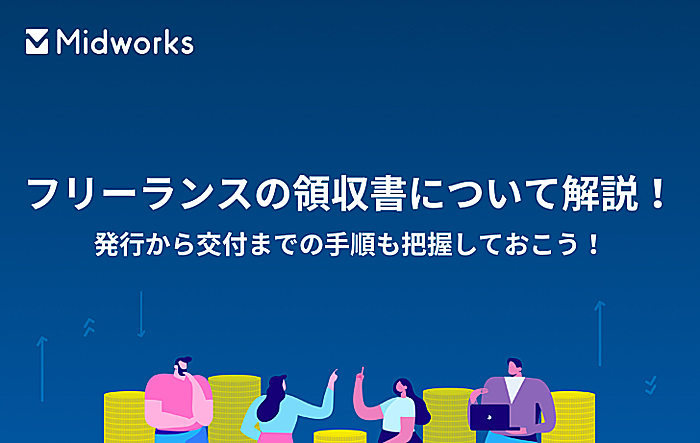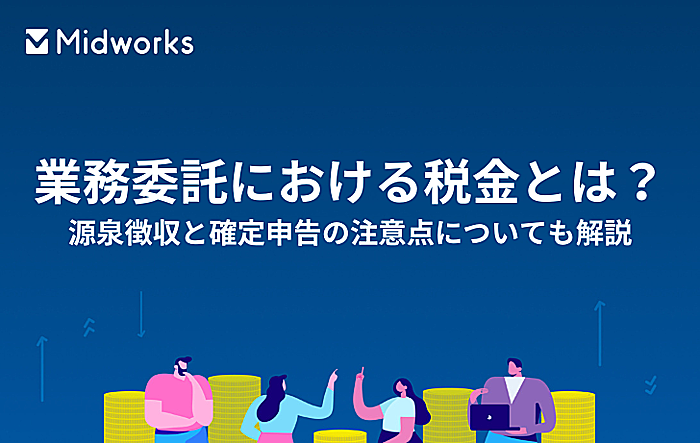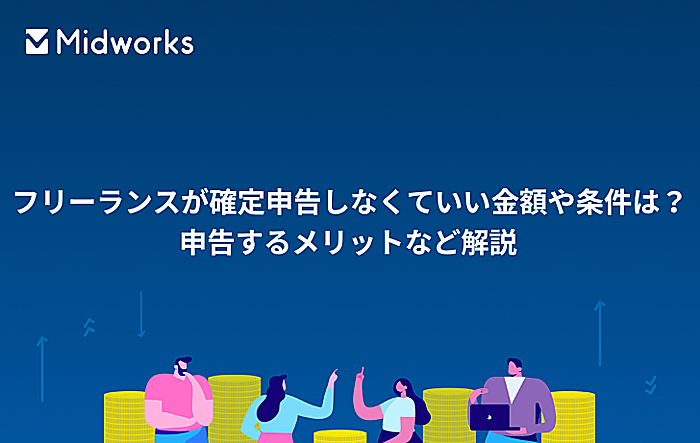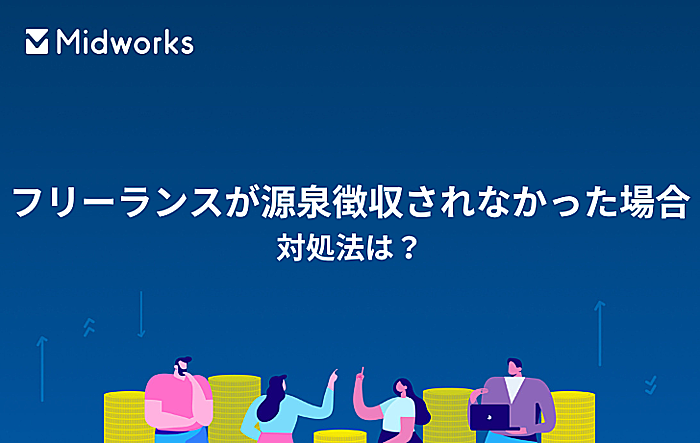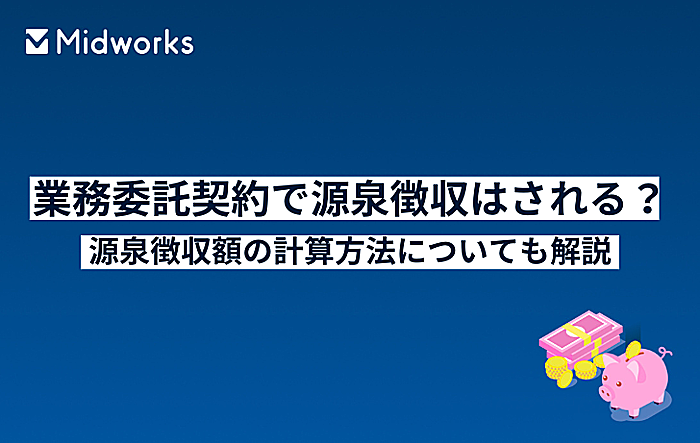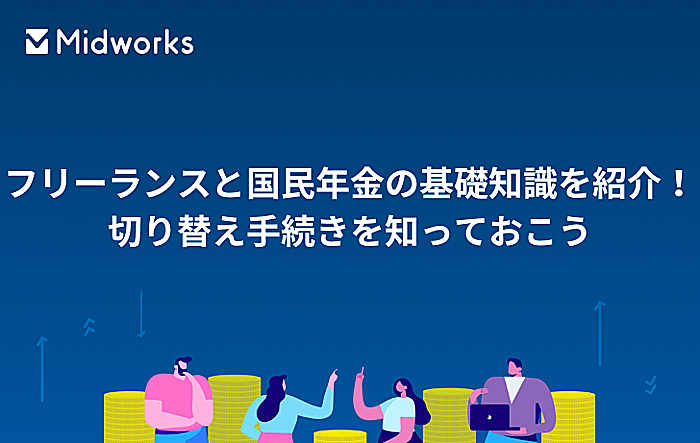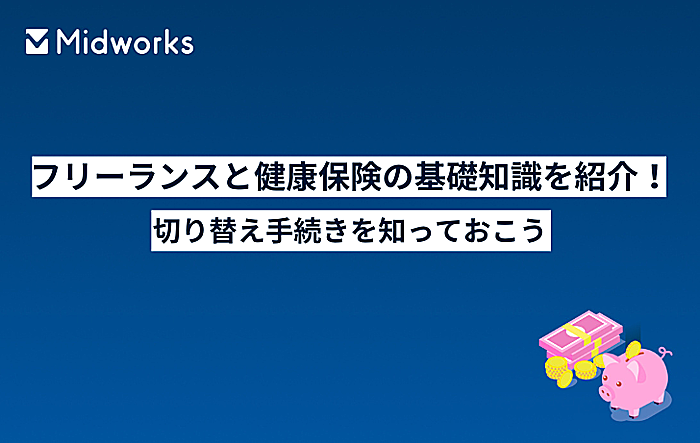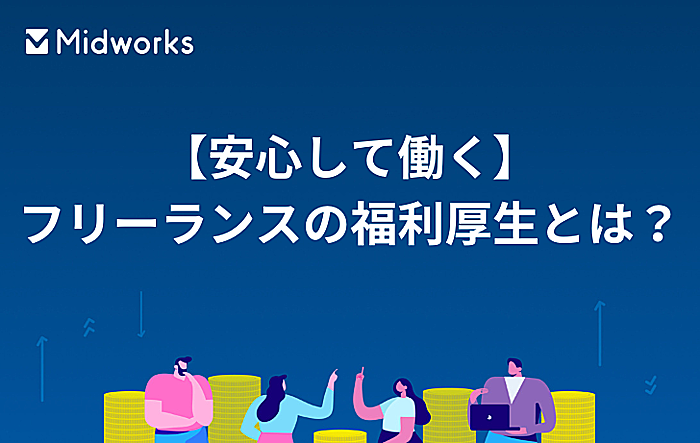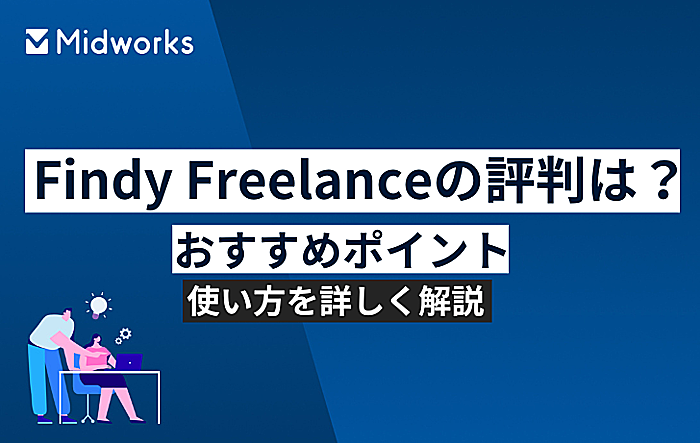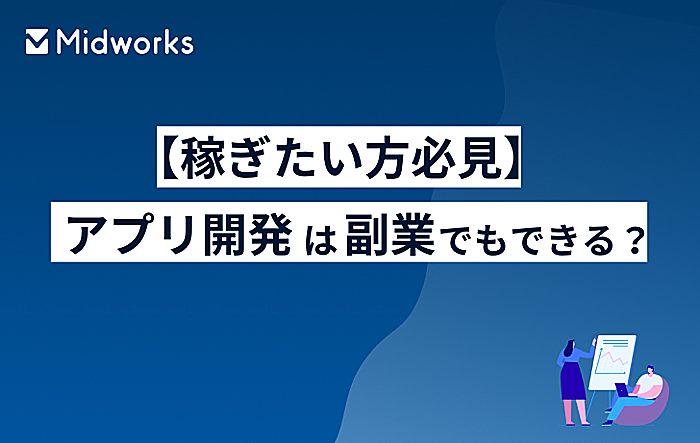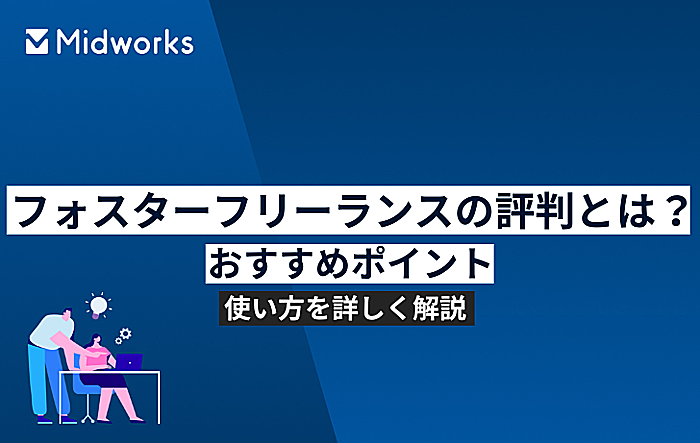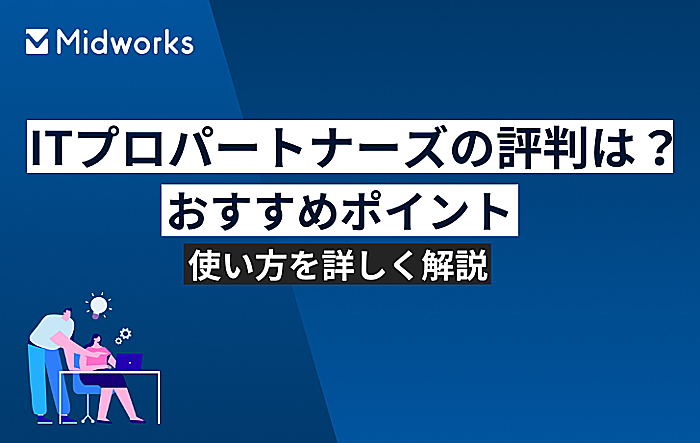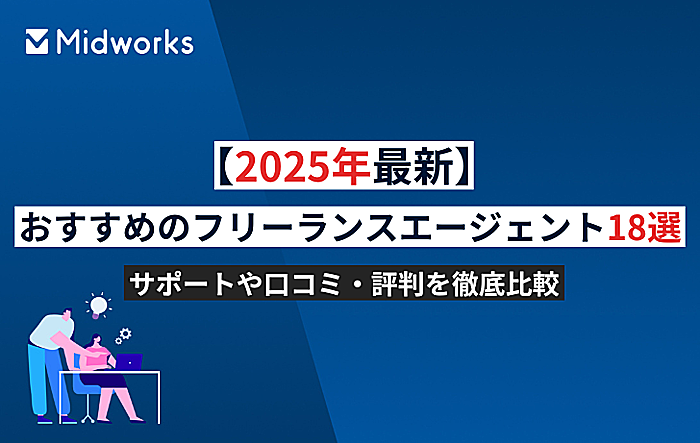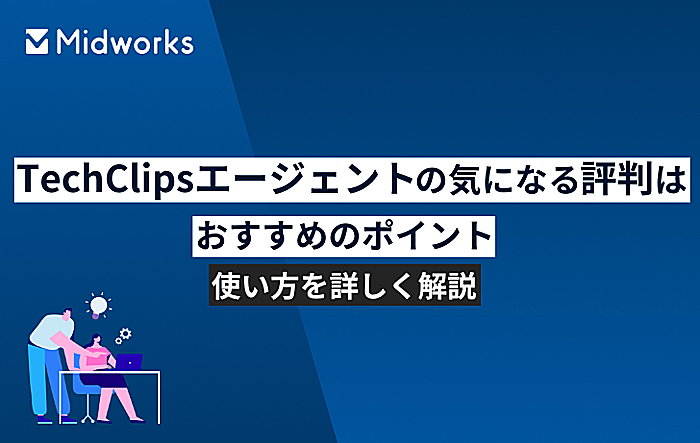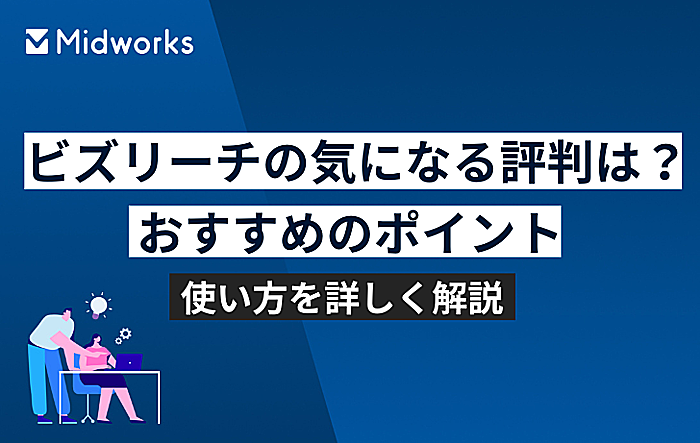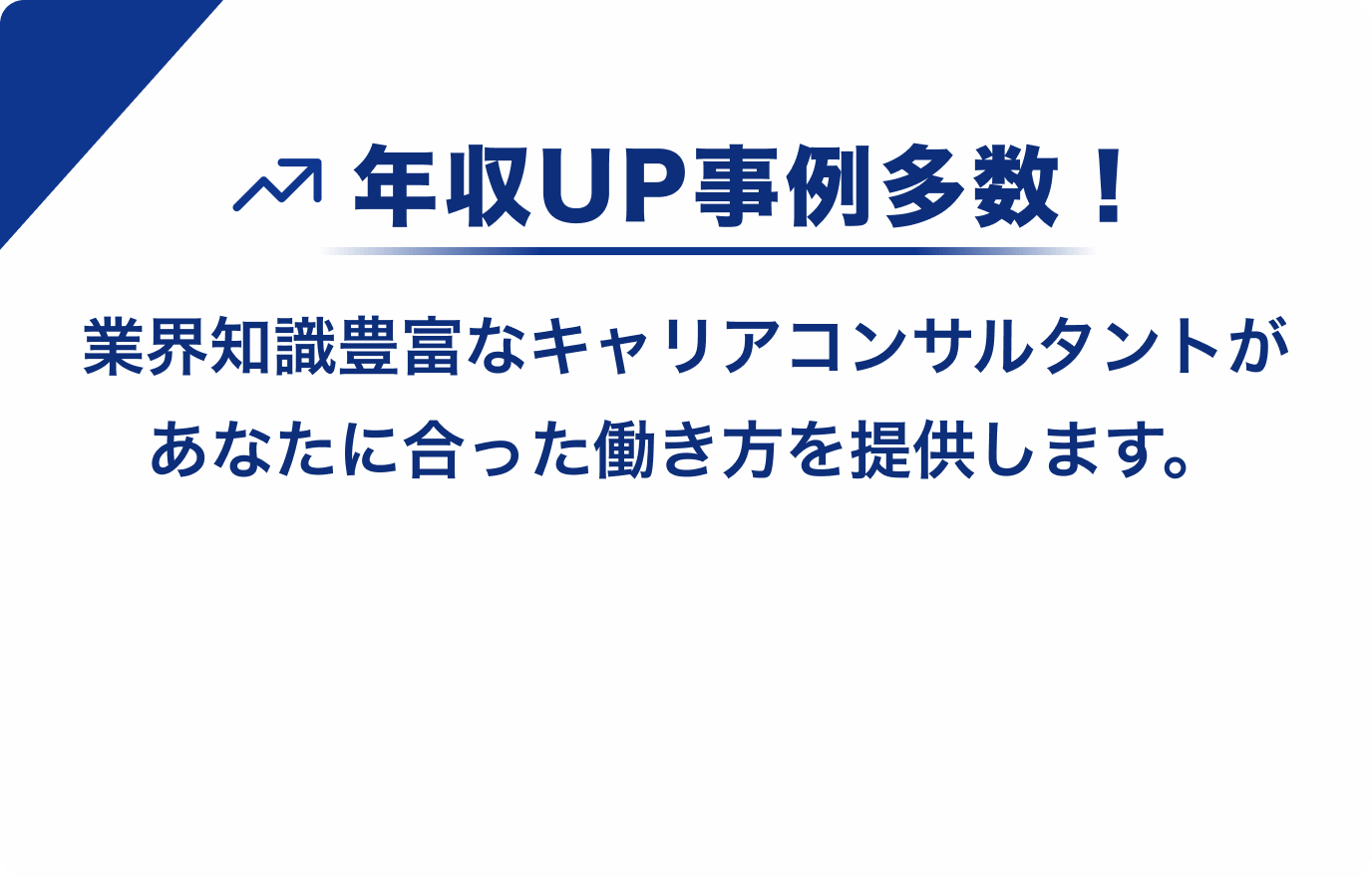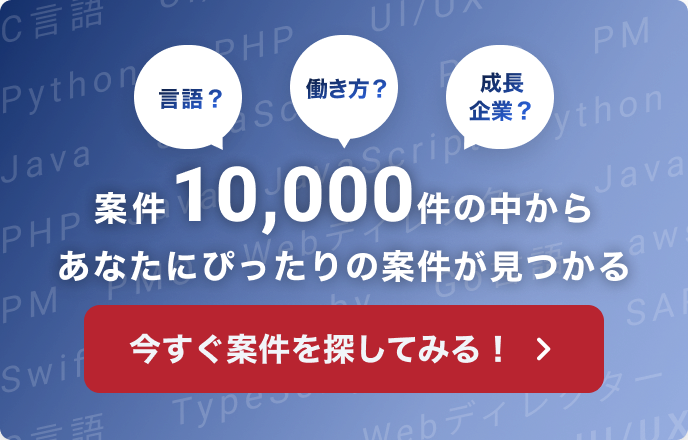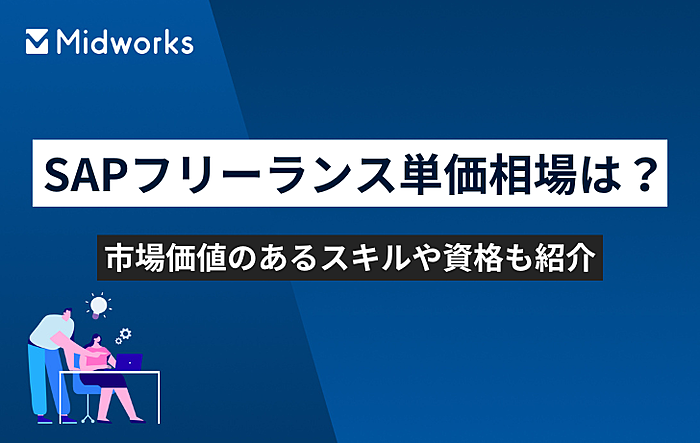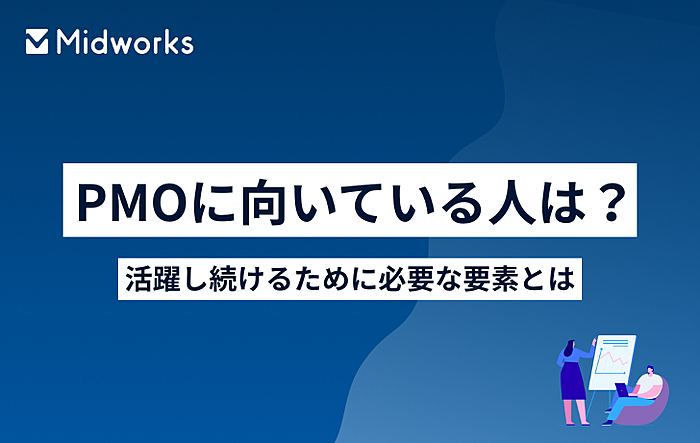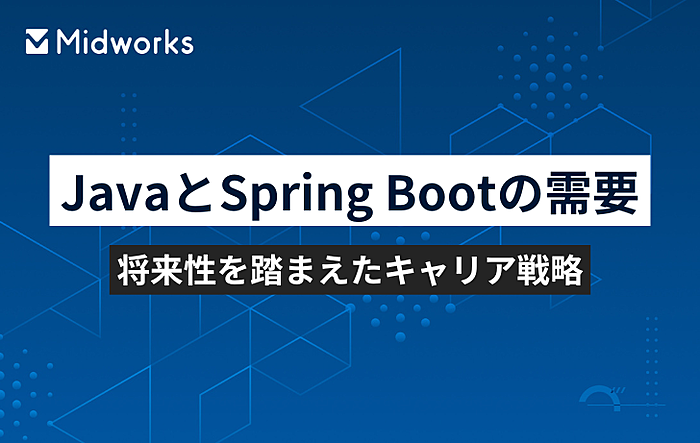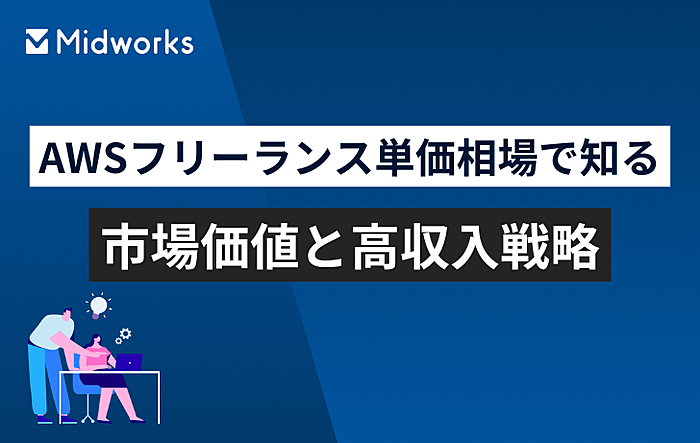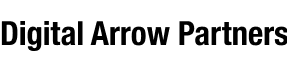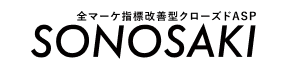個人事業主は、国民健康保険への加入、勤めていた会社で加入していた健康保険の任意継続、健康保険組合への加入、健康保険に加入している家族の扶養家族になるという選択肢があり、いずれか1つを選択する必要があります。
本記事では、個人事業主が加入できる健康保険組合や民間企業で働く人との違いについて解説しています。職種別の健康保険組合の例もご紹介しているので、個人事業主の方や個人事業主になりたい方は是非参考にしてみてください。
目次
目次を閉じる
健康保険とは
日本は国民皆保険制度のため、国民は必ず何かの健康保険に加入することになっています。自分が選んだ医療機関で、安く高度な医療を受けられることが国民皆保険制度の特徴です。
医療保険制度には適用事業で働く人が加入する健康保険、船員が加入する船員保険、公務員や私学教員が加入する共済保険、それ以外の一般住民が加入する国民健康保険があります。
出典:国民健康保険制度|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index_00002.html
個人事業主と民間企業で働く人が加入する健康保険の違い
会社を退職し個人事業主となった場合、今まで会社で入っていた健康保険との違いに驚くでしょう。そうなる前に、国民健康保険とはどういったものかを理解しておく必要があります。
ここでは、個人事業主が加入する「国民健康保険」と民間企業で加入する「健康保険」の違いについて説明していますので、参考にしてください。
個人事業主が加入する「国民健康保険」
国民健康保険は、他の健康保険に加入していない全ての人を対象にした医療保険制度です。保険者は市町村の国保と、業種ごとに組織で構成されている国民健康保険組合がありますが、ここでは一般的な個人事業主が加入する「国民健康保険」について説明します。
国民健康保険の保険料は住んでいる自治体で計算され、世帯単位の被保険者の収入により算出し、医療分・支援分・介護分の3つの要素を年齢によって組み合わせています。
扶養家族の概念がないため1人1人保険料がかかりますが、保険給付には療養の給付はもちろん高額な治療を受けた際の高額療養費、出産一時金や埋葬費は健康保険と同じように支給されます。
基本的に免除制度はありませんが、特別な事情により支払うことが困難な場合は、減免や徴収猶予を受けられることもありますので国民健康保険の窓口で相談してみてください。
民間企業で働く人が加入する「健康保険」
民間企業で働く人が加入する健康保険は、全国健康保険協会です。都道府県ごとに保険料率が違い、給料から保険料を天引きされ支払われます。また、大企業や、複数の会社が共同で設立した健康保険組合もあります。
保険料は被保険者の標準報酬月額を算定し税率をかけて計算される仕組みです。会社と被保険者が折半して払う点と、扶養家族は別途保険料がかからない点がメリットでしょう。
国民健康保険と違い傷病手当金や出産手当金があるため、病気やけが、出産で仕事ができない状態になった場合に手当金が支給されます。
個人事業主が加入できる健康保険の選択肢とは
個人事業主となった場合に加入できる健康保険には何があるでしょうか。
ここでは、4種類の方法を詳しく説明しています。自分にメリットのある健康保険、加入できる健康保険は何かをしっかり理解して見つけてください。
国民健康保険への加入
国民健康保険への加入は、退職した翌日より14日以内に市町村の国民健康保険の窓口で手続きを行います。他の健康保険に加入している世帯主であっても、被保険者の保険料を世帯単位で計算され世帯主へ通知されます。
保険料は前年度の所得に応じて計算されるため、所得が高かった年の翌年は高額になることを覚えておきましょう。
勤めていた会社で加入していた健康保険の任意継続
任意継続とは、退職前に務めていた会社で加入していた健康保険に引き続き加入できるものを指します。資格喪失日の前日まで2ヶ月以上被保険者期間があること、並びに資格喪失日から20日以内に手続きすることが加入条件です。
加入期間は任意継続を資格取得してから2年間となり、保険料を納付期限までに納付しなかった場合は資格喪失となるため、注意が必要です。
在職中の保険料は会社と折半でしたが、任意継続の場合の保険料は全額自己負担になります。扶養家族の保険料は在職中と同様で負担する必要はありません。
資格喪失日までに傷病手当金や出産手当金を受給している場合は、任意継続となった後も引き続き受け取れます。
健康保険組合へ加入
国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事し、所定の地区内に居住する人が組合員となれます。ただし、組合によって加入条件があり希望者全員加入できるわけではないところもあるので確認が必要です。
国民健康保険と同じように、扶養家族の概念がないのでそれぞれに保険料がかかります。健康保険組合ごとに保険料の計算方法が異なり、組合員の種類や家族、年齢などによって決まるところや、一律で決まっているところもあります。
国民健康保険とは違い、収入が増えても条件が変わらなければ保険料は一定となる点がメリットです。収入が多い人にとっては国民健康保険よりも保険料が安くすむ可能性があります。
健康保険に加入している家族の扶養家族になる
扶養家族に認定されると、保険料を個別に支払わなくても健康保険に加入できるというメリットがあります。健康保険組合の場合は、独自の条件がありますので確認が必要です。
認定基準には3親等内の親族であり、被保険者と同一世帯に属している場合は、認定対象者の年収が130万未満である必要があります。同一世帯ではない場合は、年収条件の他に被保険者からの仕送りよりも年収が少ないことも条件となります。
自営業の収入は売上金額から売上原価と直接的必要経費を差し引いて計算しますが、税法上における経費と一部違う部分もあるので問い合わせてみましょう。
職種別の健康保険組合の例
職種別の健康保険組合に加入する時は加入条件がそれぞれ違うだけでなく、保険料や給付内容なども独自で決めているため注意点が必要です。
ここでは、例として4つの健康保険組合を紹介します。他にもたくさんの健康保険組合がありますので、自身の業種関連に合う健康保険組合がないか調べてみましょう。
東京美容国民健康保険組合
東京都内の事業所で美容の仕事に従事し、定められた地域に居住している人と同一世帯家族が加入できます。
保険料は月額、事業主19,000円、従業員13,500円、家族8,500円、家族(未児就学)5,000円、40歳から64歳まで介護納付金分3,000円が賦課されます。
保険給付は療養の給付、高額療養費、出産育児一時金、出産手当金、埋葬費、傷病手当金があり社会保険とほとんど同じ内容です。保険事業には協定施設で受けた人間ドックの助成があり、特定健診は無料で受けられます。また、保養施設の利用助成金もあります。
出典:保険料について|東京美容国民健康保険組合
参照:https://kokuho-tokyobiyo.or.jp/hokenryou/
文芸美術国民健康保険組合
日本に居住し、組合加盟の各団体の会員である人とその家族が加入できる保険組合です。加入するにはどのくらい文芸、美術及び著作活動の仕事に従事しているか、作品例を提出するなどの審査があります。
保険料は月額、組合員21,100円、家族11,600円、40歳から64歳まで介護保険分5,200円が賦課されます。組合員の収入に関係なく一律です。
保険給付には医療費の負担、出産育児一時金、埋葬費、疾病予防があり、疾病予防には健康診断や人間ドックの補助があります。
出典:保険料について|文芸美術国民健康保険組合
参照:http://www.bunbi.com/
関東信越税理士国民健康保険組合
関東信越税理士会に登録のある税理士および事務所に勤務している税理士や職員、組合員と同居の家族が加入できます。
保険料は月額、税理士26,000円、勤務税理士26,000円、職員で15,000円、家族8,000円、6歳から74歳まで後期高齢者支援金分5,200円、40歳から64歳まで介護納付金分6,200円が賦課されます。家族の保険料は1世帯につき4人までです。
給付内容は医療給付、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費、傷病手当金があり、出産育児一時金には加算金がプラスされるため、他の健康保険より多く受け取れます。
出典:国民健康保険料|関東信越税理士国民健康保険組合
参照:http://www.ka-z-kokuho.or.jp/insurance.html
京都府建設業職別連合国民健康保険組合
建設業の職種に従事している人とその家族が対象であり、規約に定める母体組合に所属し、定められた地域に住民票がある人が加入できる保険組合です。
保険料は月額、25歳未満13,000円、25歳以上29歳未満17,000円、30歳以上39歳未満19,000円、40歳以上65歳未満24,000円、70歳以上75歳未満18,500円、家族6,500円(40歳以上65歳未満介護保険料分2,000円)賦課されます。
保険給付は療養の給付、高額療養費、出産一時金、埋葬費などがあり、他に保険事業として年度内に1回の健康診断や人間ドックの費用助成が利用できます。節目年には無料になるメリットもあります。
出典:保険料|京都府建設業識別連合国民健康保険組合
参照:http://www.syokubetu-kokuho.or.jp/kokuho/hokenryo.html
個人事業主の健康保険組合への理解を深めよう
ITやシステムエンジニアの個人事業主が現在加入できる健康保険組合は、文芸美術国民健康保険組合のみとなります。組合加盟の各団体の会員になる必要がありますが、自身が条件を満たしている場合のメリットは大きいと言えます。
また、業界別に健康保険組合が分かれているため、同業の個人事業主に相談したり情報収集したりすることによって、お得な健康保険組合が見つかる可能性もあるでしょう。この記事を参考に個人事業主の健康保険組合への理解を深め、自身に合った保険組合への加入をしましょう。
フリーランスとして安心して稼働したい方はMidworksがおすすめです。正社員並みの福利厚生サービスや給与保障サービスを保有しているため、案件に集中できる環境を整えやすいといえます。また、専門のコンサルタントによるキャリア相談や案件紹介を行っているため、不安を抱えているエンジニアの方はぜひご登録ください。
関連記事
フリーランスのキャリア


SAPフリーランス単価相場は?市場価値のあるスキルや資格も紹介

AWSフリーランス単価相場で知る|市場価値と高収入戦略
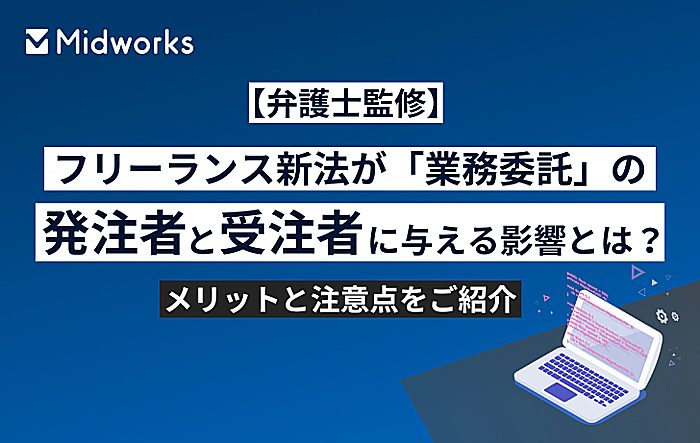
【弁護士監修】フリーランス新法が「業務委託」の発注者と受注者に与える影響とは?メリットと注意点をご紹介
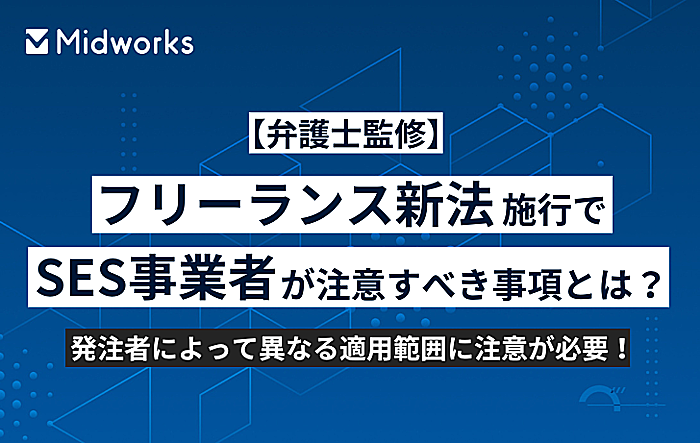
【弁護士監修】フリーランス新法施行でSES事業者が注意すべき事項とは?発注者によって異なる適用範囲に注意が必要!
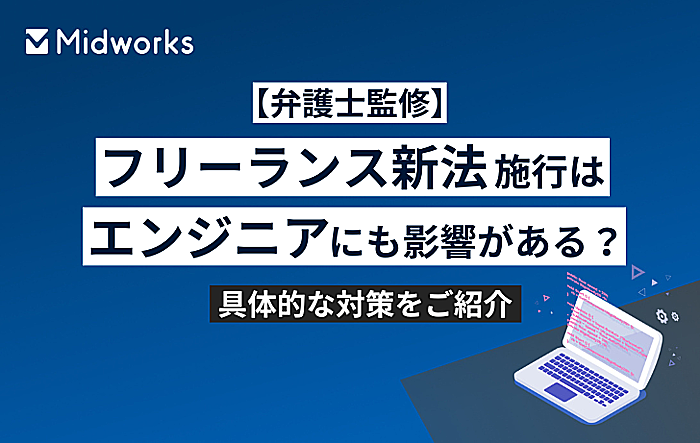
【弁護士監修】フリーランス新法施行はエンジニアにも影響がある?具体的な対策をご紹介
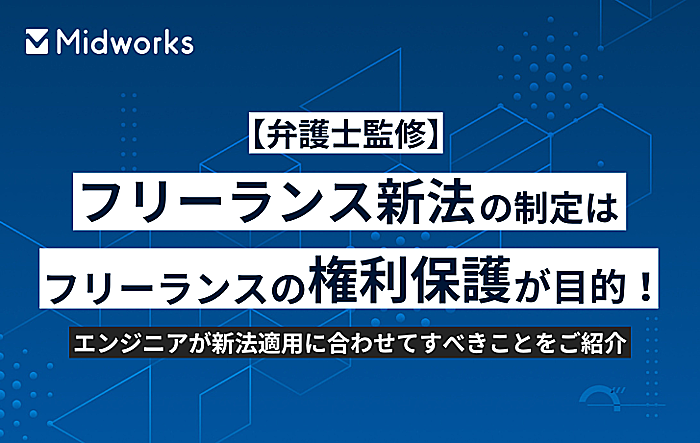
【弁護士監修】フリーランス新法の制定はフリーランスの権利保護が目的!エンジニアが新法適用に合わせてすべきことをご紹介
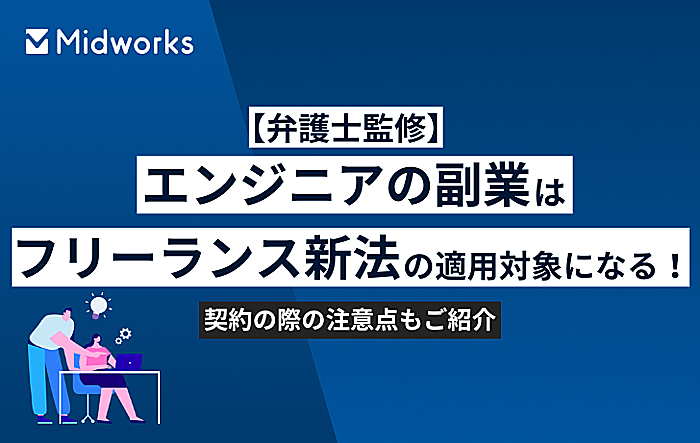
【弁護士監修】エンジニアの副業はフリーランス新法の適用対象になる!契約の際の注意点もご紹介
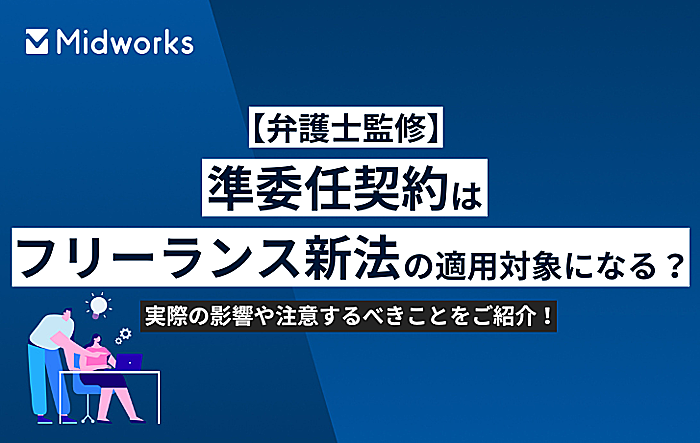
【弁護士監修】準委任契約はフリーランス新法の適用対象になる?実際の影響や注意するべきことをご紹介!
インタビュー


紹介からたった1週間で現場にフリーランスが参画!スピード感で人手不足を解消-株式会社アイスリーデザイン様
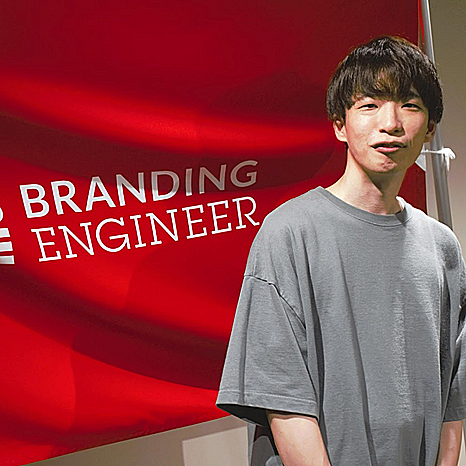
受託開発企業から、フリーランスで自社開発企業へ!

事業の成長スピードに現場が追い付かないという悩みをMidworks活用で解決-株式会社Algoage様
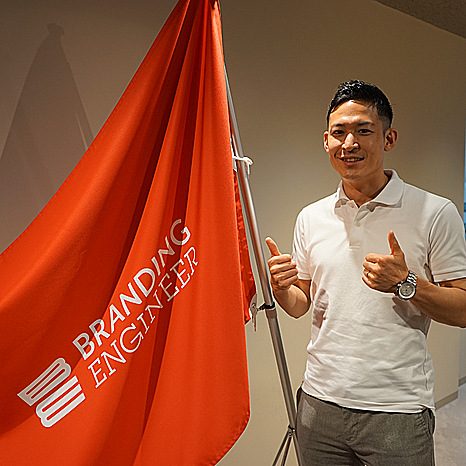
30代でも遅くない!未経験からエンジニアへのジョブチェンジで天職と巡り合った、英語が喋れる元消防士のフリーランスへの挑戦

フリーランスに転向し収入も生活も向上 アップデートを続けるエンジニアの情報収集方法を公開
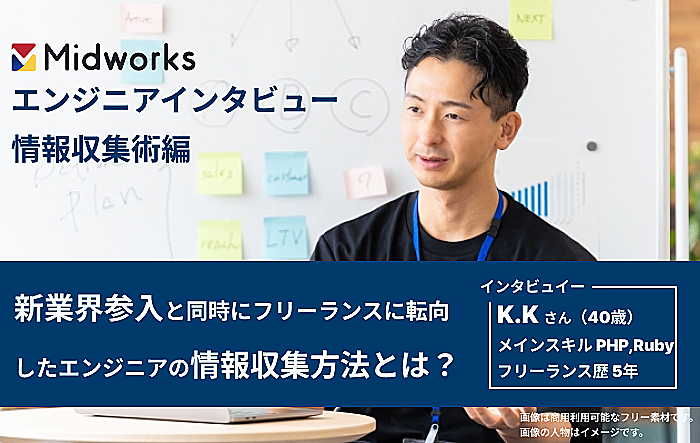
新業界参入と同時にフリーランスに転向したエンジニアの情報収集方法とは?
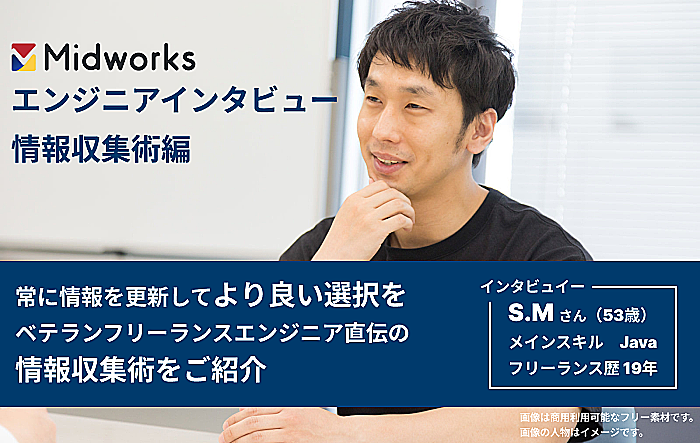
常に情報を更新してより良い選択を ベテランフリーランスエンジニア直伝の情報収集術をご紹介
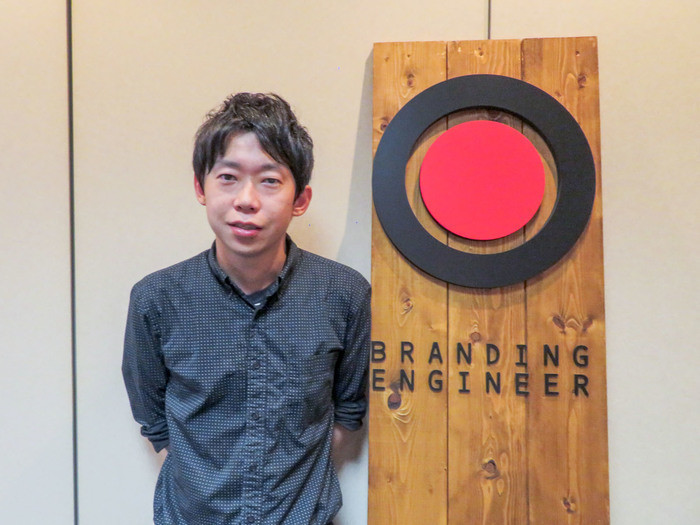
理想的なエンジニア像を描き、自由な働き方を求めてフリーランスへ。
フリーランスの基礎知識


何年の経験でフリーランスエンジニアは案件を獲得できる?未経験の場合についても解説

20代前半でもフリーランスエンジニアになれる?平均年収やメリット・デメリット

副業フリーランスはおすすめ?未経験からの始め方やメリット・デメリットを解説

【初心者におすすめ】ITパスポート試験で合格点は?合格に近づく勉強法

IT業界の現状は?市場規模や今後の動向についても解説!

フリーランスのソフトウェア開発に求められる「12のこと」をご紹介!必要なスキルも解説

【職種別】フリーランスエンジニアの年収一覧!年代やプログラマーの言語別にも紹介
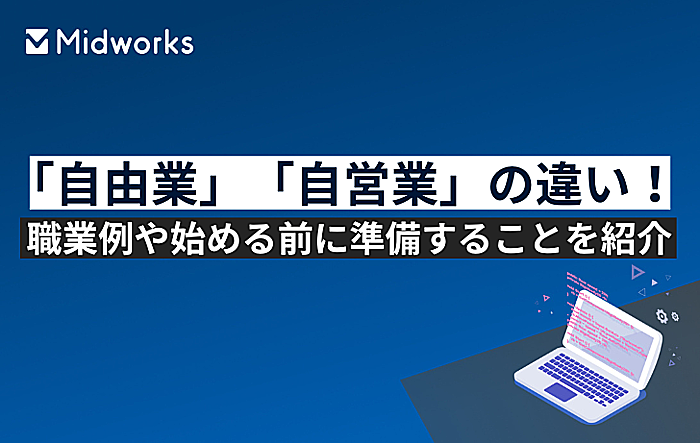
実は知られていない「自由業」「自営業」の違い!職業例や始める前に準備することを紹介
プログラミング言語

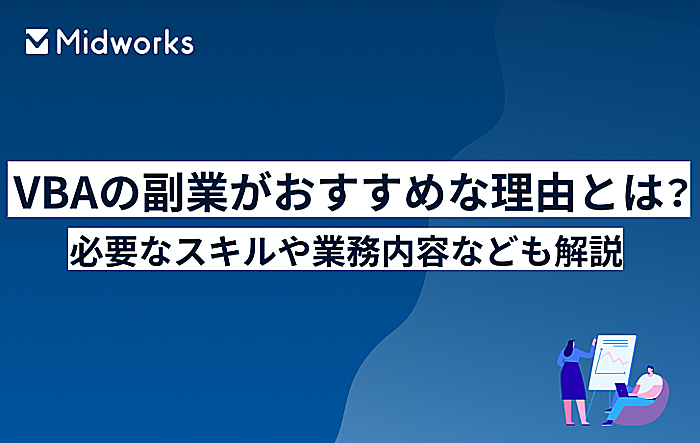
VBAの副業がおすすめな理由とは?必要なスキルと業務内容・案件の探し方も解説
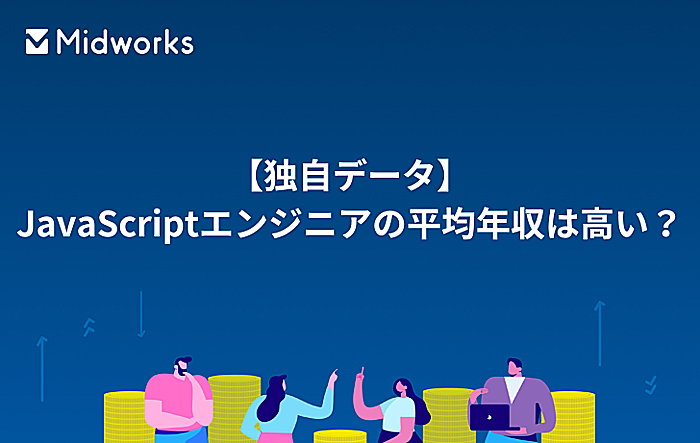
【独自データ】JavaScriptエンジニアの平均年収は高い?年収を上げる方法もご紹介
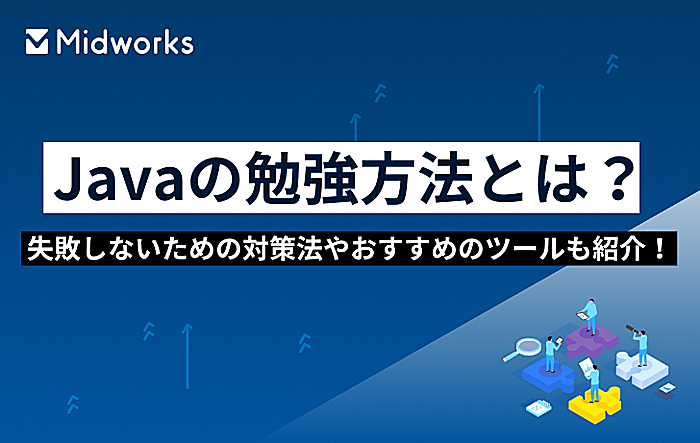
Javaの勉強方法とは?失敗しないための対策法やおすすめのツールも紹介!

【独自データ】PHPエンジニアの年収は高い?年収を上げるための方法もご紹介!
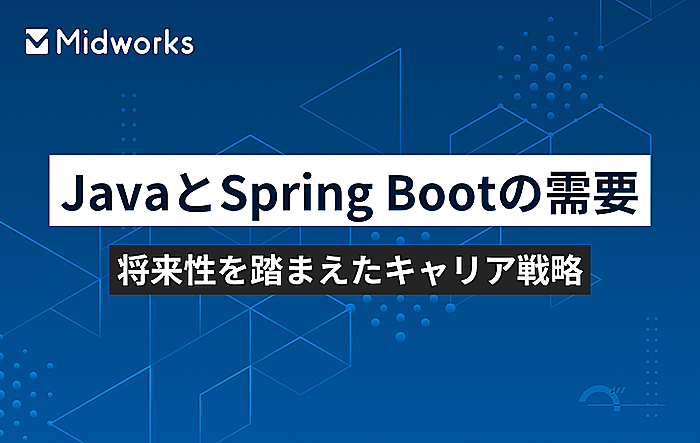
Title JavaとSpring Bootの需要|将来性を踏まえたキャリア戦略

Java Gold資格の難易度とキャリア価値を徹底解説
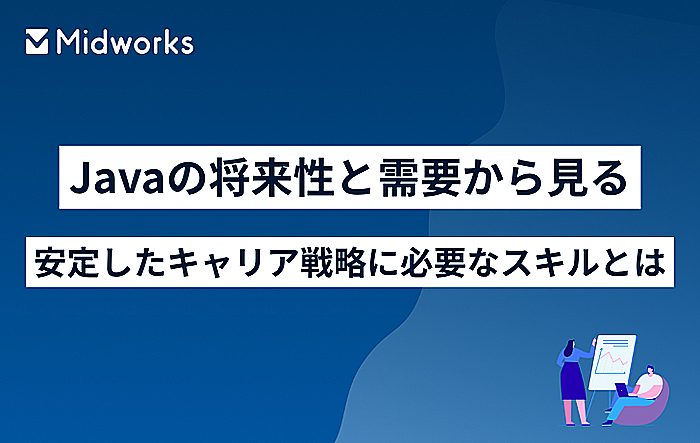
Javaの将来性と需要から見る|安定したキャリア戦略に必要なスキルとは
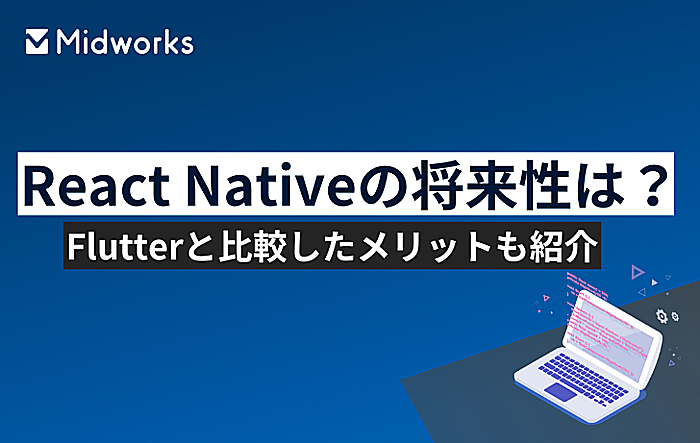
React Nativeの将来性は?Flutterと比較したメリットも紹介
企業向け情報

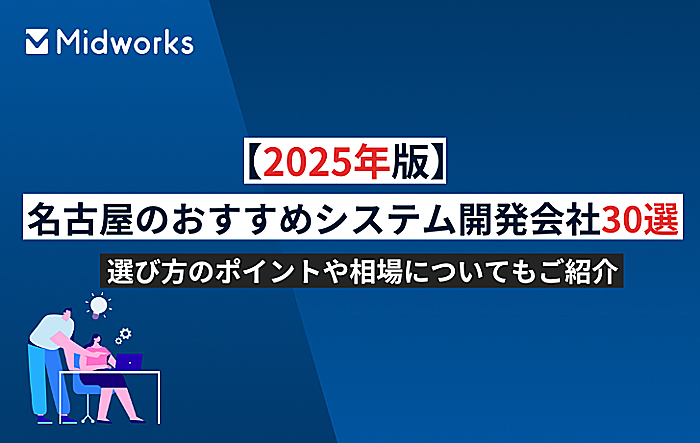
【2025年版】名古屋のおすすめシステム開発会社30選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
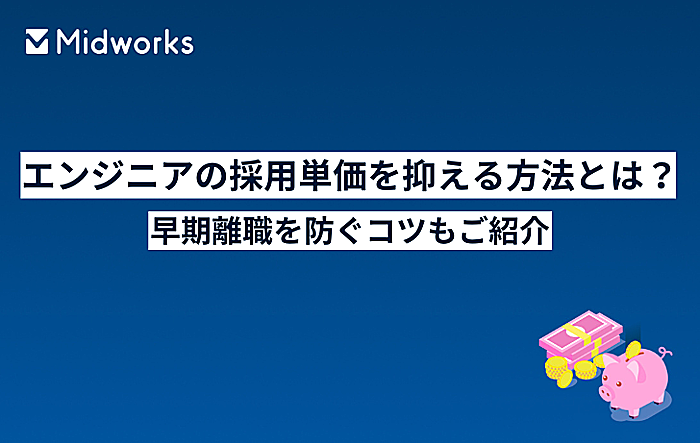
エンジニアの採用単価を抑える方法とは?早期離職を防ぐコツもご紹介
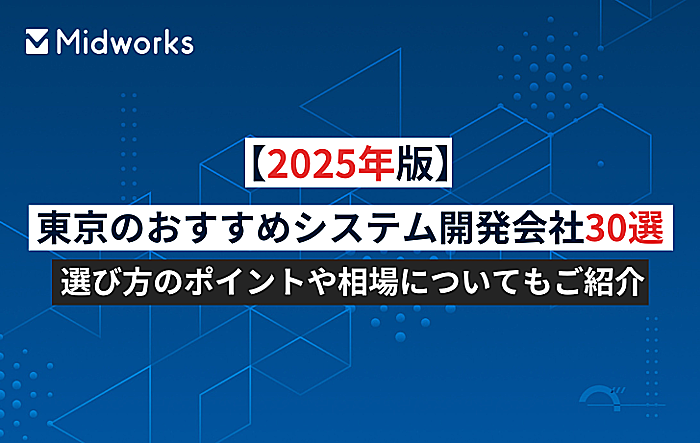
【2025年版】東京のおすすめシステム開発会社30選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
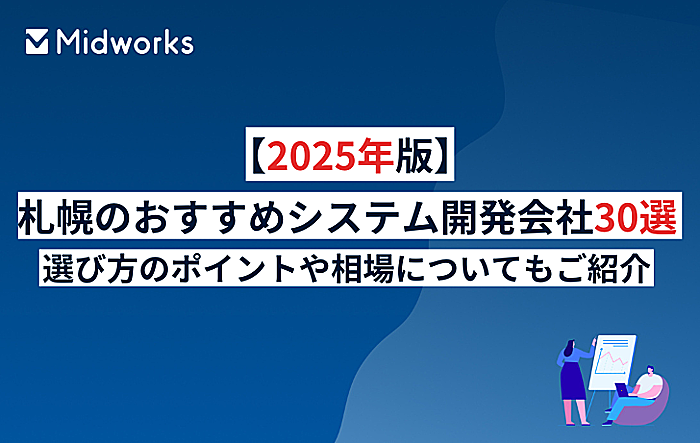
【2025年版】札幌のおすすめシステム開発会社30選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
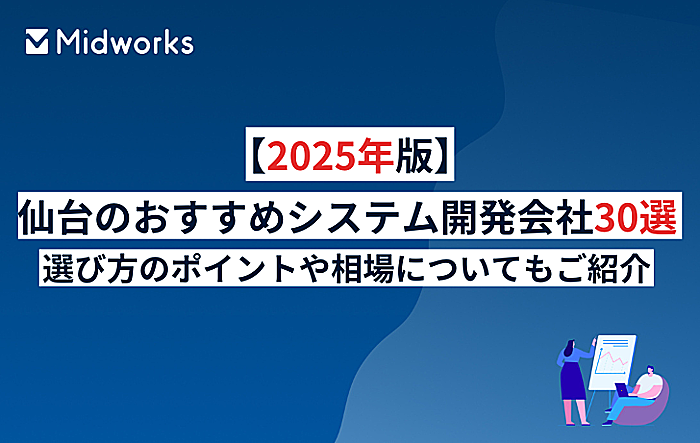
【2025年版】仙台のおすすめシステム開発会社30選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
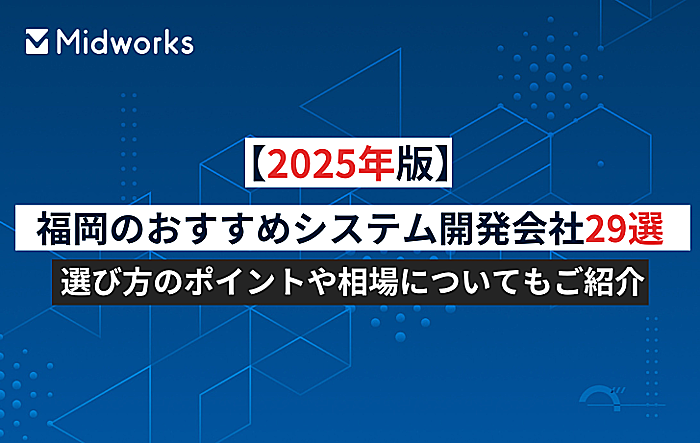
【2025年版】福岡のおすすめシステム開発会社29選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
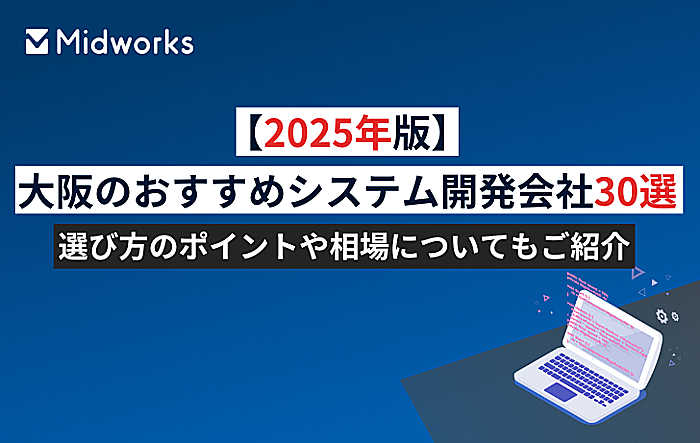
【2025年版】大阪のおすすめシステム開発会社30選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
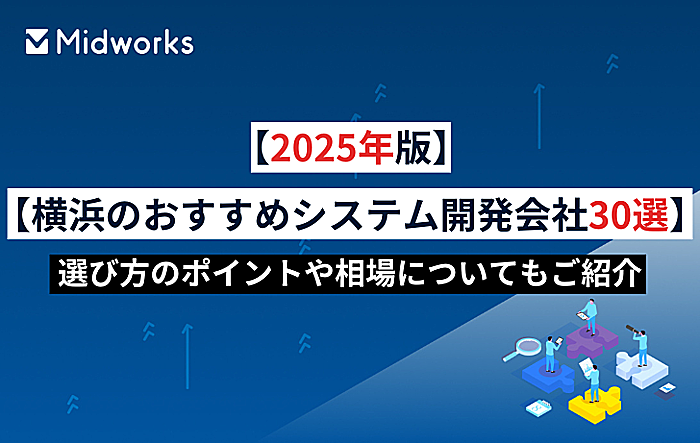
【2025年版】横浜のおすすめシステム開発会社30選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
業界特集


医療業界のフリーランスエンジニア向け案件特集|DX化が進む成長市場で求められるスキルと働き方のポイント

自動車業界フリーランスエンジニア案件特集|CASE時代の開発をリード!求められる技術とプロジェクト事例

EC業界のフリーランスエンジニア向け案件特集|急成長業界で必要とされるスキルや働き方のポイントもご紹介

セキュリティ業界のフリーランスエンジニア向け案件特集|案件参画で身につくスキルや参画の際に役立つ資格もご紹介

金融業界(Fintech領域)のフリーランスエンジニア向け案件特集|業界未経験でも活躍する方法もご紹介

生成AI分野フリーランスエンジニア案件特集|最先端技術を駆使!注目スキルと開発プロジェクト事例

小売業界フリーランスエンジニア案件|年収アップとキャリアアップを実現!最新トレンドと案件獲得のコツ