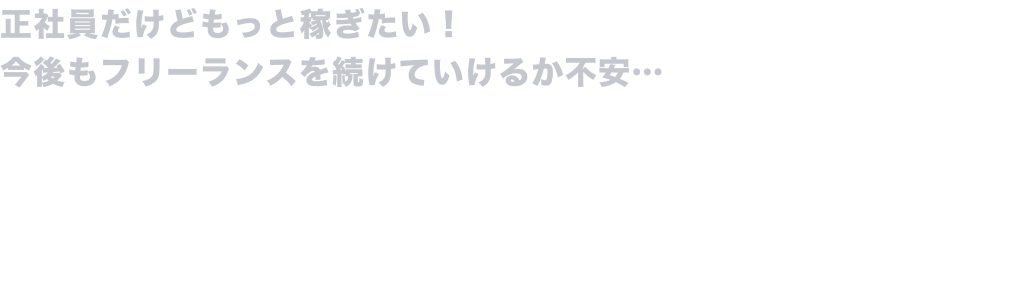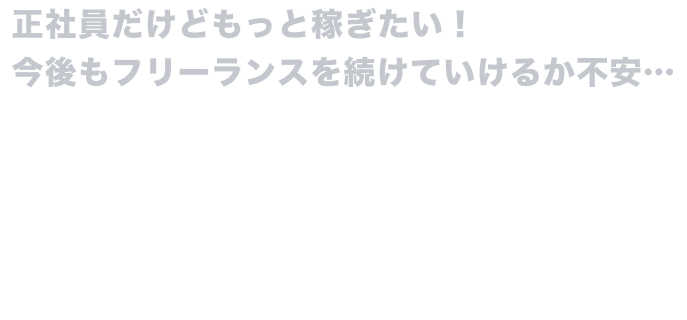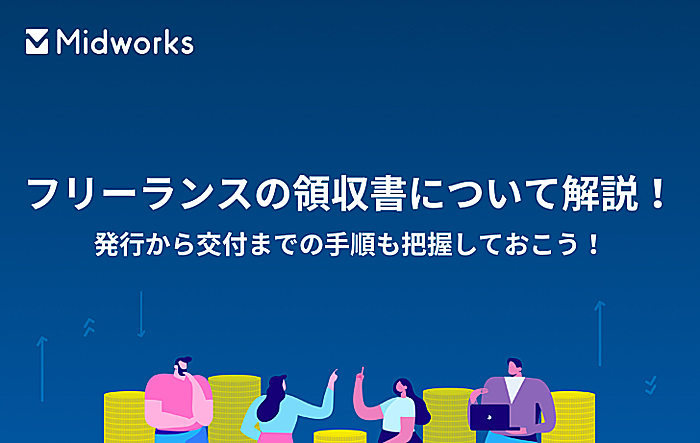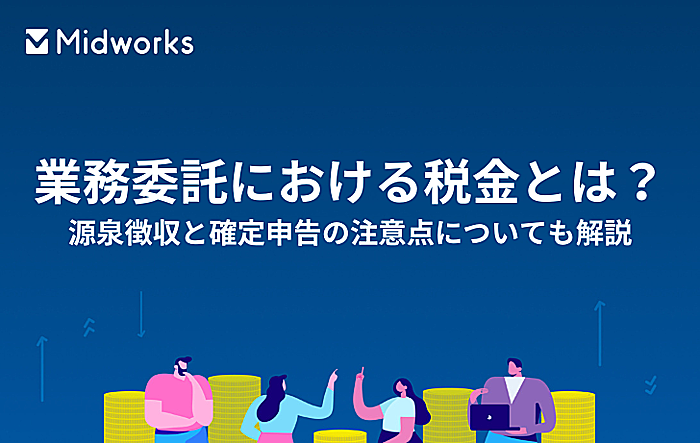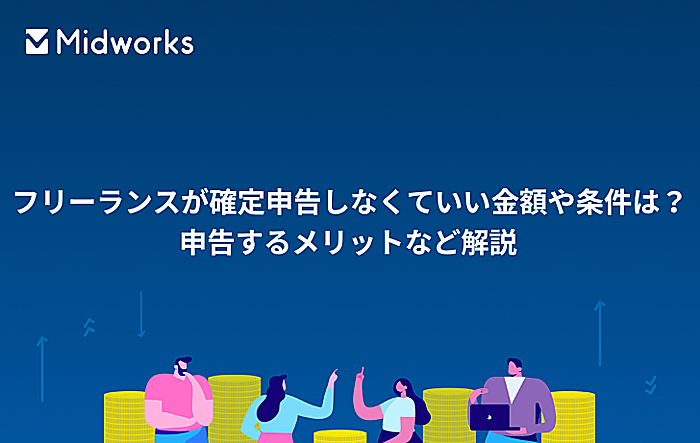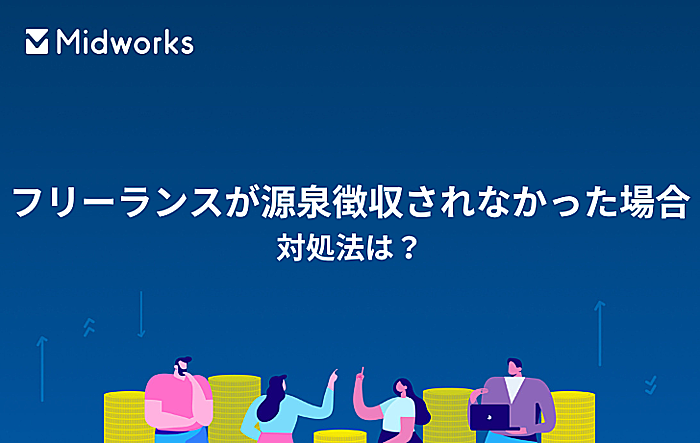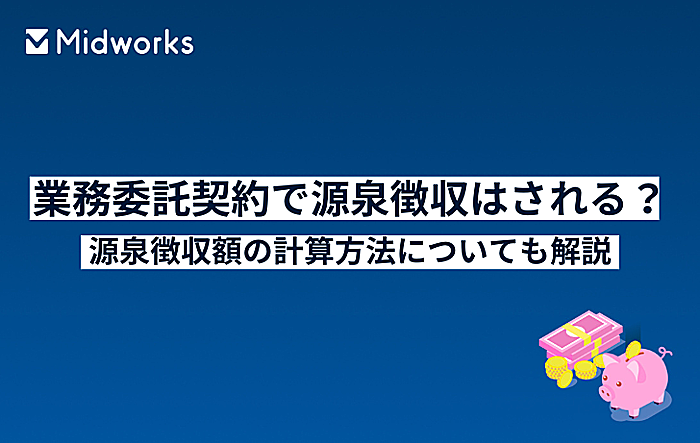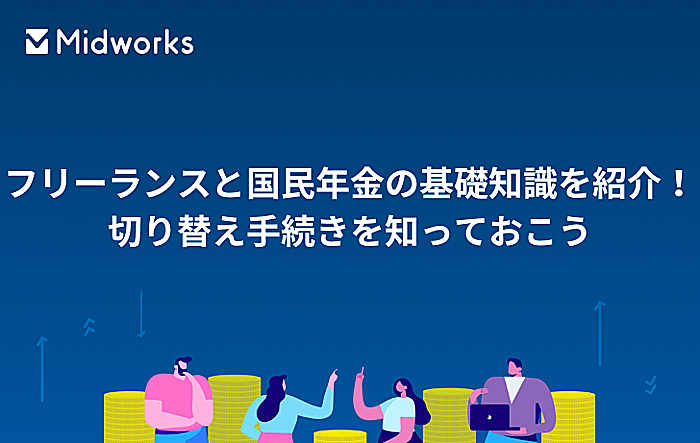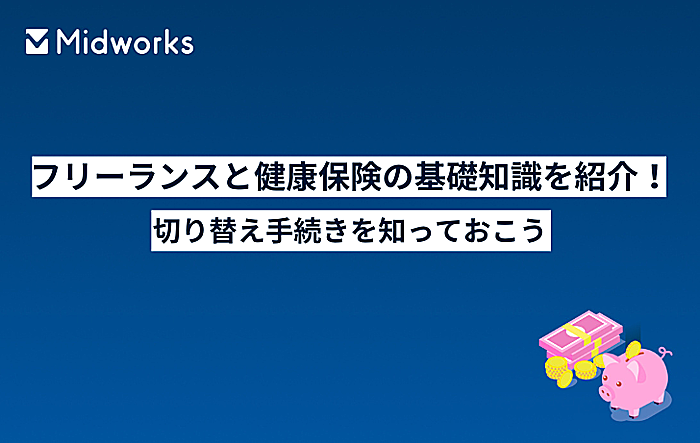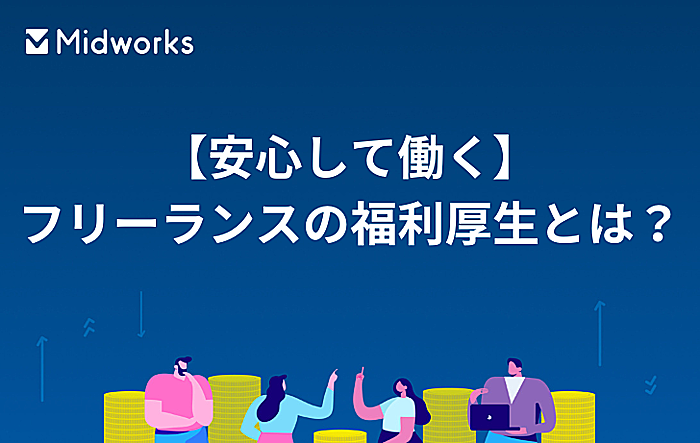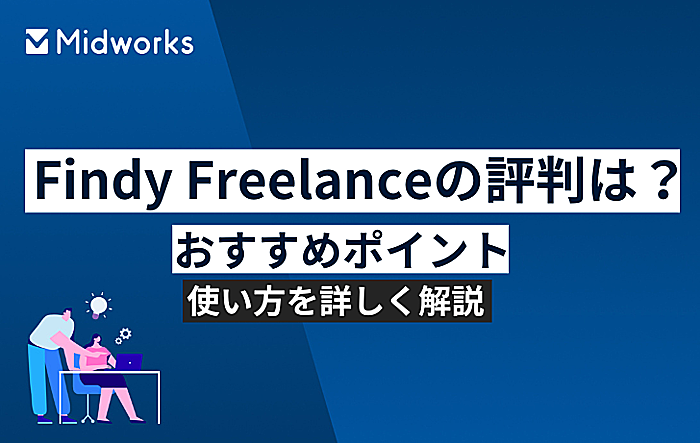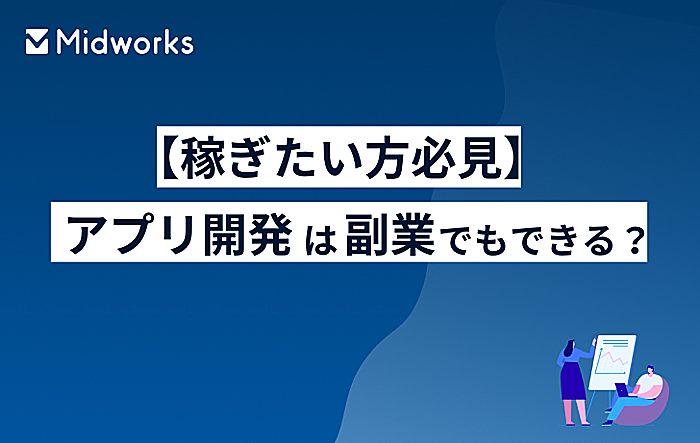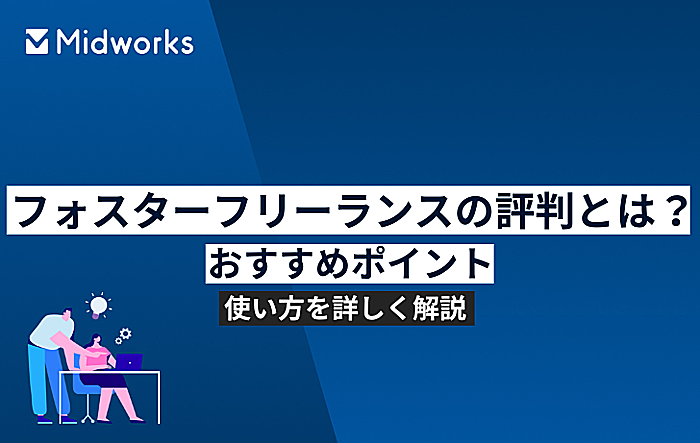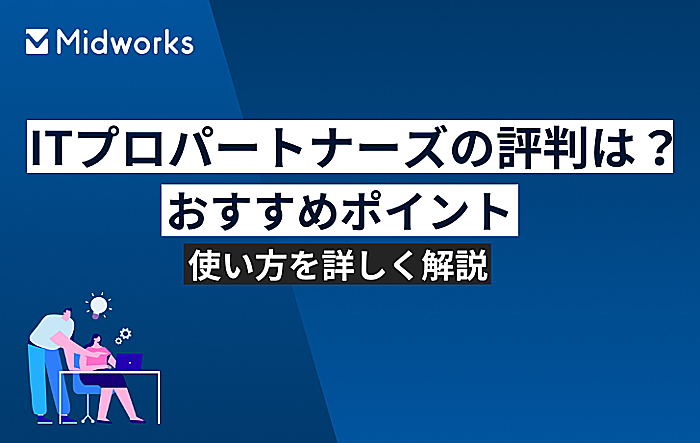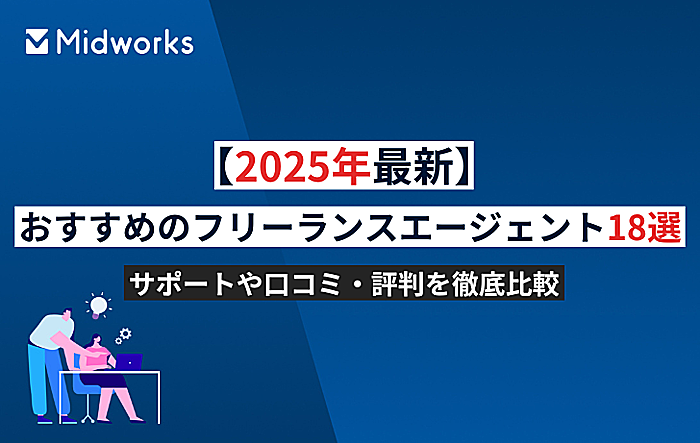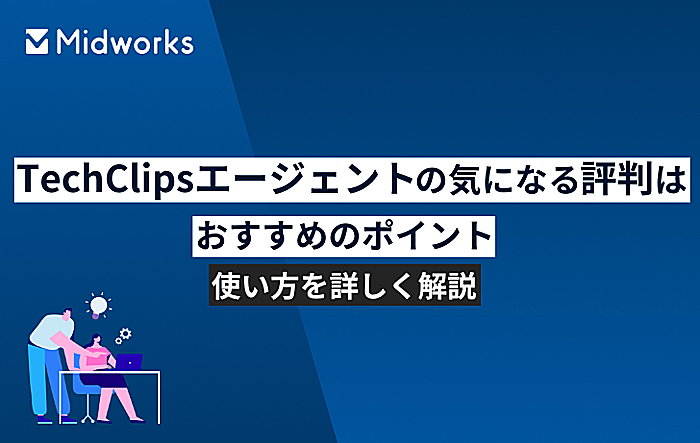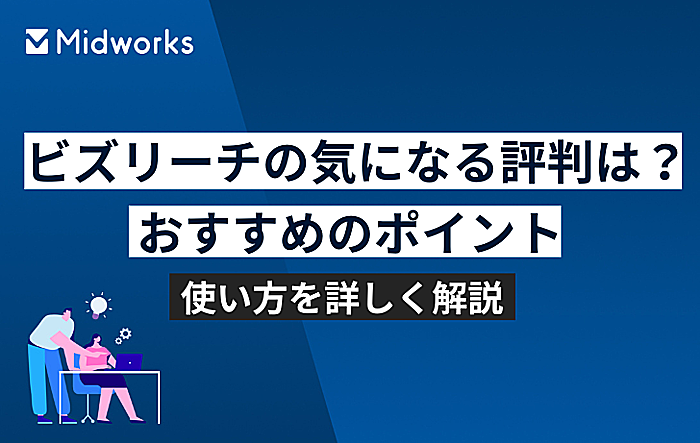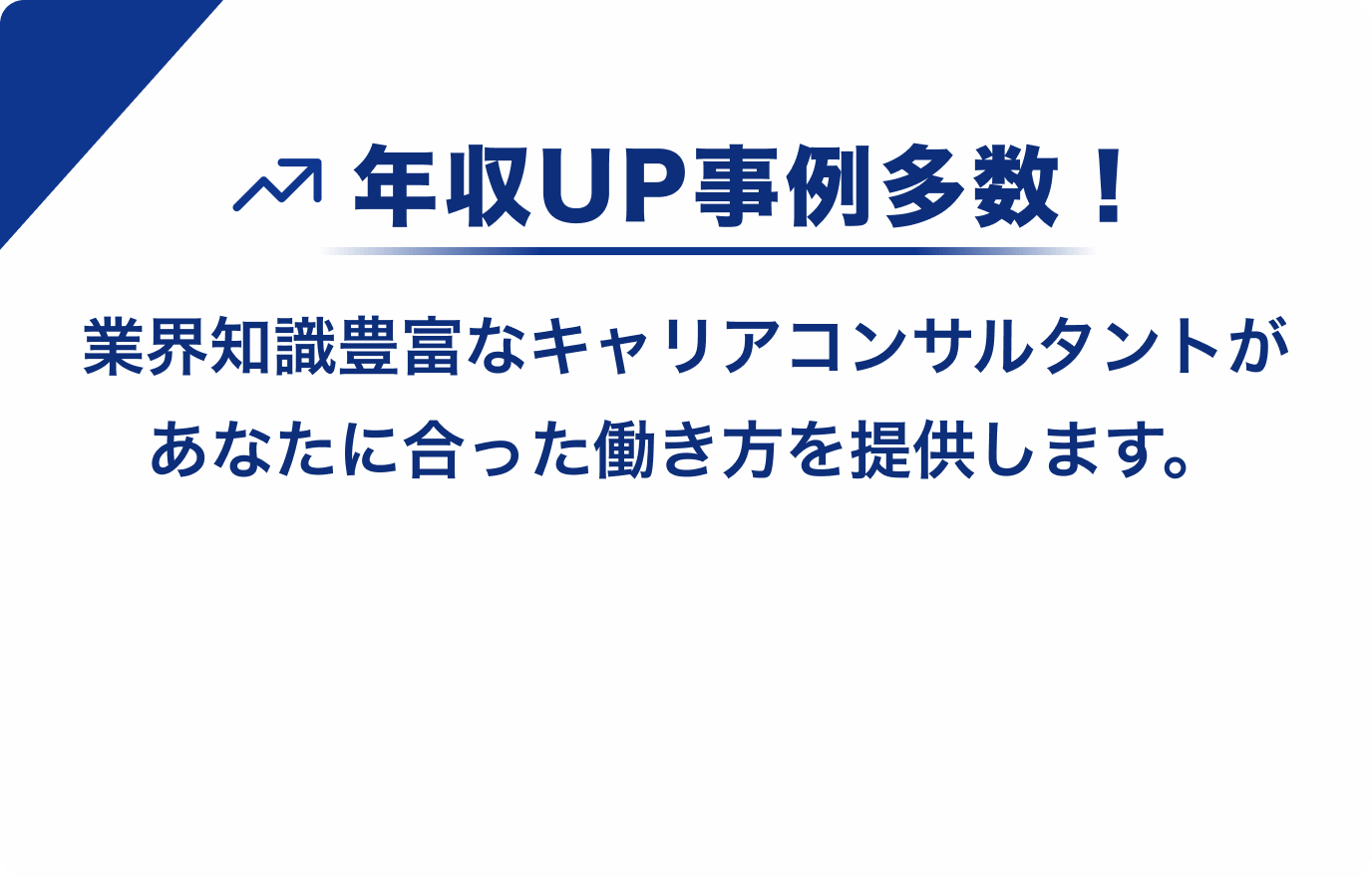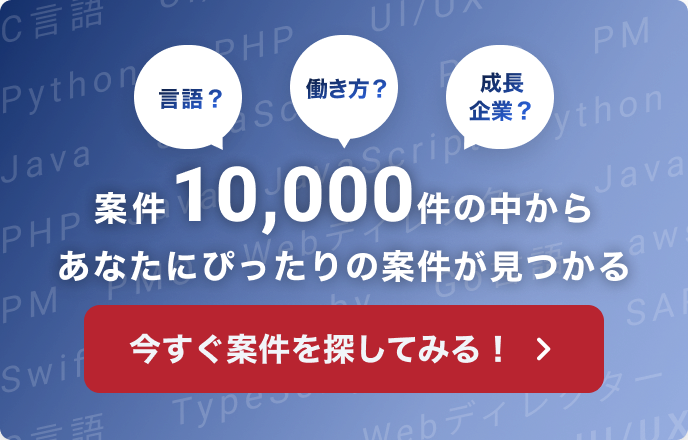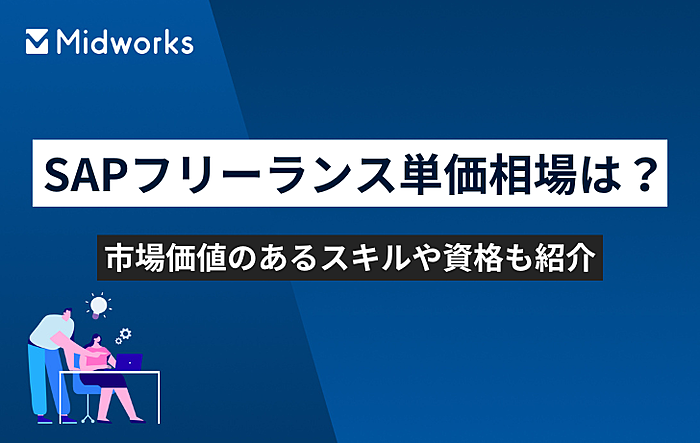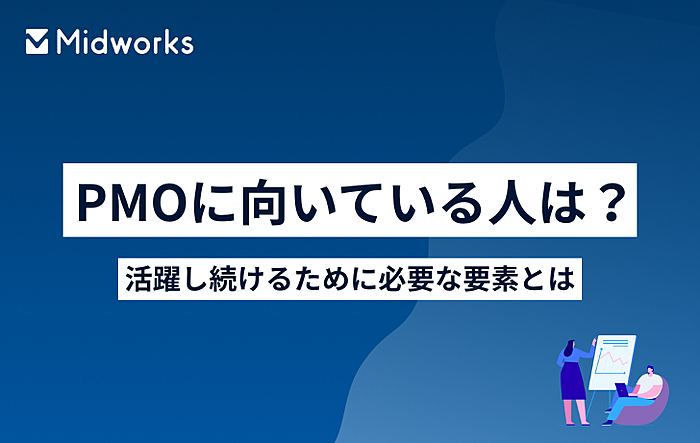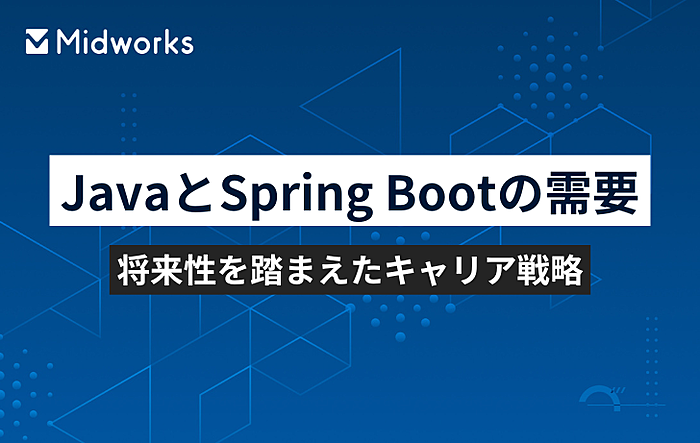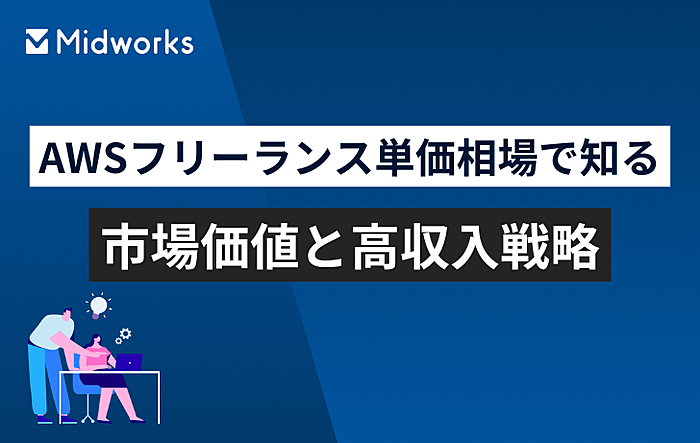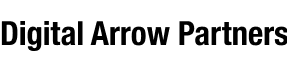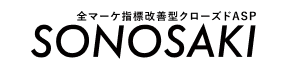「フリーランスになると年金ってどうなるの?」
「フリーランスとして働きたいけれど、将来の年金って会社員と同じなの?」
フリーランスとして働きたいけれど、将来の年金に不安を抱えている人も多いのではないでしょうか。
この記事では年金の基礎知識に加え、会社員とフリーランスのそれぞれの年金について比較しています。また、フリーランスだからできる年金の増やし方や税金に対するお得な方法も紹介しています。
この記事を読むことによって年金の基礎知識を理解し、会社員とフリーランスでの年金の違いが把握できます。また、退職した後も後悔のないようにできるでしょう。
これからフリーランスへ転身しようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
目次を閉じる
年金とは

年金とは全ての人が現役時代に保険料を負担し、その負担に応じて将来受給できる制度を言います。
年金には、公的年金として国民年金や厚生年金だけでなく、個人で加入できる個人年金保険などもあります。それぞれ受給条件に該当した場合に、一定期間や終身に渡り支給されるお金です。
出典:公的年金制度はどのような仕組みなの?|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/01/01-02.html
日本の公的年金のシステム
公的年金のシステムは現役世代が支払った保険料を、高齢者などの年金給付等へ役立たせており、世代と世代の支え合いで成り立っています。
昔は親と同居し子供が親を養う形だったが、今は親と別居して都市に働きに出るスタイルが多くなり個人や家族の範囲で対応したくても難しくなってきています。そのため、公的年金によって、親を養う資金が軽減されていると言えます。
国民全員の加入義務である国民年金
日本国内に住む20歳以上の全ての人が公的年金に加入することとなっており、このことを国民皆年金と言います。
自営業者など国民年金のみに加入している人を第一号被保険者と言い、会社員や公務員は厚生年金や共済年金にも加入している人は国民年金の第二号被保険者です。
専業主婦などの第二号被保険者の配偶者に扶養されている人は第三号被保険者となり、国民年金保険料を個別に支払うことなく国民年金に加入していることになります。
国民年金の加入期間に応じて老齢基礎年金の金額が計算され、資格期間が10年以上あれば65歳から受給できます。
出典:国民年金はどのような人が加入するのですか。|日本年金機構
参照:https://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kanyu/20140116.html
主に会社員が加入する厚生年金
適用事業所に常時使用されている全ての人が厚生年金の対象となります。
厚生年金保険料は会社の給料計算時に計算され、事業主と被保険者が半分ずつ負担することとなっています。被保険者の負担分は給料から天引きされるので、別途保険料を納付する必要はありません。
公的年金は2階建て構造になっており、国民全員加入義務のある国民年金は1階、会社員や公務員が加入する厚生年金や共済年金は2階部分となり国民年金の上乗せとなります。
フリーランスと会社員が受け取る年金の金額とは
フリーランスが受ける年金は国民年金となり、1人当たりの月額は約64,000円になります。この金額は老齢基礎年金を満額支払った場合の1人分です。夫婦2人分となると約128,000円になります。
会社員が受ける年金は厚生年金となり、夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な月額は約220,000円です。
会社員が受ける年金の方が多くなるのは、先ほど説明した2階建て構造にあるのです。会社員は厚生年金保険料を払って2階部分を築くことができるので年金額が増えるのです。
出典:令和4年度の年金額改定についてお知らせします|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000725140.pdf
フリーランスの扶養家族の年金とは
会社員の配偶者で要件を満たしている人は第3号被保険者となり国民年金保険料を支払う必要はありません。しかし、フリーランスの配偶者は全て第1号被保険者となるため、国民年金保険料の納付が必要になります。
会社員からフリーランスへ転身を考えている人は、夫婦2人分の国民年金保険料が必要となることを覚えておきましょう。
フリーランスは年金を控除対象にすることができる
会社員は厚生年金保険料を年末調整で社会保険料控除として控除できますが、フリーランスの場合も国民年金保険料は確定申告で控除できます。
1年間に支払った国民年金保険料の合計を健康保険料や介護保険料と一緒に社会保険料控除として申告しましょう。また、家族分の国民年金保険料を支払っている場合も合算できます。
ちなみに、確定申告の際に青色申告で申告することによって最大65万円の特別控除を受けられます。
フリーランスになったら国民年金へ加入手続き

20歳以上60歳未満の人が会社員を辞めてフリーランスになった場合、社会保険から脱退することになるので国民年金への切り替えが必要となります。また、扶養家族がいる人は家族の手続きも必要です。
国民年金の手続きは、市役所または町役場でできます。基礎年金番号を明らかにできる書類(基礎年金番号通知書や年金手帳)と退職した日が分かる物(離職証明書や健康保険喪失証明書等)を持参し、退職日から14日以内に手続きをしなければなりません。
もしも、所得が下がり国民年金保険料の納付が困難になった場合は、国民年金保険料の免除(全額、3/4、半額、1/4)や納付猶予制度を利用できます。支払えないからといって、放置はしないでください。
免除は将来の年金額に一部反映されますが、猶予は年金額への反映はありません。資金的余裕ができた時に免除や猶予分も納付すれば、反映されるようになります。
また、国民年金保険料は2年分前納制度を活用することによって、2年間で15,000円程度が割引になるお得な支払い方法もあるため、活用しても良いでしょう。
老後の生活費の目安

総務省の家計調査報告によると高齢者夫婦世帯での支出の月額は約27万円と報告されています。
夫婦2人分の老齢基礎年金が約128,000円なので約14万円不足(1人分約7万円)となるため、年間84万円(7万×12か月)20年間1,680万円、夫婦2人分となると3,000万円は必要になる計算です。
老齢厚生年金を受給できる人は夫婦2人分で約220,000円となり、約5万円不足(1人分約2.5万円)になりますが、この金額は60歳で定年となった場合を想定しています。会社員の場合は、退職金制度や定年後の働き方によってはこの不足額を補填できる可能性もあるでしょう。
フリーランスの場合は会社員と違い定年退職という概念がないので、健康であれば70歳や80歳でも現役で働ける可能性もありますが、いつまでも健康で働ける保障はないため、国民年金に上乗せできる制度もきちんと理解しておく必要があるでしょう。
出典:家計調査年報(家計収支編)2020年(令和2年)|総務省統計局
参照:https://www.stat.go.jp/data/kakei/2020np/gaikyo/
国民年金にプラスして加入を検討すべき制度

フリーランスで働く人にとって、厚生年金と国民年金の差額を補填する方法を把握することはとても大切です。ここでは、少ない掛金で備えられるおすすめの制度を紹介しますので参考にしてください。
国民年金基金
国民年金基金は国民年金の2階部分になれる公的な年金制度です。会社員の年金との差額を埋めるために創設されました。
老齢年金として1口目は終身年金A型、B型から選択する必要があり、2口目は受給期間が決まっている確定年金の5種類の中から選択します。受給前もしくは保証期間中に亡くなられた場合は遺族の方に一時金が支給されます。(B型は除く)
掛金は性別と加入時年齢によって決まり1口目と2口目を合わせた上限は68,000円以内となり、年金額は確定年金が終身年金を超える選択は不可能です。
出典:掛金について|国民年金基金連合会
参照:https://www.npfa.or.jp/check/benefit.html
付加年金
付加年金は国民年金の定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、将来の年金額を増やせます。
付加保険料の月額は400円、付加年金額(年額)は200円×付加保険料納付月数となるため、2年以上受け取ると支払った保険料以上の年金を受け取ることになり、3年目からは付加年金のメリットを活かせるでしょう。
出典:付加保険料の納付のご案内|日本年金機構
参照:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150331-03.html
iDeCo(個人型確定拠出年金)
私的年金のiDeCoは、掛金を拠出し自分で運用方法を選んで運用し資産形成をする年金制度です。20歳以上60歳未満(一部65歳未満)の人であれば誰でも対象であり、拠出限度額は職業によって決められています。
フリーランスや自営業者の掛金の拠出限度額は月額68,000円です。月々5,000円から1,000円単位で自由に決められるだけでなく、全額所得控除の対象となるため節税にも繋がります。
しかし、原則60歳まで引き出しや解約ができないため注意しましょう。
出典:iDeCoをはじめよう|iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)
参照:https://www.ideco-koushiki.jp/start/
小規模企業共済
小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員や個人事業主などのための退職金制度です。
掛金は1,000円から70,000円まで500円単位で掛金を設定でき、その掛金は所得控除できるため節税効果もあります。
共済金に満期はなく、退職や廃業の際に受け取れます。受け取り方法が一括の場合は退職所得扱いに、分割受け取りの場合は雑所得扱いにできるため、節税対策にもなります。また、掛金の範囲内で貸付金制度も利用できます。
出典:小規模企業共済|小規模企業共済(中小機構)
参照:https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
経営セーフティ共済とは、取引先の会社が倒産した際に連鎖倒産や経営難に陥らないように対策を取るための制度です。
掛金の月額は5,000円から20万円まで自由に設定でき、必要経費として算入できるので節税対策としても利用できます。
無担保・無保証人で掛金の10倍まで借入できます。また、自己都合の解約であっても40か月以上納めていれば掛金が全額戻ってくるので後から使用用途の変更も可能です。
出典:経営セーフティ共済|経営セーフティ共済(中小機構)
参照:https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/
フリーランスの年金について理解しよう

会社員とフリーランスの年金の違いは大きいです。その違いをよく理解した上で、フリーランスに転身した後も困らないよう年金対策と税金対策の準備が大切です。
この記事を参考にフリーランスの年金について知り、安心して老後を迎えられるようにしましょう。
Midworks おすすめの案件例
- 芝公園駅 / 港区月額80万〜90万円
- 新宿駅 / 新宿区月額70万〜90万円
- 本郷三丁目駅 / 文京区月額80万〜90万円
- 渋谷駅 / 渋谷区月額70万〜120万円
- 京橋駅 / 大阪市城東区月額100万〜200万円
関連記事
フリーランスのキャリア


SAPフリーランス単価相場は?市場価値のあるスキルや資格も紹介

AWSフリーランス単価相場で知る|市場価値と高収入戦略
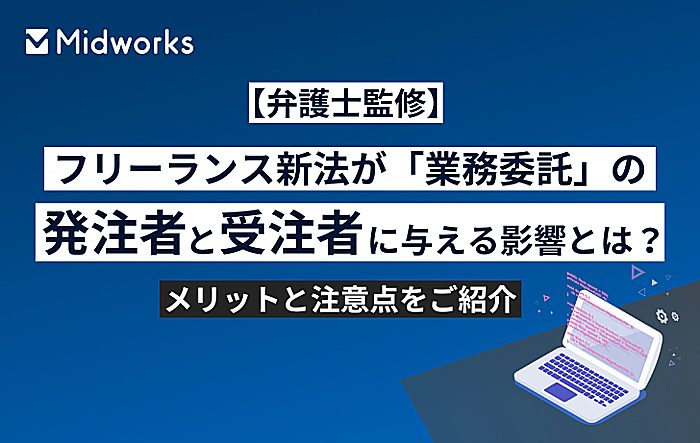
【弁護士監修】フリーランス新法が「業務委託」の発注者と受注者に与える影響とは?メリットと注意点をご紹介
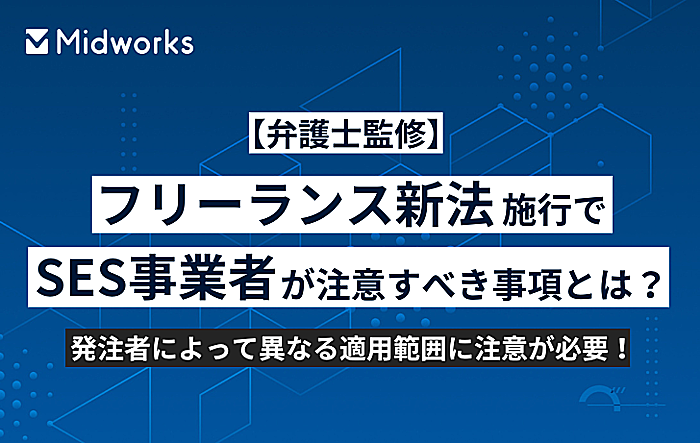
【弁護士監修】フリーランス新法施行でSES事業者が注意すべき事項とは?発注者によって異なる適用範囲に注意が必要!
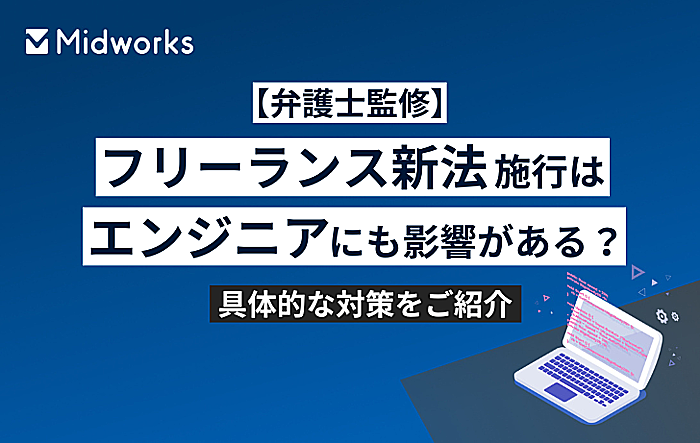
【弁護士監修】フリーランス新法施行はエンジニアにも影響がある?具体的な対策をご紹介
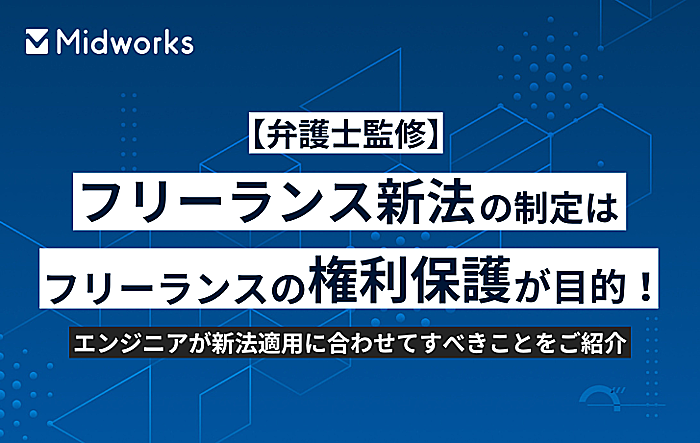
【弁護士監修】フリーランス新法の制定はフリーランスの権利保護が目的!エンジニアが新法適用に合わせてすべきことをご紹介
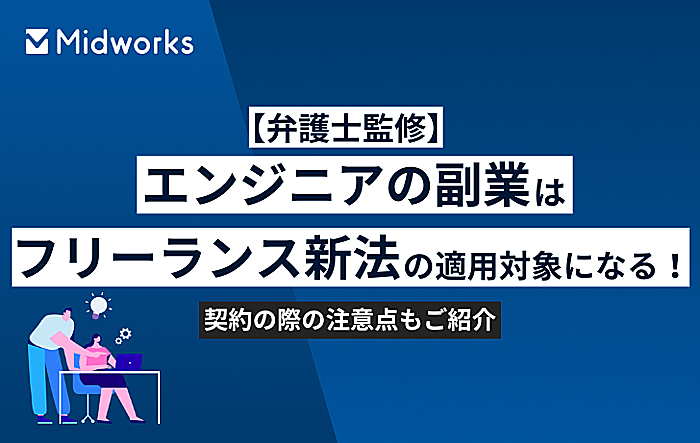
【弁護士監修】エンジニアの副業はフリーランス新法の適用対象になる!契約の際の注意点もご紹介
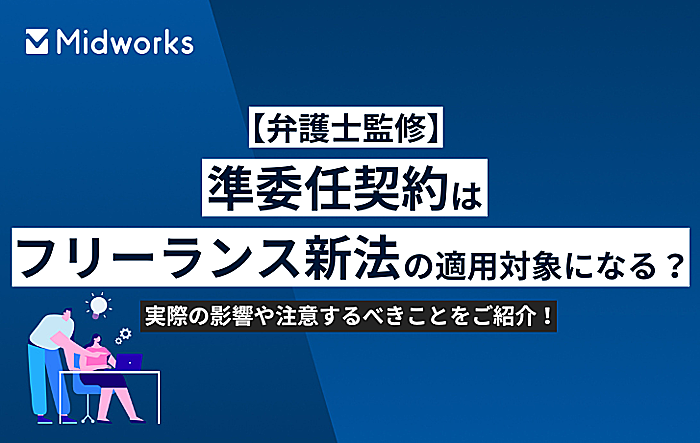
【弁護士監修】準委任契約はフリーランス新法の適用対象になる?実際の影響や注意するべきことをご紹介!
インタビュー


紹介からたった1週間で現場にフリーランスが参画!スピード感で人手不足を解消-株式会社アイスリーデザイン様
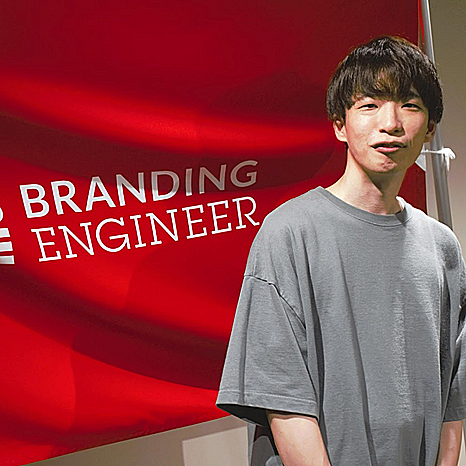
受託開発企業から、フリーランスで自社開発企業へ!

事業の成長スピードに現場が追い付かないという悩みをMidworks活用で解決-株式会社Algoage様
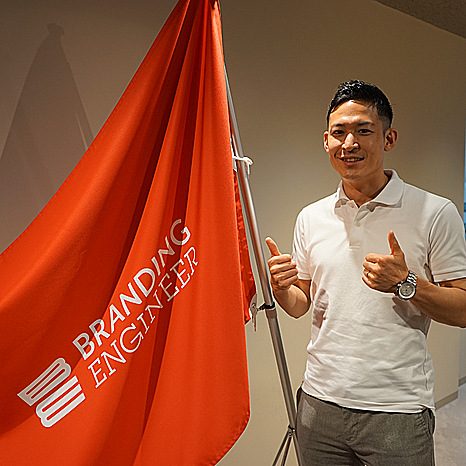
30代でも遅くない!未経験からエンジニアへのジョブチェンジで天職と巡り合った、英語が喋れる元消防士のフリーランスへの挑戦

フリーランスに転向し収入も生活も向上 アップデートを続けるエンジニアの情報収集方法を公開
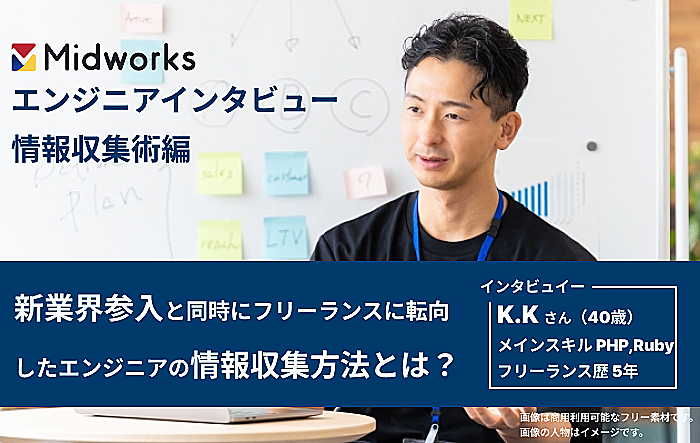
新業界参入と同時にフリーランスに転向したエンジニアの情報収集方法とは?
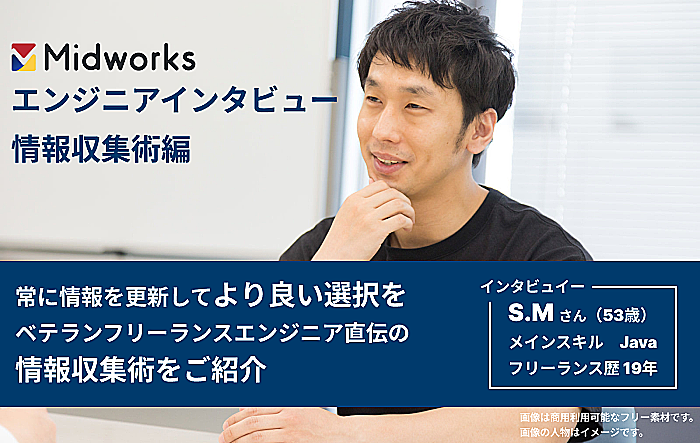
常に情報を更新してより良い選択を ベテランフリーランスエンジニア直伝の情報収集術をご紹介
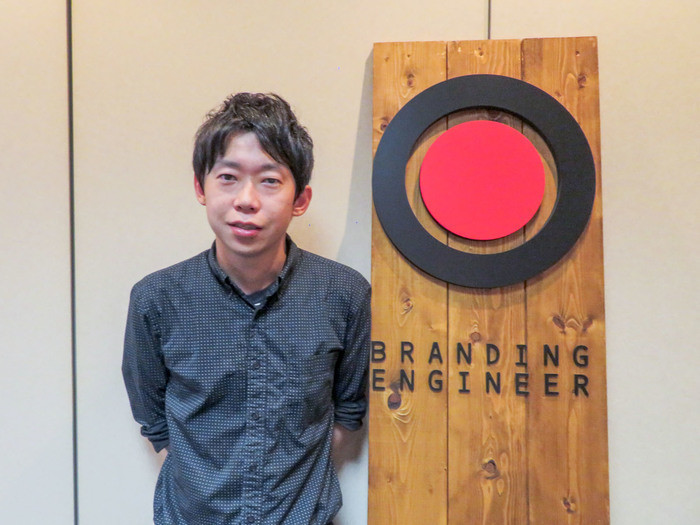
理想的なエンジニア像を描き、自由な働き方を求めてフリーランスへ。
フリーランスの基礎知識


何年の経験でフリーランスエンジニアは案件を獲得できる?未経験の場合についても解説

20代前半でもフリーランスエンジニアになれる?平均年収やメリット・デメリット

副業フリーランスはおすすめ?未経験からの始め方やメリット・デメリットを解説

【初心者におすすめ】ITパスポート試験で合格点は?合格に近づく勉強法

IT業界の現状は?市場規模や今後の動向についても解説!

フリーランスのソフトウェア開発に求められる「12のこと」をご紹介!必要なスキルも解説

【職種別】フリーランスエンジニアの年収一覧!年代やプログラマーの言語別にも紹介
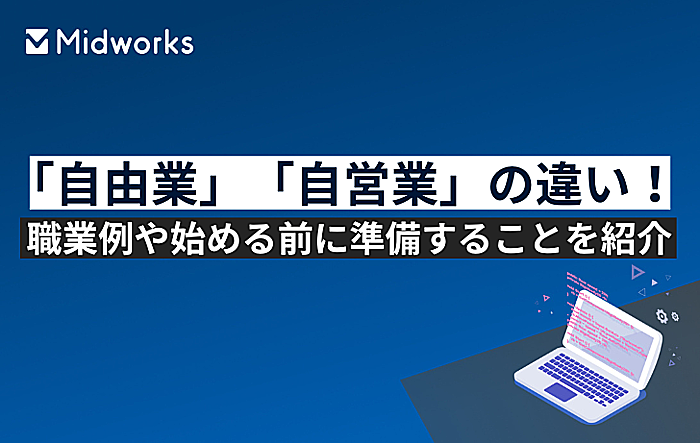
実は知られていない「自由業」「自営業」の違い!職業例や始める前に準備することを紹介
プログラミング言語

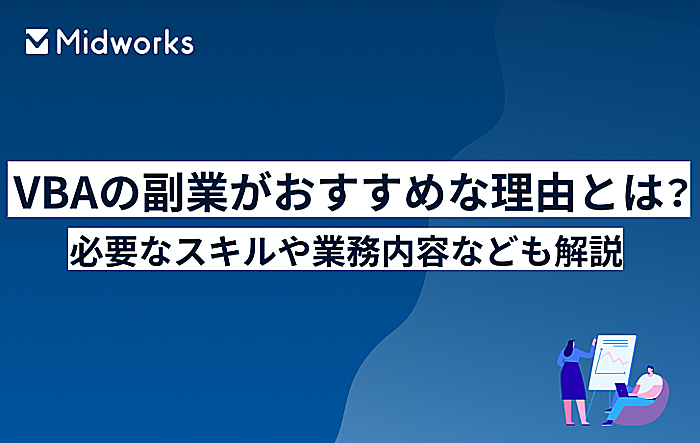
VBAの副業がおすすめな理由とは?必要なスキルと業務内容・案件の探し方も解説
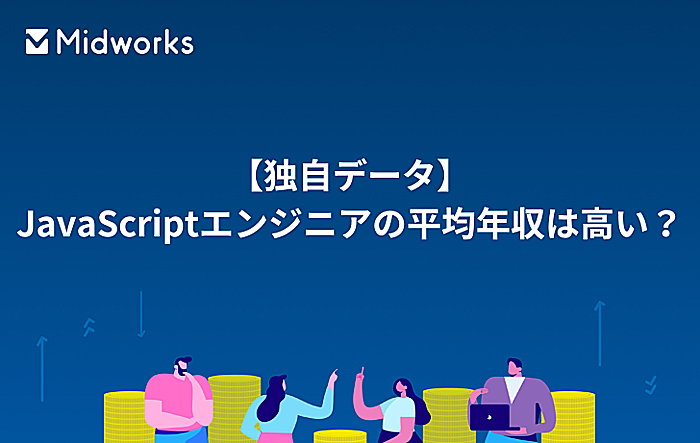
【独自データ】JavaScriptエンジニアの平均年収は高い?年収を上げる方法もご紹介
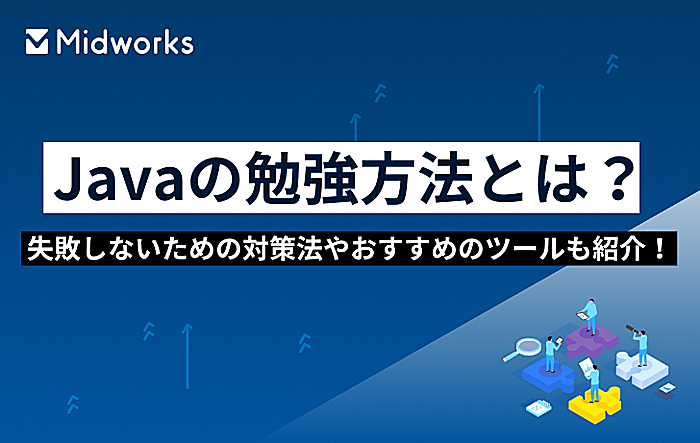
Javaの勉強方法とは?失敗しないための対策法やおすすめのツールも紹介!

【独自データ】PHPエンジニアの年収は高い?年収を上げるための方法もご紹介!
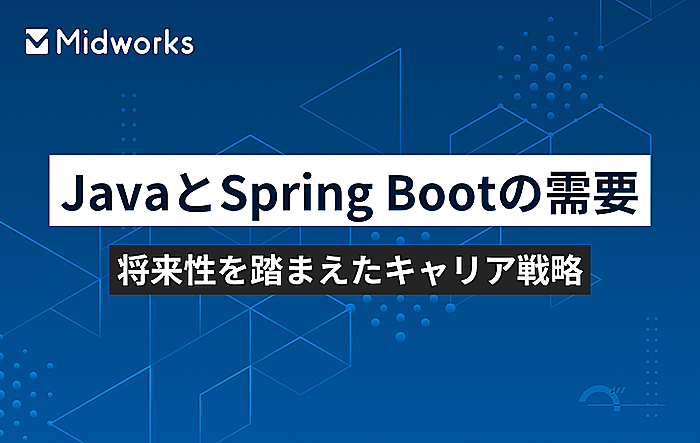
Title JavaとSpring Bootの需要|将来性を踏まえたキャリア戦略

Java Gold資格の難易度とキャリア価値を徹底解説
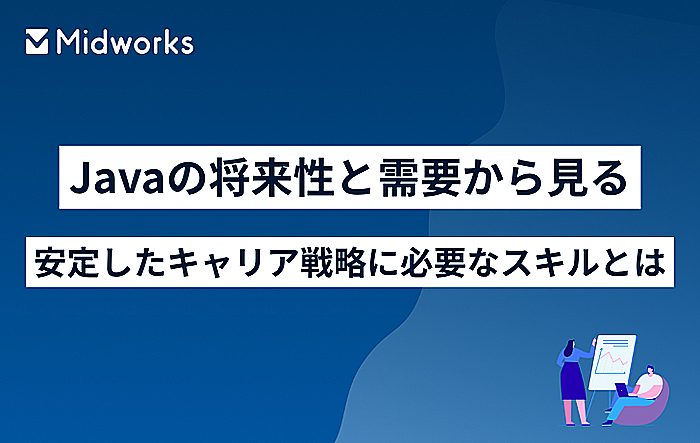
Javaの将来性と需要から見る|安定したキャリア戦略に必要なスキルとは
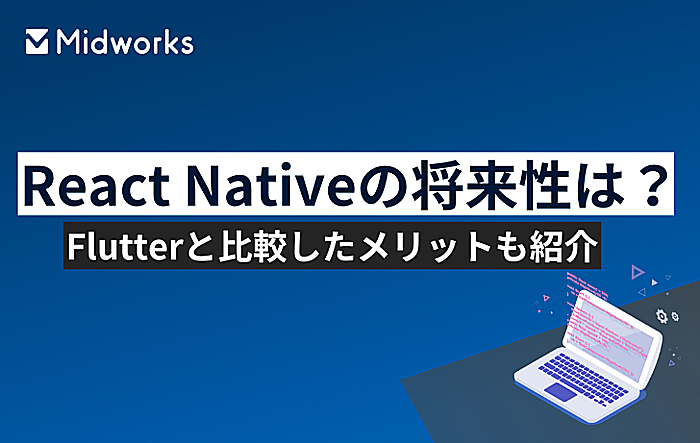
React Nativeの将来性は?Flutterと比較したメリットも紹介
企業向け情報

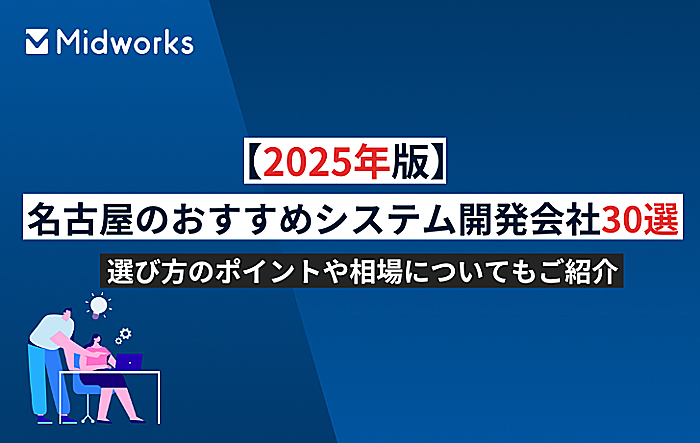
【2025年版】名古屋のおすすめシステム開発会社30選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
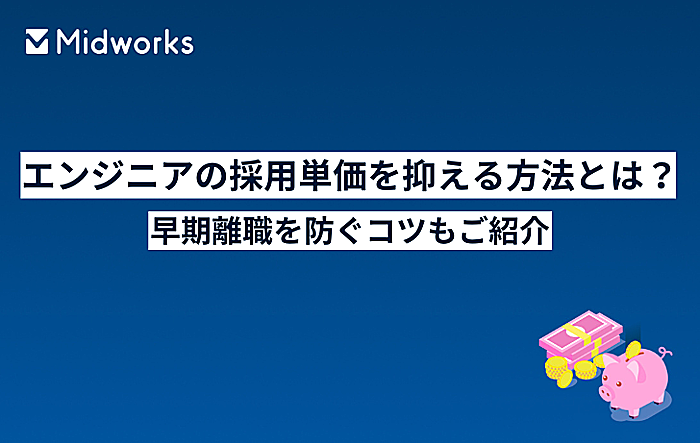
エンジニアの採用単価を抑える方法とは?早期離職を防ぐコツもご紹介
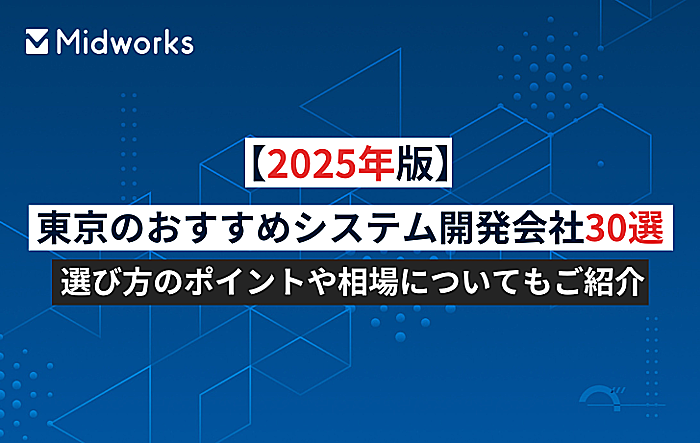
【2025年版】東京のおすすめシステム開発会社30選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
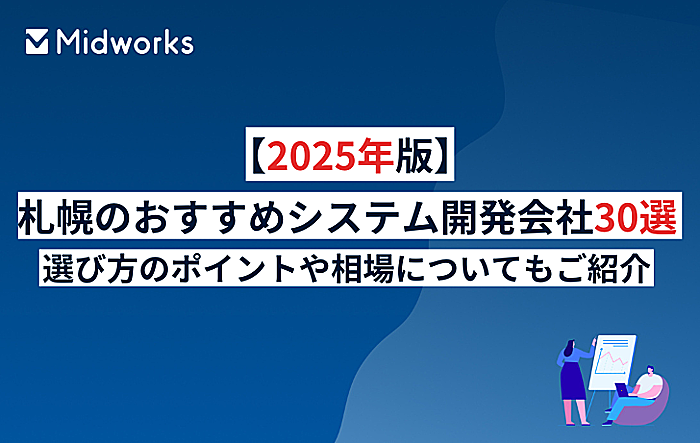
【2025年版】札幌のおすすめシステム開発会社30選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
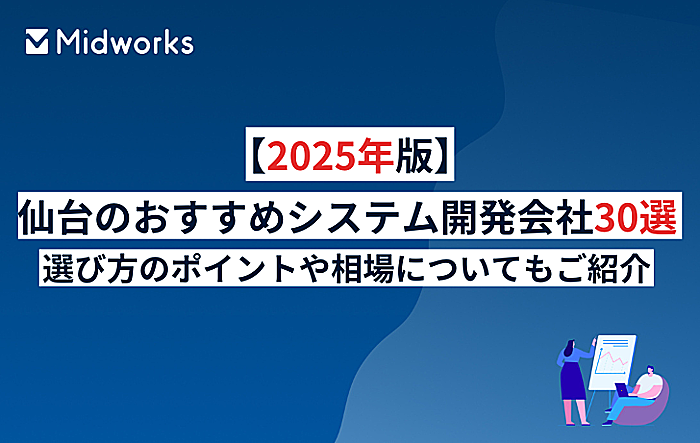
【2025年版】仙台のおすすめシステム開発会社30選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
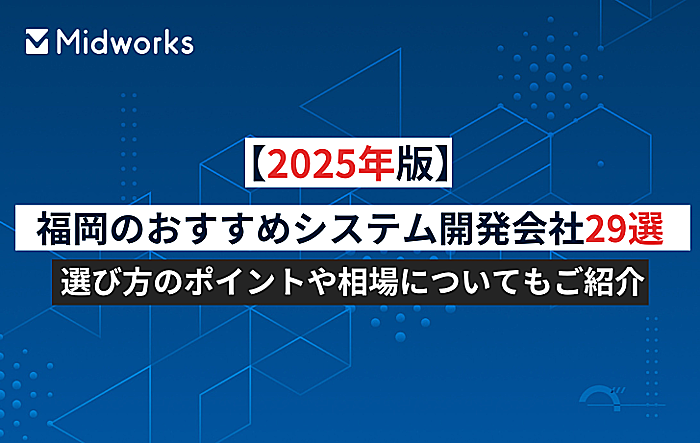
【2025年版】福岡のおすすめシステム開発会社29選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
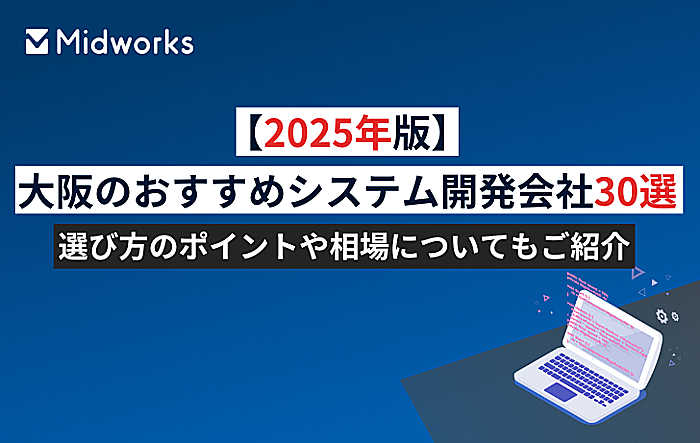
【2025年版】大阪のおすすめシステム開発会社30選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
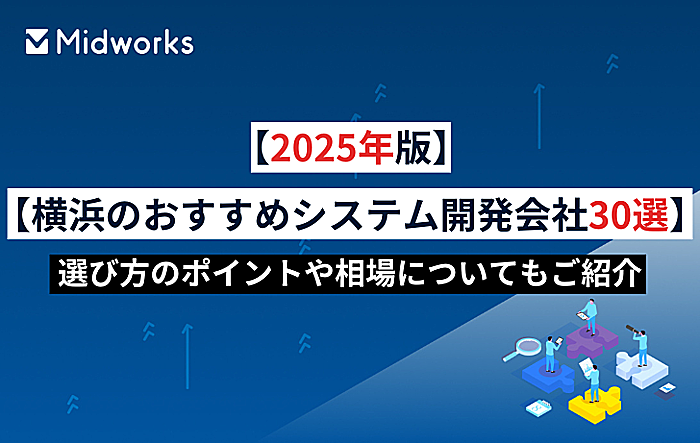
【2025年版】横浜のおすすめシステム開発会社30選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
業界特集


医療業界のフリーランスエンジニア向け案件特集|DX化が進む成長市場で求められるスキルと働き方のポイント

自動車業界フリーランスエンジニア案件特集|CASE時代の開発をリード!求められる技術とプロジェクト事例

EC業界のフリーランスエンジニア向け案件特集|急成長業界で必要とされるスキルや働き方のポイントもご紹介

セキュリティ業界のフリーランスエンジニア向け案件特集|案件参画で身につくスキルや参画の際に役立つ資格もご紹介

金融業界(Fintech領域)のフリーランスエンジニア向け案件特集|業界未経験でも活躍する方法もご紹介

生成AI分野フリーランスエンジニア案件特集|最先端技術を駆使!注目スキルと開発プロジェクト事例

小売業界フリーランスエンジニア案件|年収アップとキャリアアップを実現!最新トレンドと案件獲得のコツ