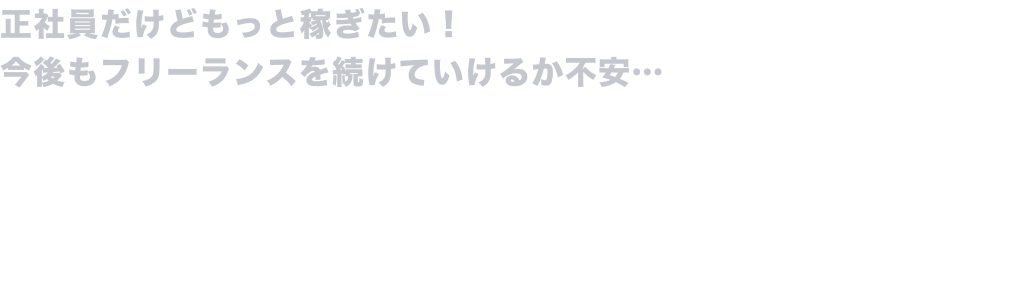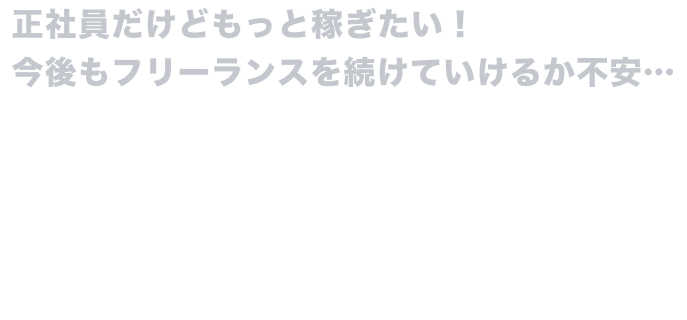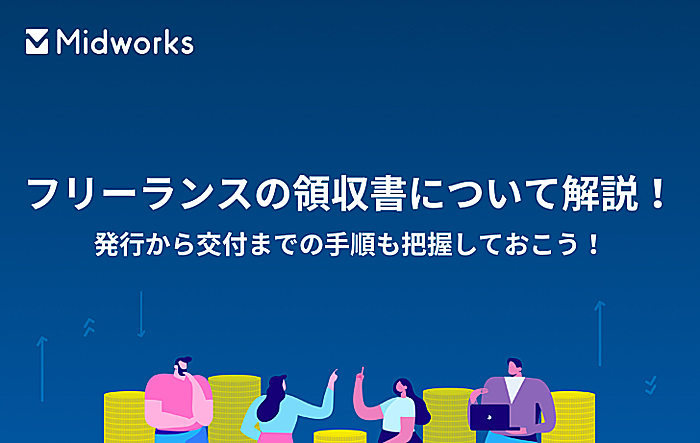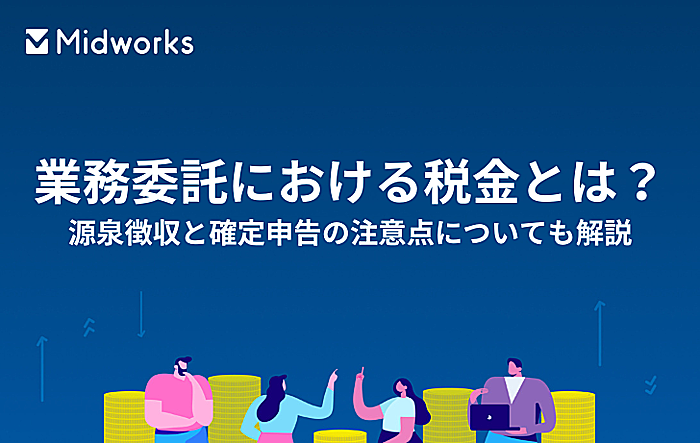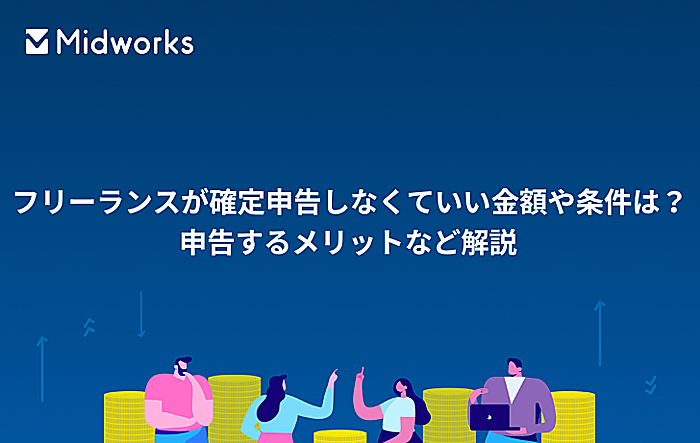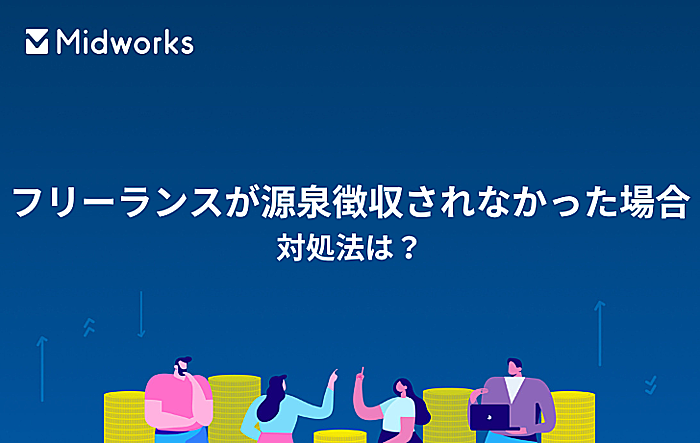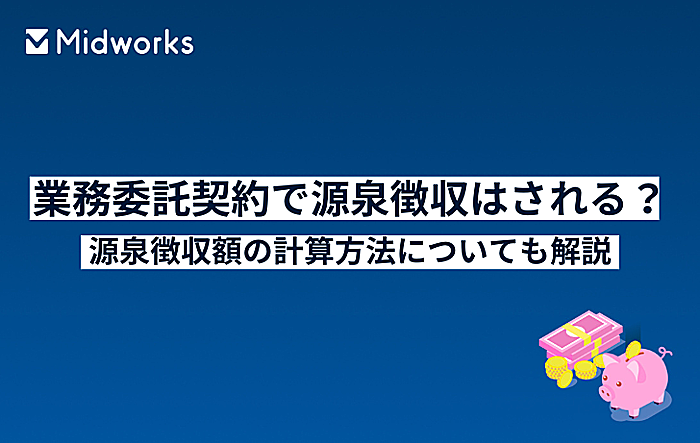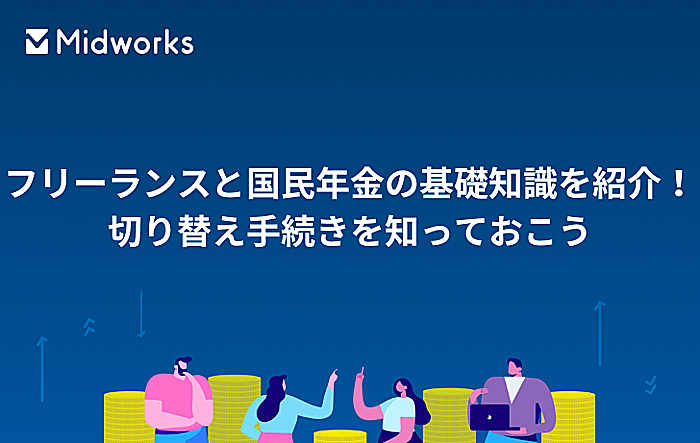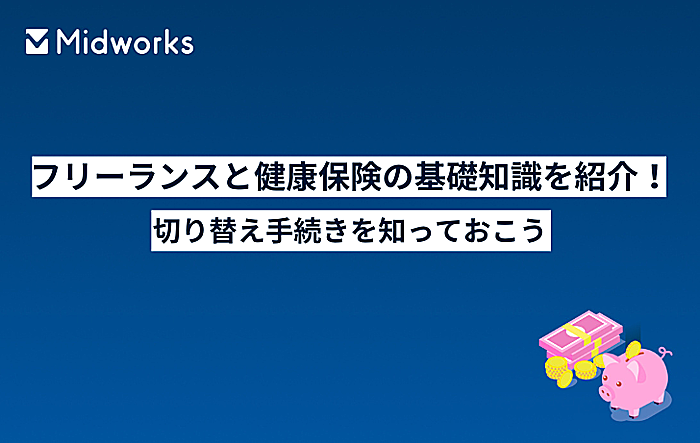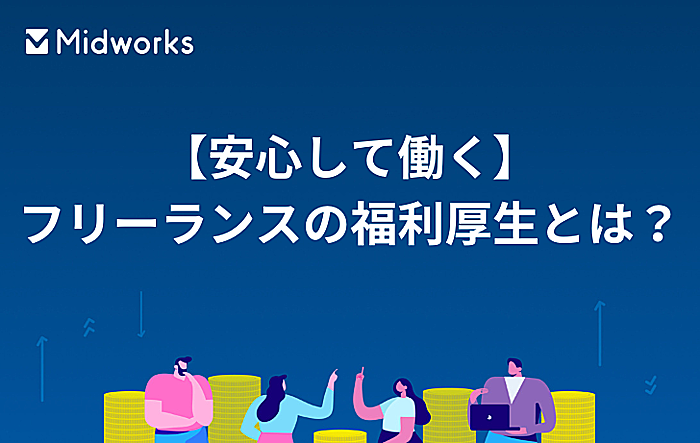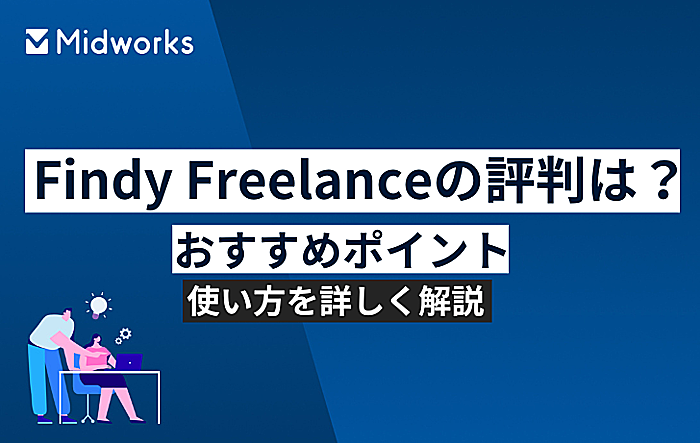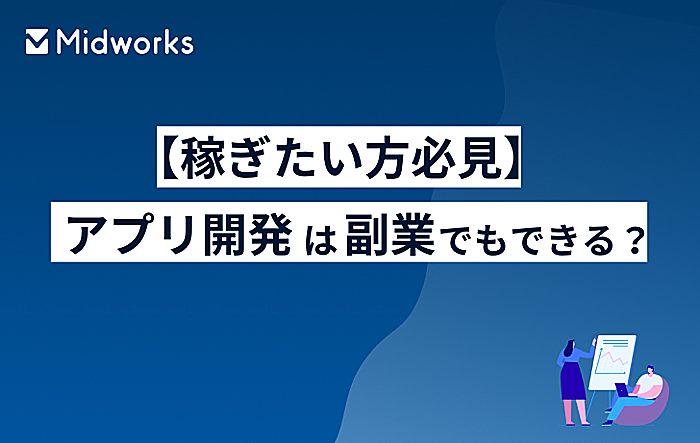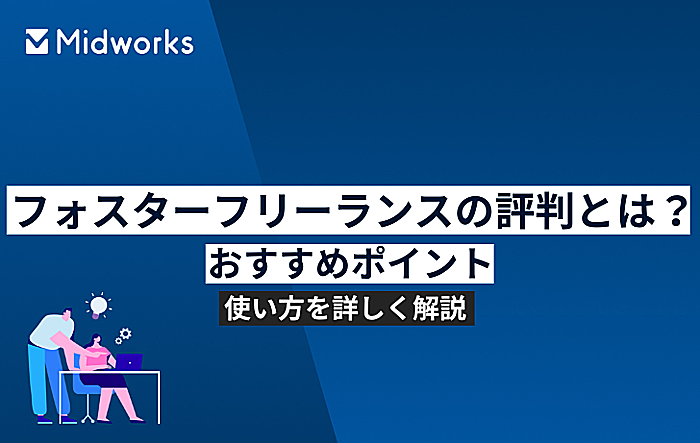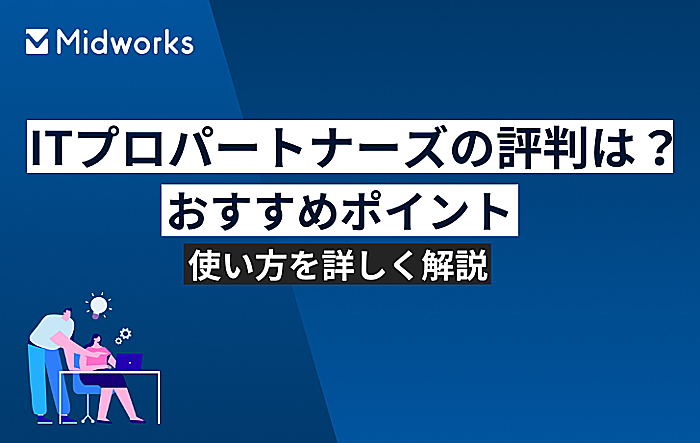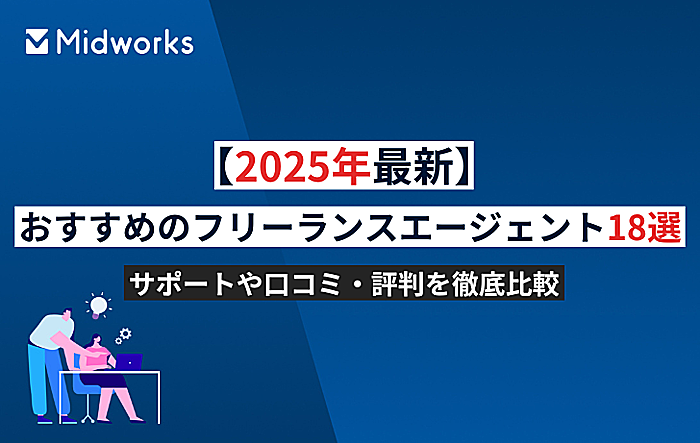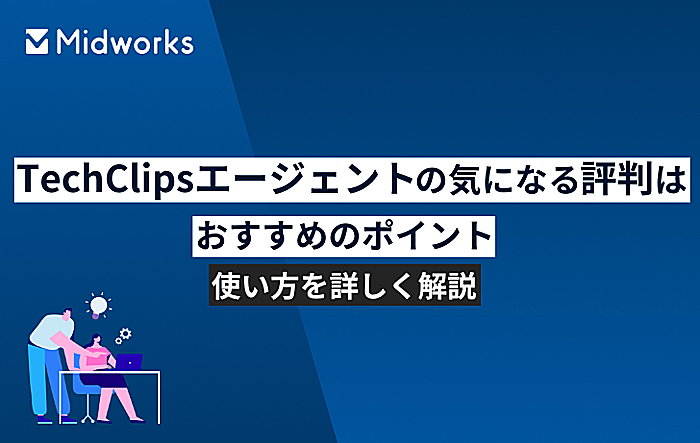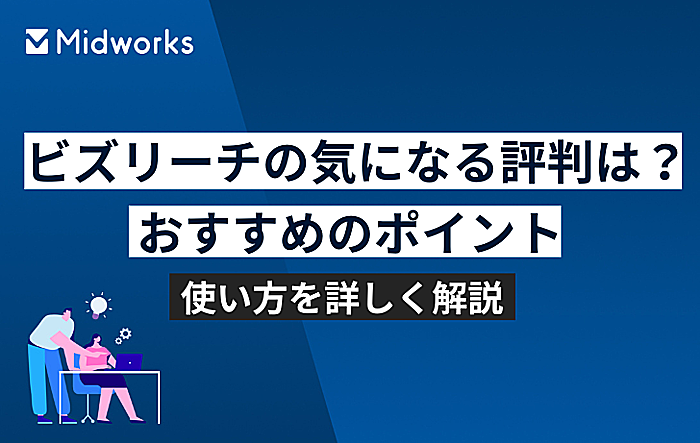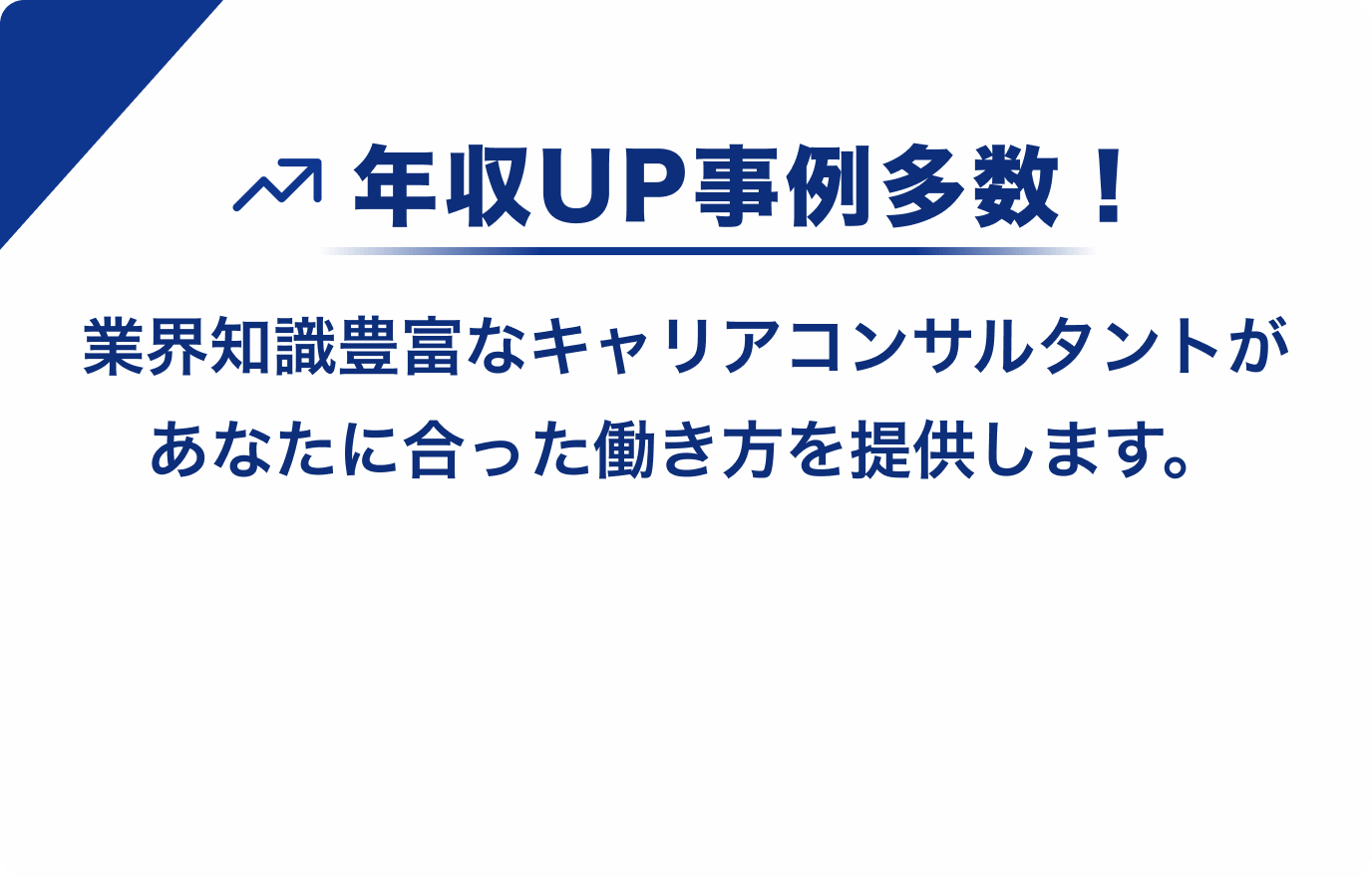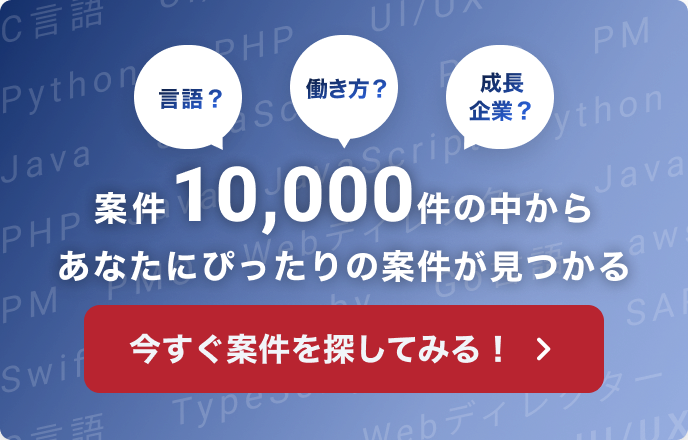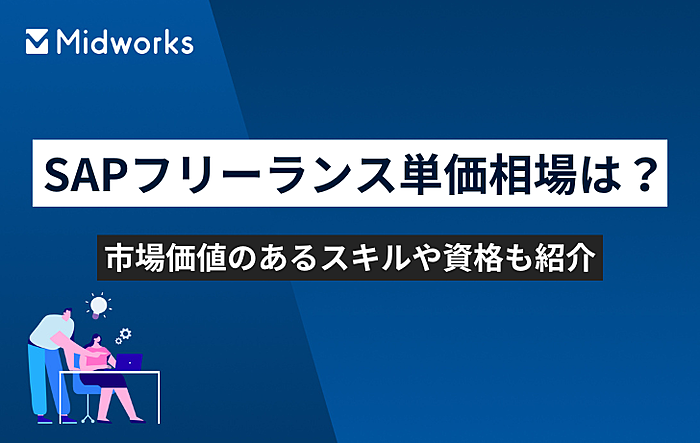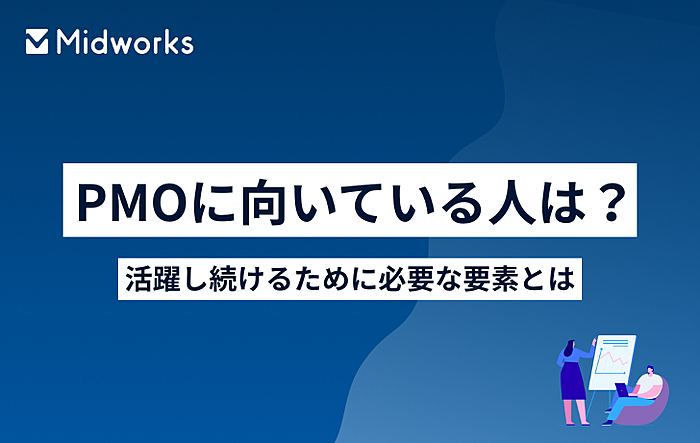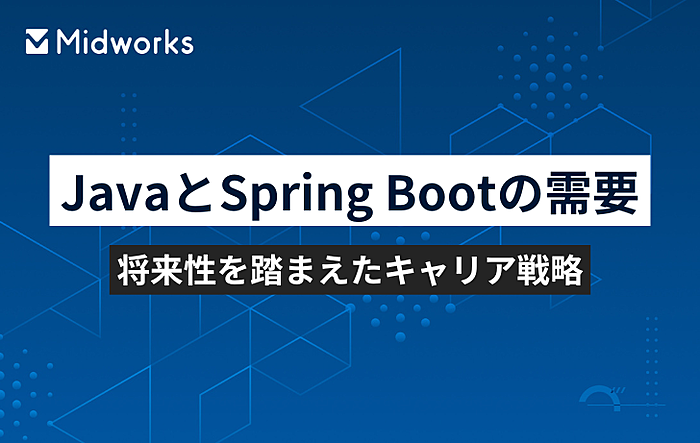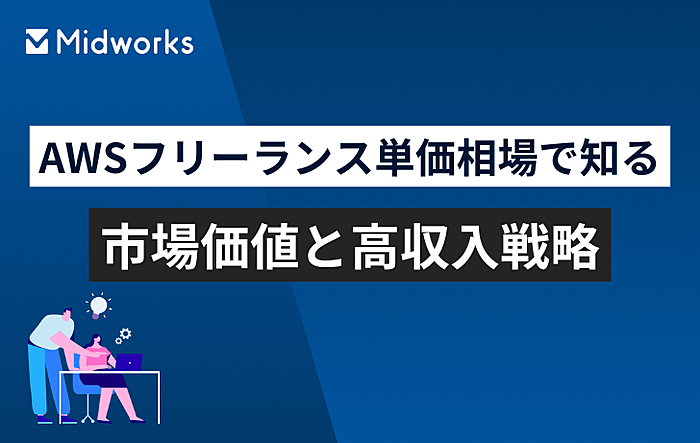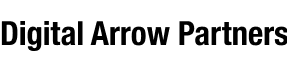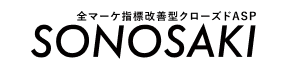統計検定とは、統計に関する知識や活用力を評価する試験です。検定試験は統計検定5種、統計調査士2種、データサイエンス系の3種に区分されており、しっかりと対策をすれば独学でも合格を目指せます。
本記事では、統計検定の概要に加え、それぞれの試験概要、学習方法について解説しています。統計検定の取得を目指している方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
目次を閉じる
統計検定とはどんな試験?

統計検定は、統計についての知識や技術などの能力を評価する試験です。統計についての教育の重要性が増す中、2011年に統計教育の成果を確かめる目的で2級から4級までが、翌年には1級が発足しました。
その後さらに統計調査士、データサイエンスといった実務的な技術などについての区分が追加され、2023年現在では計10区分の試験が存在しています。このように、統計検定はさまざまな統計分野に対応し、初級から専門家レベルまでの知識を幅広く測れる検定試験といえるでしょう。
出典|参照:統計検定|Japan Statistical Society Certificate
出典|参照:統計検定と統計能力の評価 | 中央調査社
統計検定は何に役立つの?
統計検定に合格する利点は、その学習を通して統計についての知識が得られることです。現在ではデータの解析は、あらゆるところで行われています。たとえば、ビジネスでグラフや表などを使ってデータを示すのは一般的な手法です。
国の政策なども統計調査の結果を判断材料にしている場合があります。統計の知識があれば、よりよいデータの表現方法を考えたり、政策などの意味を深く理解したり、といったことができるようになるでしょう。
次に、データ解析などを研究する大学の教育機関の入試において、統計検定の取得が有利に働く場合があります。たとえば滋賀大学データサイエンス研究科では、一次選考に統計検定2級の結果を活用しており、準1級以上に合格していると統計学の成績は満点として扱われます。
もちろん、統計検定に合格していると就職でも有利です。とりわけデータサイエンスやAI技術にとって統計の知識は重要であることから、その能力を示せる統計検定はこれらの職種における採用でも評価されます。
統計検定は細かく分けると10種類ある

統計検定は2011年の発足以来、多様化する社会のニーズに合わせてその種類を増やして来ました。
そのため、統計検定の区分は多く、2023年現在、統計検定5種、統計調査士2種、およびデータサイエンス系3種の合計10種類もあります。初めて統計検定を知った人は、この区分が何かわかりにくいでしょう。
そこで、ここではその10種類の検定試験について、簡単にご説明しましょう。
出典|参照:統計検定とは|統計検定
出典|参照:統計検定|Japan Statistical Society Certificate
統計検定4~1級
統計検定4級、3級、2級、準1級、1級は一般的な統計学の知識について測る試験です。4級および3級は、データを整理するのに使うグラフや表の書き方や読み方、それ以外では確率分布や検定など高度な数学を用いた実践的な統計学についての問題が出題されます。
そのため、実際の仕事などで評価されるのは2級以上、4級や3級は入門・教養のための資格と考えてよいでしょう。
統計調査士・専門統計調査士
統計調査士と専門統計調査士の検定試験では、実際の統計データを集める上での知識を問われます。
そのため取得すると統計調査の法規や役割、データの活用法といった実際の業務に必要とされる知識を有していることの証明になるでしょう。
データサイエンス基礎・データサイエンスエキスパート
データサイエンス(DS)基礎、DS発展、およびDSエキスパートの3種類の検定は、データ解析についての知識やスキルを測る試験です。基礎では高校や大学入試、発展では大学教養、エキスパートになると大学専門レベルの内容が出題されます。
実際のデータ解析を行う上で必要となるExcelやPythonでの解析スキルも求められ、より実務に即したデータの取り扱いに焦点を当てた検定区分となっています。
結局どれを選べばいいの?
専門性を意識せずに統計学の一般的な知識を得たいなら、統計検定4〜1級がおすすめです。また、就職や大学・大学院の進学で役立てたいなら、その中でも2級以上を取得しておくとよいでしょう。
統計調査士や専門統計調査士の検定は、統計調査士になる場合や統計データを収集する職種に就く時のスキルを磨くのに役立ちます。
データアナリストやAI技術者で必要とされるような、より専門的なデータの扱い方を身につけたい場合は、データサイエンス系の検定の中から自分のレベルにあった資格を選ぶと効果的です。
統計検定の取得で得られるメリット

ここまでで統計検定の概要についてご説明してきました。しかし「取得することでどのようなメリットがあるの?」という疑問を抱いた人もいることでしょう。資格の勉強には時間と手間がかかるため、それを上回る利点がなければ、なかなか取得に向けて行動する気にはなれません。
しかし、統計検定は実際の仕事などでも有用な資格であり、目指すキャリアによっては挑戦して損のない資格です。ここでは、より具体的に統計検定の取得で得られるメリットについてご紹介します。
統計処理のスキルが身につく
統計検定を取得するメリットは、統計処理などのスキルが身につきその理解を深められることです。統計処理といったスキルは、AI開発を専門とするAIエンジニアには欠かせないスキルであり、このスキルが身につくとAIエンジニアへの道が開けます。
AI開発業界のエンジニア不足は深刻であり、今後も需要の高い分野であることが予想されているため、統計処理のスキルは将来的にも需要の高いスキルであるといえるでしょう。
就職や転職で有利に働くことがある
統計検定は統計学に関する知識やスキルの証明となるため、就職や転職で評価される場合があります。
統計検定があれば、独学でも専門的な知識を有していることの証明になり、しかも実際の業務にかかわるような内容が盛り込まれているため、即戦力としても評価されます。統計検定が比較的挑戦しやすい転職や就職でのアピールポイントのひとつとして役立つでしょう。
【種類別】統計検定とその他の試験概要
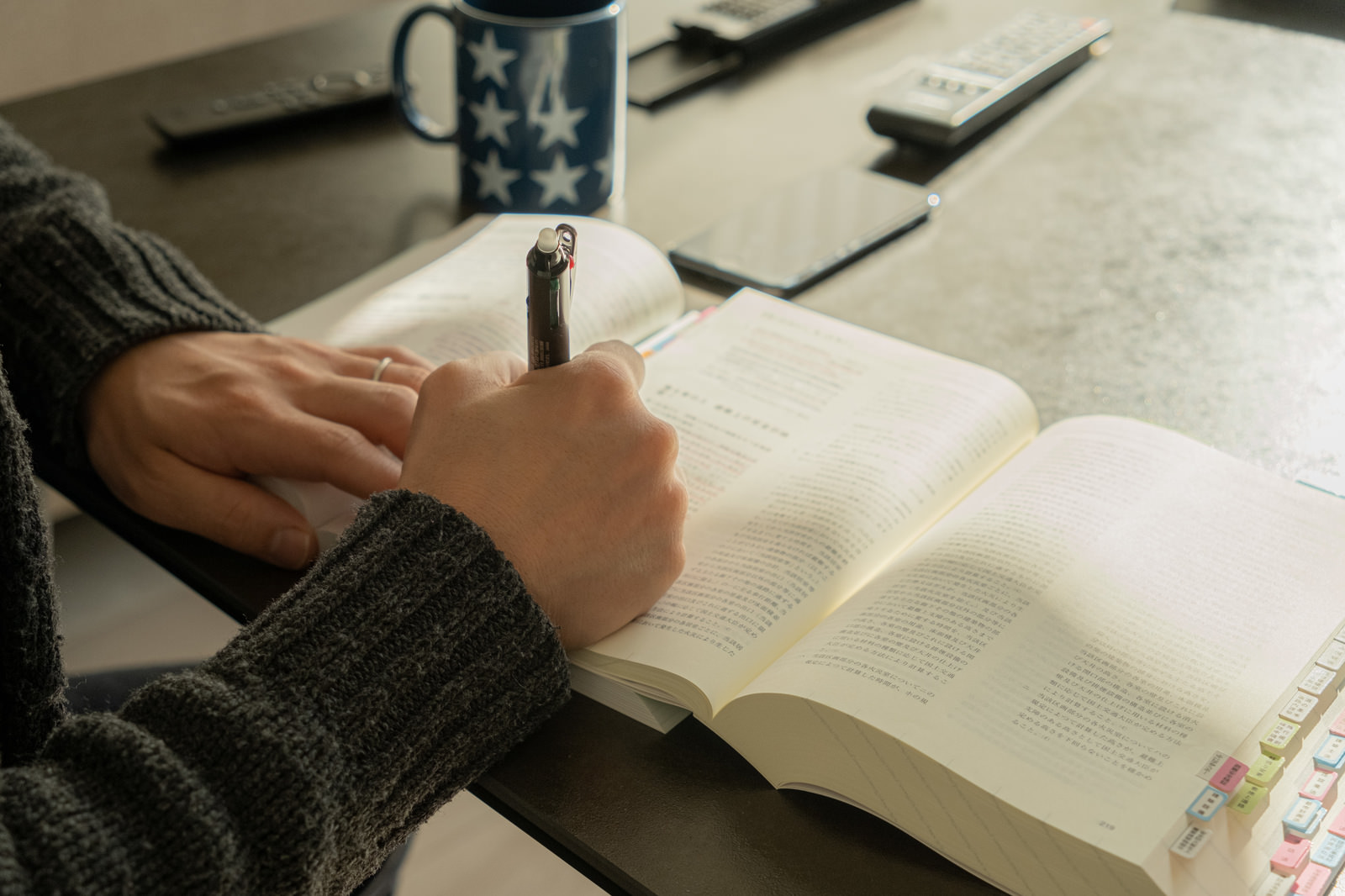
統計検定の区分は10種類もあり、それぞれどのような違いがあるかわかりにくいかもしれません。そこで、それぞれの検定の出題範囲や出題形式といった試験の概要をまとめました。
自分のキャリアと能力から最適な種類の資格を選ぶ時の参考にしてください。
出典|参照:統計検定|Japan Statistical Society Certificate
統計検定4級の試験概要
4級は用語や基本的な考え方などの、統計学についての基礎的な知識があるか確かめる検定です。データを理解する上で最低限必要な、グラフの読み方などの統計的なリテラシーを検定することを実施趣旨としています。
試験内容はグラフやクロス集計表などの表の読み方、確率の基礎などが主となり、中学で習う数学の知識があれば十分に理解できるしょう。
以前は記述式のPBT試験でしたが、2021年以降は廃止され、コンピューター上で解答するCBT方式の試験のみとなっています。出題形式は4〜5択問題、出題される問題数は30問程度で試験時間は1時間となっています。
2021年6月の試験を受験した人数は147名で合格率は72.8%と高く、統計検定の中ではかなり簡単な区分です。そのため10~30時間ぐらいの勉強でも合格できるとされています。
これから統計学の勉強を始めようとする人におすすめの検定です。
出典|参照:1級以外の種別の紙媒体を利用した従来の試験(PBT方式試験)の終了について(更新)|統計検定:Japan Statistical Society Certificate
出典|参照:2021年6月20日試験|統計検定:Japan Statistical Society Certificate
統計検定3級の試験概要
3級では4級の内容に加えて大学で学ぶ統計学の基礎につながるような確率分布や推計、相関や回帰などの知識について出題されます。
高校で学ぶ数学Iのデータ分析に相当する問題解決能力を身につけることを趣旨のひとつとしているため、高校生でも十分に合格可能です。
試験問題は4級と同じく1時間のCBT形式で、出題される問題は30問程度の4~5択問題で構成されています。PBT試験は2021年以降は廃止されてCBT形式のみになりました。
2021年6月の試験を受験した人数は320名と4級受験者数の2倍以上ではあるものの、合格率は75.6%と4級と同程度に高く、取得するのは難しくない検定区分です。
勉強時間も統計学の初心者でも20~30時間程度、統計学や数学が得意なら10時間程度で問題ないでしょう。高校レベルの数学に自信がある初学者が、まず目指すのにちょうどいいレベルの検定です。
出典|参照:1級以外の種別の紙媒体を利用した従来の試験(PBT方式試験)の終了について(更新)|統計検定:Japan Statistical Society Certificate
出典|参照:2021年6月20日試験|統計検定:Japan Statistical Society Certificate
統計検定2級の試験概要
2級は仮説の検証といった、大学で学ぶ基礎的な統計学と同程度の実力があるか測ることを検定の実施趣旨としています。出題範囲は3~4級のものに加えて、より幅広いデータの扱い方や確率分布、標本分布、仮説検定、線形モデルなどが含まれます。
試験はCBT形式で行われ、時間は90分、問題数は35問程度の4~5択問題なので、3級よりもボリュームも多めです。PBT試験は廃止されCBT形式のみとなっています。
2021年6月のPBT試験を受験した人数は731名と3級受験者のほぼ2倍、一方合格率は34.1%で3級の半分以下しかありませんでした。
合格するには50時間程度の学習が必要とされており、しっかりと準備しておかなければ合格は難しいでしょう。
ビジネスでも使える統計の基礎となる知識やスキルを有する証明となるので、就職や転職活動で統計検定を役立てたいのなら、2級の取得を目標とするのがおすすめです。
出典|参照:2021年6月20日試験|統計検定:Japan Statistical Society Certificate
統計検定準1級の試験概要
準1級はさまざまな実際の問題に統計学を応用する能力を測ることが実施趣旨です。大学の3~4年で学ぶ統計学と同程度の知識が必要で、データ収集から解析手法、結果の解釈までの総合的な力が試されます。
合格には300時間程度の勉強が必要になり、2級よりも格段に難易度は上がります。実際、2021年6月の試験を受験した人数は704名で合格率は23.6%であり、統計検定の中では狭き門といえるでしょう。
CBT形式で約25~30問の問題数、試験時間は1時間半、3級までとは異なり5択問題の他に数値を入力する問題も出題されます。PBT試験は廃止されて今はCBT形式のみとなっています。
難易度は高いですが実用性のある総合的な能力の証明となり、統計学を扱うビジネスの世界では高く評価される検定区分といえるでしょう。
出典|参照:2021年6月20日試験|統計検定:Japan Statistical Society Certificate
統計検定1級の試験概要
1級は実務でのデータ解析で使われる統計学が理解できているかを問う検定区分です。大学で統計学を専門的に学んで得られるような知識が必要とされ、合格には統計や数学についての深い理解が必要とされます。
試験は統計数理と統計応用の二つに分かれていて、両方とも合格することで資格が取得可能です。ただし、どちらか一方に合格してから10年以内にもう一方に合格してもよいとする経過措置もあります。
また、統計応用は「人文科学」「社会科学」「理工学」「医薬生物学」の4つの分野があり、申し込みの段階で選択して受験するシステムです。筆記のみのPBT試験で午前中に統計数理、午後に統計応用の試験が行われます。試験時間はともに90分です。
PBT試験は廃止されてCBT形式のみとなっています。
2022年11月に実施された試験では、統計数理は受験者数998名で合格率22.4%、統計応用は受験者数911名で合格率20.6%でした。
300時間ほどの勉強が必要とされる上に合格率が低く、しかも両方の試験に合格しなければ資格を得られないので、取得は難しいといえるでしょう。
しかし、難易度が高いことから統計解析について優れた能力の証明になるため、データアナリストを初めとした職種での転職では高く評価される資格です。
出典|参照:2022年11月20日試験|統計検定:Japan Statistical Society Certificate
統計調査士の試験概要
統計調査士検定は、公的な統計などで必要とされる統計法規や手法統計データの活用法などについての理解を測る試験です。
また、上位資格の専門統計調査士は、この統計調査士に合格していなければ取得できません。
要求される数学の知識は高校レベルであまり高くはありませんが、代わりに、法律や調査員の役割といった知識を問う問題が半分程度出題されるのが特徴です。
試験時間は1時間、30問の5択問題で出題されるCBT形式です。PBT試験は廃止されてCBT形式だけになりました。2021年11月の試験では受験者数128名、合格率28.9%で統計検定の種別の中では中間にあたる難易度です。
勉強にかかる時間は、初めて統計を学ぶ人なら30時間程度、すでに統計についてある程度理解がある場合は10時間前後でしょう。数学の問題が少ないことから文系の人でも挑戦しやすく、統計調査の業務を行うなら取得を検討しましょう。
出典|参照:2021年11月21日試験|統計検定:Japan Statistical Society Certificate
専門統計調査士の試験概要
専門統計調査士は統計調査の企画、管理、とりまとめ、さらに調査員の指導を行う上で必要となる知識や能力を測る検定です。
また、統計調査士を取得していなければ合格しても資格として認められないことには注意してください。専門統計調査士の試験に合格している場合、5年以内に統計調査士を取得すると専門統計調査士として認められる経過措置があります。
統計学の知識については大学の教養で学ぶ基礎的なレベルであり、統計検定2級と同程度の知識が必要です。統計調査士に比べると計算問題の割合が多めになっています。
勉強にかかる時間は、初学者なら40~50時間程度、すでに統計について十分程度理解がある場合は20時間前後でしょう。
試験時間は1時間半。CBT形式で、40問の5択問題で出題されます。PBT試験は現在は廃止されています。2021年11月の試験を受験した人数は74名で合格率は25.7%と、統計検定の中ではやや難しい部類です。
企業でのリサーチ業務でも評価される資格なので、統計調査でキャリアを積みたい人にはおすすめの資格です。
出典|参照:統計検定 専門統計調査士|統計検定:Japan Statistical Society Certificate
出典|参照:2021年11月21日試験|統計検定:Japan Statistical Society Certificate
データサイエンス基礎(DS基礎)の試験概要
DS基礎は、データサイエンスに必要なデータの取り扱いや統計学のスキルを評価する検定で、マイクロソフト社の表計算ソフトであるExcelを使ってパソコン上でデータ処理を行うテスト方式であることが特徴です。
高校の数学科と情報科の内容を中心にしており、大学入試レベルの問題が出題されます。
Excelは試験会場のパソコン内のものを使い、CBT形式で問題数は45問程度、試験時間は1時間半です。2021年から始まった資格で、受験者数や合格率は公開されていません。合格に必要な統計学のレベルから、統計検定3~2級と同程度の難易度と考えられています。
合格に必要な勉強時間は、統計学の初学者なら50時間前後、統計検定2級合格と同程度の知識レベルであれば20時間程度です。データサイエンスを今から始めようとする人でも挑戦しやすい資格といえるでしょう。
出典|参照:「統計検定 データサイエンス基礎(CBT)」が7月13日から開始されました|統計検定:Japan Statistical Society Certificate
データサイエンス発展(DS発展)の試験概要
DS発展は大学教養レベルのデータの取り扱いや解析手法、AIとその倫理といったデータサイエンスに関するスキルについて評価する資格です。統計検定2級と同程度の実力が必要とされており、加えてフローチャートやPythonを元にした問題も出題されます。
試験時間は1時間、30問程度の問題数でCBT形式です。受験者数や合格率は公開されていません。大学で統計学を学んだ人にとってはそれほど難易度が高い試験ではありませんが、出題範囲が広いので初学者にとっては少し難しいと考えられます。
取得すればデータサイエンスを扱う職種における就職や転職で評価される資格といえるでしょう。
データサイエンスエキスパート(DSエキスパート)の試験概要
DSエキスパートは2023年5月に試験が行われるようになった新しい資格です。データサイエンス系検定の最上位であり、大学専門レベルの高度なデータ解析、統計学、AIなどの非常に幅広い知識が要求されます。
試験時間は1時間半、問題数は40問程度で、CBT形式で行われます。受験者数や合格率は公開されていません。出題範囲が広く統計学はもちろん、SQLなどのプログラムやデータベースの知識も必要なため、統計検定の中でも難易度はかなり高いといえるでしょう。
データアナリストやAI技術者としてより高度なキャリアを目指すなら、挑戦しておきたい資格です。
出典|参照:「統計検定 データサイエンスエキスパート」が2023年5月10日から開始されました|統計検定:Japan Statistical Society Certificate
統計検定の例年の受験日と申し込み方法

統計検定は筆記のPBT試験を採用している1級とCBT形式で解答するそれ以外の検定で受験日や申し込み方法が大きく異なります。とくにCBT形式の試験は手続きが会場によって異なるため、少しわかりにくい部分があります。
受験前にあわてないように、余裕を持って確認しておきましょう。
受験日
統計検定1級は毎年11月に札幌、東京、名古屋、大阪、福岡などの主要都市部で行われます。統計検定1級以外はCBT形式で行われるため、全国のCBTに対応した会場で随時受験できます。
出典|参照:統計検定1級|統計検定:Japan Statistical Society Certificate
申し込み方法
統計検定1級は9月初めから10月初めまでの受付期間に統計検定のウェブサイトのフォームから申し込みできます。受験料の支払方法はクレジットカード決済または銀行振込です。
また、10名以上であればメールで団体受験の申し込みも可能で、この場合は受験料の支払方法は銀行振込のみです。午前中に統計数理、午後に統計応用の試験が行われ、同時に受験する場合は受験料の割引があります。
申し込みすると11月上旬に受験票が送付されるので、受験者の写真を貼り付けて試験に持っていかなければなりません。統計検定1級以外の検定を申し込む場合は、まず株式会社オデッセイ・コミュニケーションズのウェブサイトで統計検定の試験を行っている会場を検索しましょう。
その会場で試験日程を確認し、会場のウェブサイトにアクセスして直接受験の申し込みをします。申し込みや支払方法は会場によって異なります。
また、試験までにオデッセイ・コミュニケーションズのアカウント登録(無料のOdyssey IDの取得)が必要です。20名以上であれば団体受験も可能で、その場合は株式会社オデッセイ・コミュニケーションズに問い合わせをしてください。
統計検定1級以外は学割制度があり受験料が2~3割程度安くなるため、学生の方は積極的に利用しましょう。
統計検定は独学でも合格できる?

企業や学校で資格の取得をサポートしてくれる場合もありますが、基本的に統計検定は自分で勉強するケースが多い資格となります。その際気になるのは、独学で合格できるかということでしょう。
ここでは独学で統計検定は取得できるか、できるとしてどのようなことに気をつければいいかを解説します。
独学でも合格は可能
結論からいうと、独学での統計検定の取得は可能です。しかし、受ける検定の種類や受験者の能力によって状況は大きく変わります。
たとえば1級や準1級、DSエキスパートなどは、解答に高度な数学が必要な問題が出題されるため、大学などでどの程度数学や統計学を学んだかが重要です。
数学の基礎がない場合は、数学から勉強しなければいけないため独学で合格するのは非常に難しいと言わざるを得ません。
しかし、4級、3級レベルであれば高校や中学の数学しか使わないため独学での合格難易度は低くなります。2級も大学の基礎レベルのため、理系の学部に通っていた人であれば問題なく独学で取得できるでしょう。
このように、統計検定の取得を独学で目指すなら、まずは自分の実力に見合った検定の種類を見定めるのが重要です。
スケジュールを立てて計画的に勉強する
資格の取得では、まず学習計画を立てることが重要です。無計画のままだとやるべきことを先延ばしにして、学習が続かなくなってしまうからです。
最初に試験を受ける日を決め、そこまでにやるべきことを調べて、いつまでに何を学習すればいいかといった勉強のスケジュールを作りましょう。
スケジュールを定めて成果を確かめるようにすれば、どれだけ学習が進んだかがわかりやすくモチベーションの維持にもつながります。
わかりやすい参考書や問題集を使用する
独学では他の人に質問するのが難しいため、学習しやすい参考書や問題集を選ぶのも重要です。
公式からは試験範囲が丁寧に解説してある参考書が販売されているため、独学には非常に役立つ一冊といえるでしょう。しかし、必ずしも万人にとってわかりやすいとはいえないため、それを補うような市販の参考書も用意するのが得策です。
また、解答付きの公式過去問題集も販売されているので、アウトプット用にこちらも用意しておきましょう。
統計検定を学ぶのにおすすめの参考書・問題集
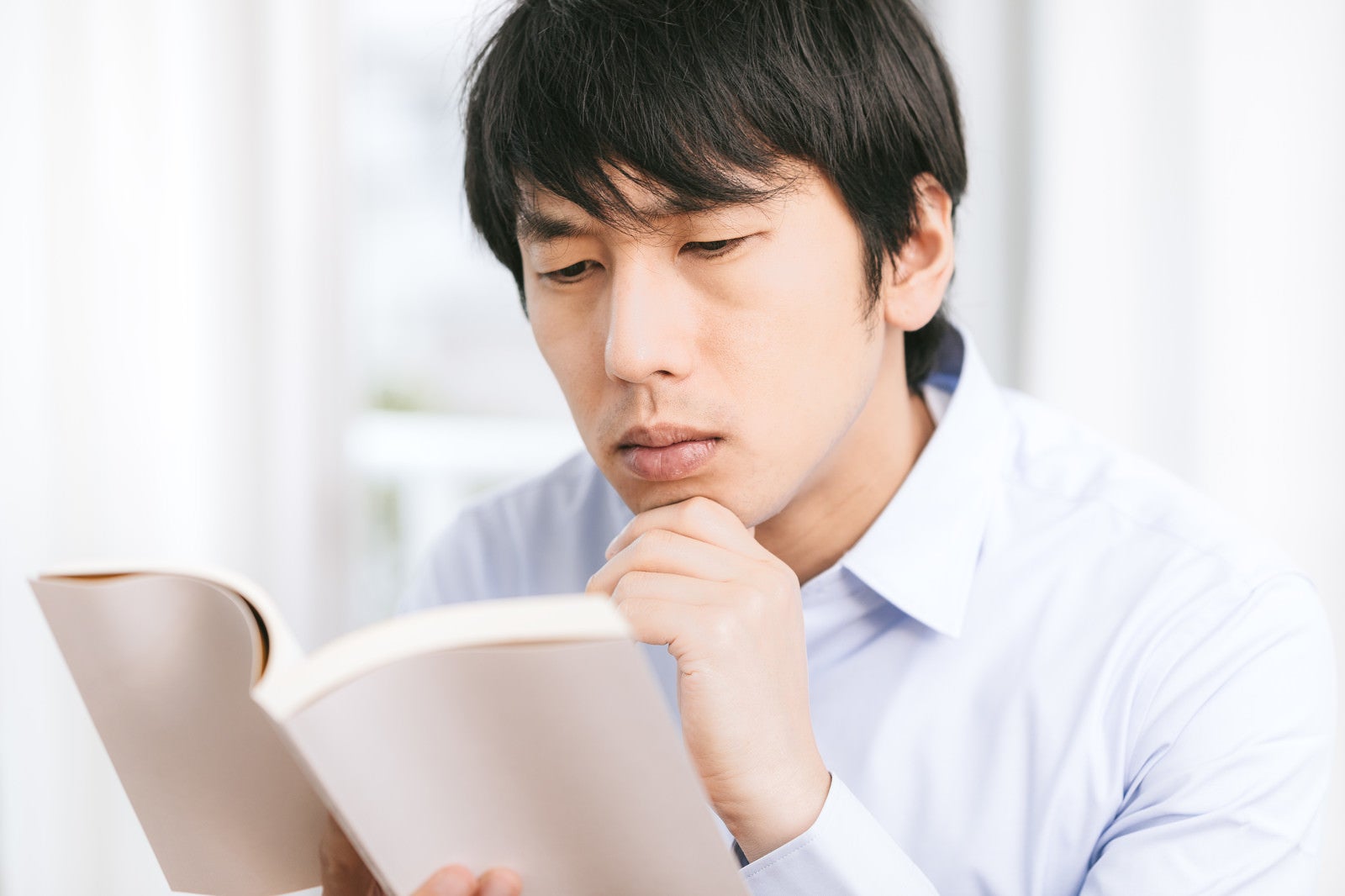
統計学の参考書にはいろいろな種類があり、資格取得の際にはその中で自分の能力や目的に適した参考書を選ぶのが重要です。
初めて学習するのであれば、まずは統計学の考え方に慣れる必要があります。たとえば「マンガでわかる統計学 素朴な疑問からゆる〜く解説 (サイエンス・アイ新書)」といった入門書なら、わかりやすく基本的な統計学の概念を学べるでしょう。
また、日本統計学会公式認定の公式テキストと問題集は、確実に検定に必要な範囲の知識が身につくため、試験を受ける前には目を通しておきたい参考書です。
東京大学教養学部統計学教室の「統計学入門」は、2級程度の統計学をわかりやすく説明しています。公式テキストで理解しにくい部分を補う用途で役に立つでしょう。
統計検定によくある疑問

ここまで統計検定について詳しく説明してきたため、その概要についてはおわかりいただけたのではないでしょうか。
しかし、まだいくつか疑問に感じる点があるかもしれませんので、ここではそれらに答えていきます。
統計検定は国家資格?
統計検定は民間資格です。国家資格は国や国が委託している組織が実施している資格です。
一方、統計検定の認定組織は一般社団法人日本統計学会であり、実施しているのは一般財団法人統計質保証推進協会です。国や国が委託している組織ではありません。
しかし、総務省、文部科学省、経済産業省、内閣府、厚生労働省の5つもの政府機関が後援し、協賛団体や協賛学会も多いため、社会的に価値を認められている資格なのは確かです。
出典|参照:国の資格制度一覧|総務省
統計検定で電卓は使用できる?
統計検定のほとんどの試験では、関数機能がない一般的な電卓の使用が許可されています。プログラムやグラフ機能があるような関数電卓や金融電卓は禁止されているので、注意してください。
百分率や平方根の機能はついていても問題ないので、これらの機能は備わっている電卓を選びましょう。12桁表示の一般的な事務用電卓ならほとんどの場合は問題ありません。
ただし、DS基礎だけは電卓そのものの持ち込みが禁止されています。
統計検定の過去問は入手可能?
統計検定の過去問とその解答は直近のPBT方式(筆記式)のものが公式サイトから無料でダウンロードできます。
しかし、1級以外はCBT形式に切り替わったため、最近の問題は掲載されていません。また、問題と解答のみで解説はなく、どうやって解答を導くかは自分で考えるか、インターネット上で解説しているサイトを探すなどする必要があります。
そのため、実際の学習で使うなら過去数年分の問題と詳しい解説が付属した、公式過去問題集が便利でしょう。
キャリアに合った種類の統計検定を取得しよう

AI技術やデータサイエンスなどがビジネスで使われるようになってきた現代社会において、統計検定は今後ますます評価される可能性があります。
統計検定の中には、統計学の初心者でも取得可能な種類があるため、初学者がスキルを身につける過程でも非常に役立ち、さらに上位資格となれば高度な専門家として自分の実力をアピールできる優れた資格なのです。
もちろん、取得していれば実務でも十分生かせる資格となっています。統計検定の資格を生かした仕事にはどのような種類があるのか、さっそくMidworksで検索してみてはいかがでしょうか。
関連記事
フリーランスのキャリア


SAPフリーランス単価相場は?市場価値のあるスキルや資格も紹介

AWSフリーランス単価相場で知る|市場価値と高収入戦略
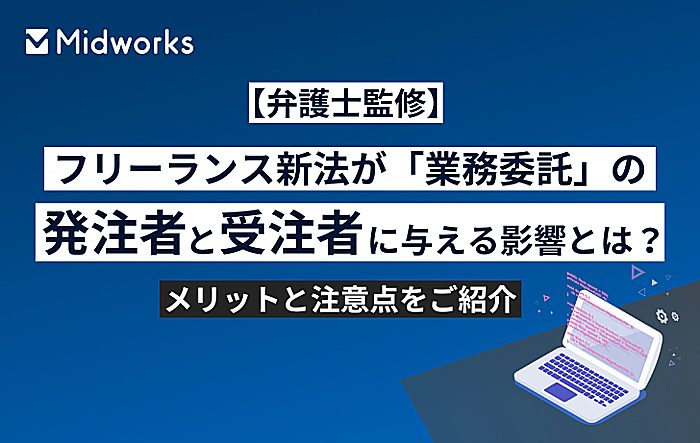
【弁護士監修】フリーランス新法が「業務委託」の発注者と受注者に与える影響とは?メリットと注意点をご紹介
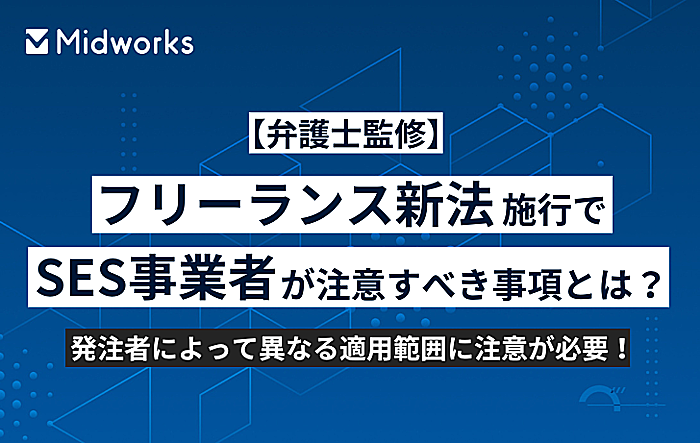
【弁護士監修】フリーランス新法施行でSES事業者が注意すべき事項とは?発注者によって異なる適用範囲に注意が必要!
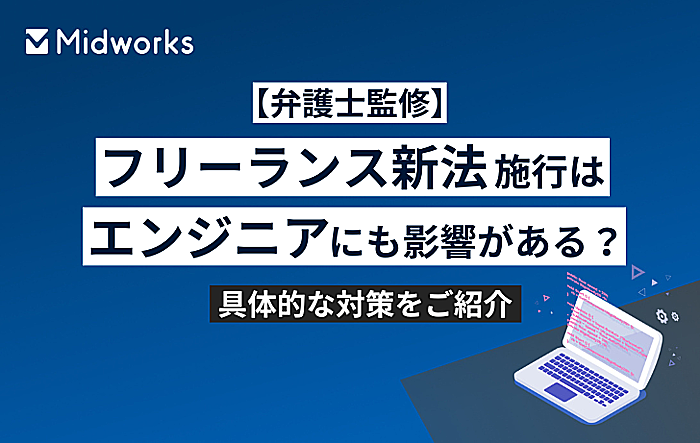
【弁護士監修】フリーランス新法施行はエンジニアにも影響がある?具体的な対策をご紹介
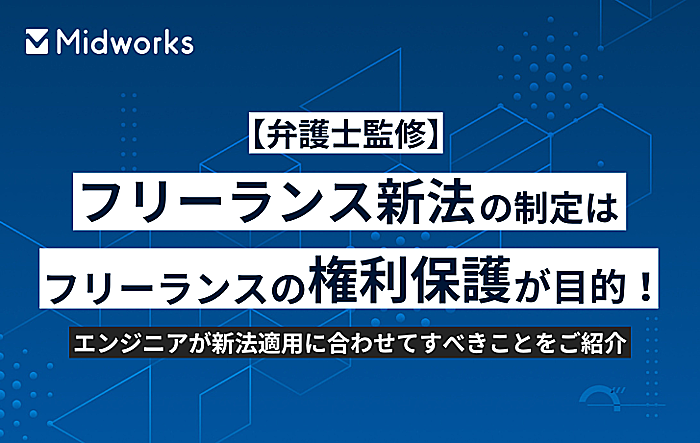
【弁護士監修】フリーランス新法の制定はフリーランスの権利保護が目的!エンジニアが新法適用に合わせてすべきことをご紹介
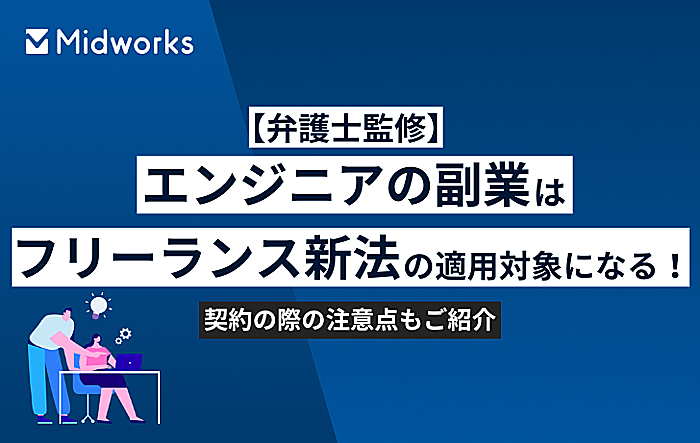
【弁護士監修】エンジニアの副業はフリーランス新法の適用対象になる!契約の際の注意点もご紹介
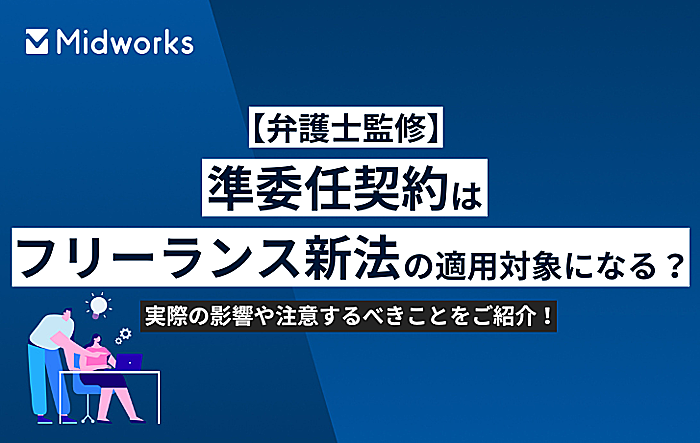
【弁護士監修】準委任契約はフリーランス新法の適用対象になる?実際の影響や注意するべきことをご紹介!
インタビュー


紹介からたった1週間で現場にフリーランスが参画!スピード感で人手不足を解消-株式会社アイスリーデザイン様
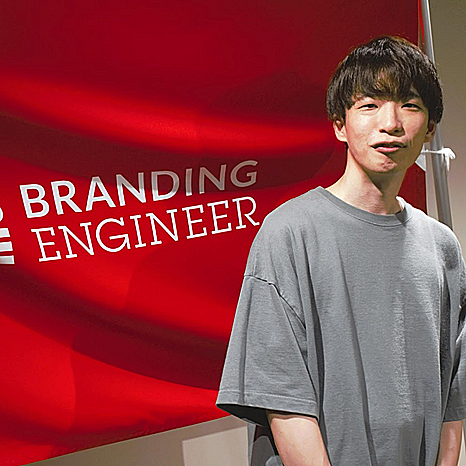
受託開発企業から、フリーランスで自社開発企業へ!

事業の成長スピードに現場が追い付かないという悩みをMidworks活用で解決-株式会社Algoage様
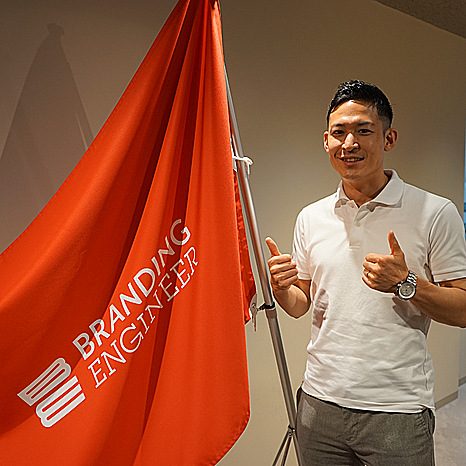
30代でも遅くない!未経験からエンジニアへのジョブチェンジで天職と巡り合った、英語が喋れる元消防士のフリーランスへの挑戦

フリーランスに転向し収入も生活も向上 アップデートを続けるエンジニアの情報収集方法を公開
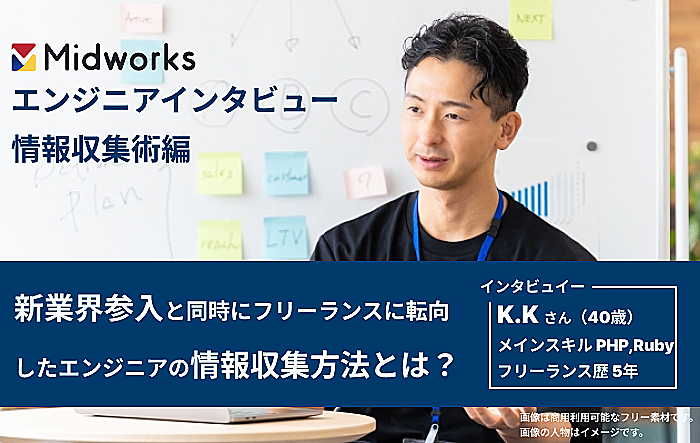
新業界参入と同時にフリーランスに転向したエンジニアの情報収集方法とは?
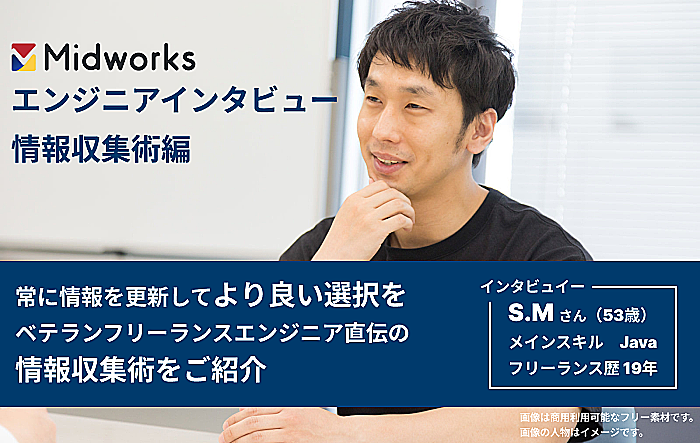
常に情報を更新してより良い選択を ベテランフリーランスエンジニア直伝の情報収集術をご紹介
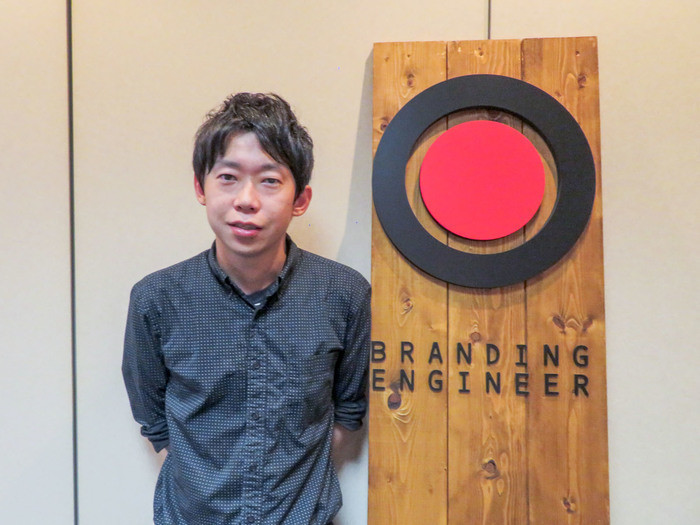
理想的なエンジニア像を描き、自由な働き方を求めてフリーランスへ。
フリーランスの基礎知識


何年の経験でフリーランスエンジニアは案件を獲得できる?未経験の場合についても解説

20代前半でもフリーランスエンジニアになれる?平均年収やメリット・デメリット

副業フリーランスはおすすめ?未経験からの始め方やメリット・デメリットを解説

【初心者におすすめ】ITパスポート試験で合格点は?合格に近づく勉強法

IT業界の現状は?市場規模や今後の動向についても解説!

フリーランスのソフトウェア開発に求められる「12のこと」をご紹介!必要なスキルも解説

【職種別】フリーランスエンジニアの年収一覧!年代やプログラマーの言語別にも紹介
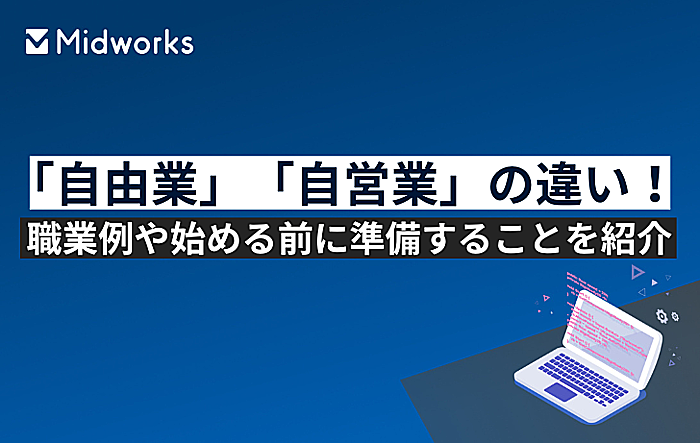
実は知られていない「自由業」「自営業」の違い!職業例や始める前に準備することを紹介
プログラミング言語

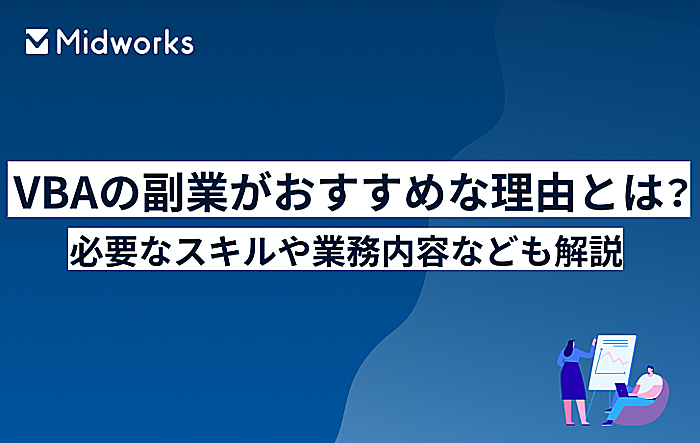
VBAの副業がおすすめな理由とは?必要なスキルと業務内容・案件の探し方も解説
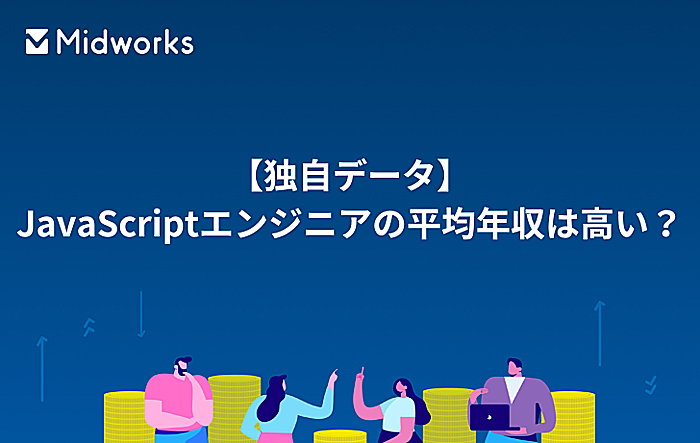
【独自データ】JavaScriptエンジニアの平均年収は高い?年収を上げる方法もご紹介
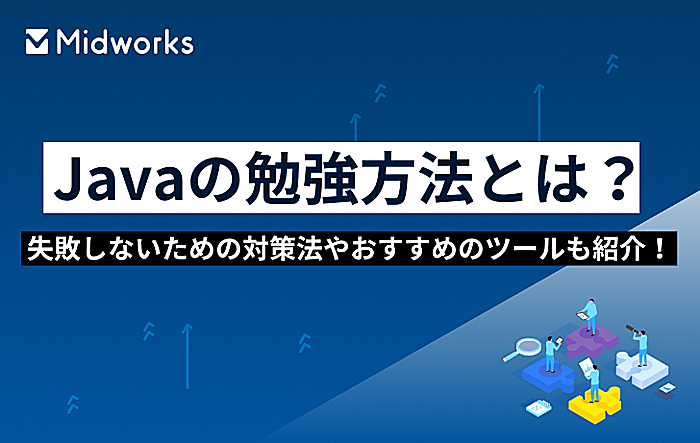
Javaの勉強方法とは?失敗しないための対策法やおすすめのツールも紹介!

【独自データ】PHPエンジニアの年収は高い?年収を上げるための方法もご紹介!
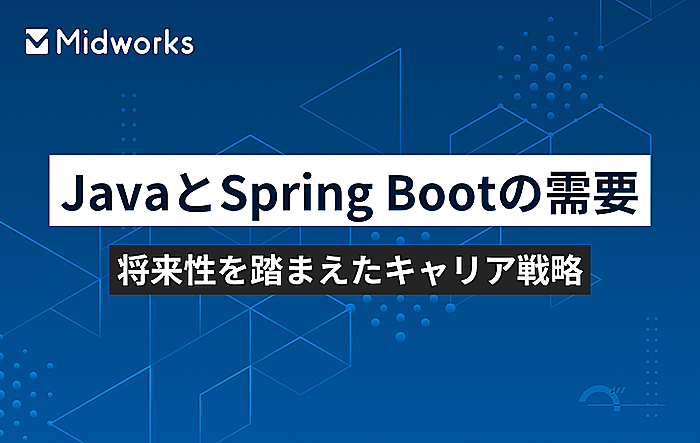
Title JavaとSpring Bootの需要|将来性を踏まえたキャリア戦略

Java Gold資格の難易度とキャリア価値を徹底解説
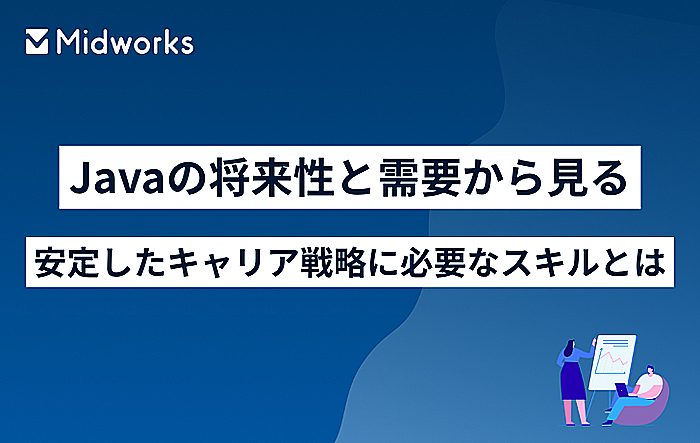
Javaの将来性と需要から見る|安定したキャリア戦略に必要なスキルとは
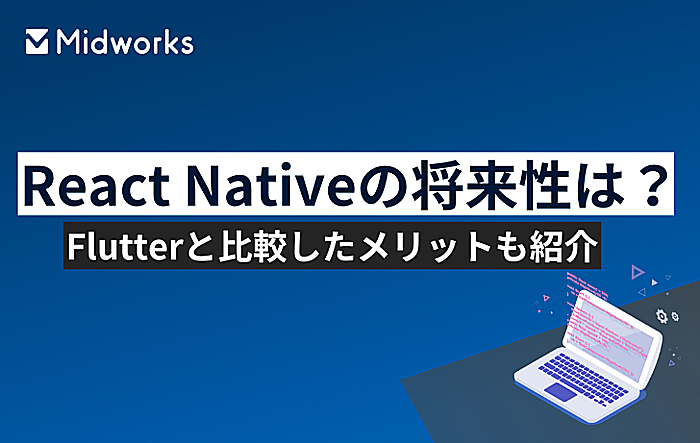
React Nativeの将来性は?Flutterと比較したメリットも紹介
企業向け情報

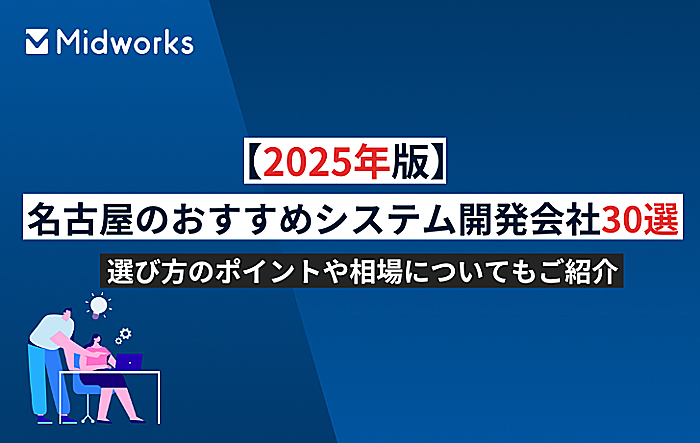
【2025年版】名古屋のおすすめシステム開発会社30選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
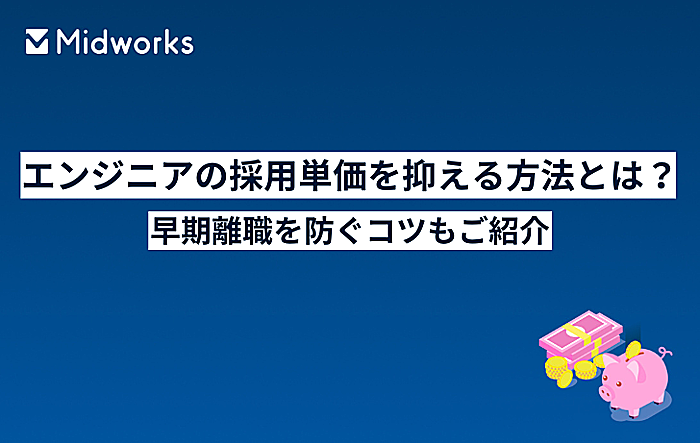
エンジニアの採用単価を抑える方法とは?早期離職を防ぐコツもご紹介
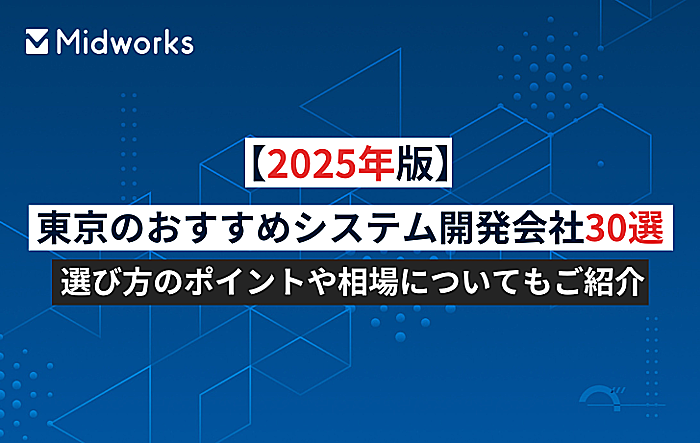
【2025年版】東京のおすすめシステム開発会社30選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
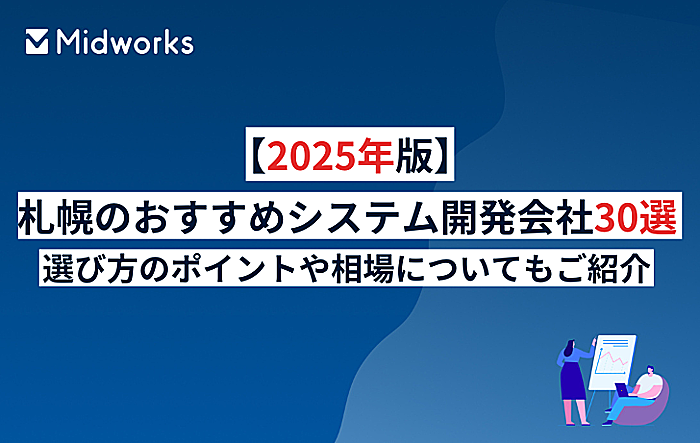
【2025年版】札幌のおすすめシステム開発会社30選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
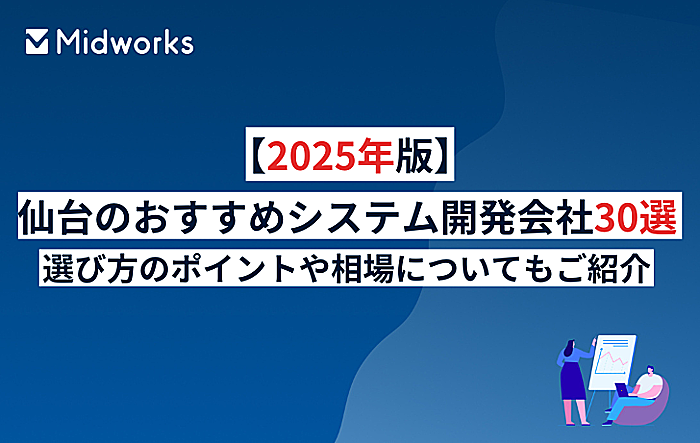
【2025年版】仙台のおすすめシステム開発会社30選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
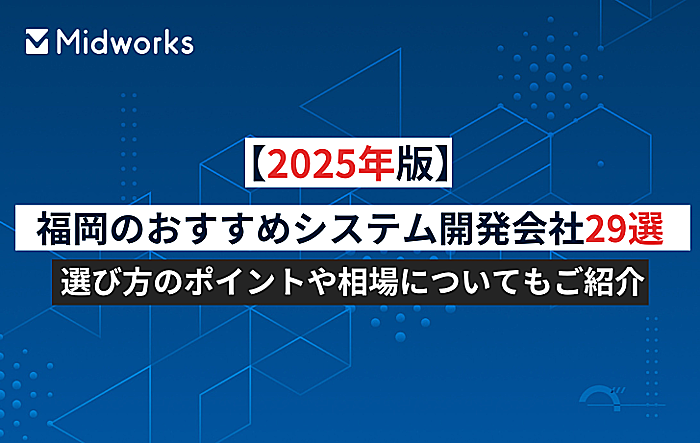
【2025年版】福岡のおすすめシステム開発会社29選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
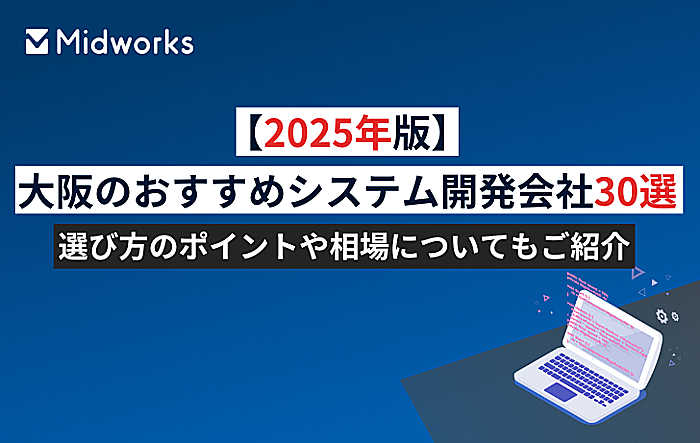
【2025年版】大阪のおすすめシステム開発会社30選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
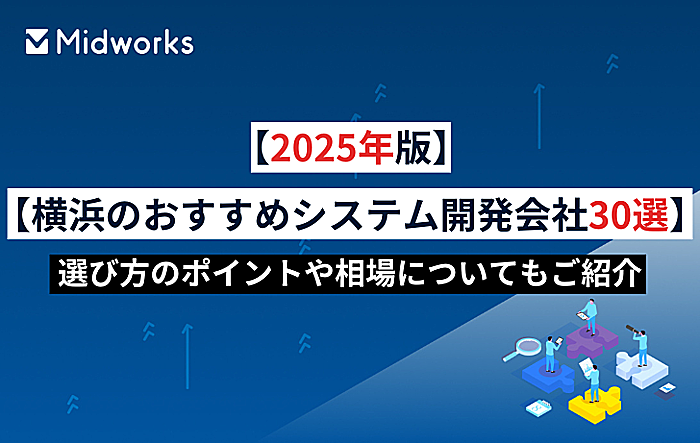
【2025年版】横浜のおすすめシステム開発会社30選|選び方のポイントや相場についてもご紹介
業界特集


医療業界のフリーランスエンジニア向け案件特集|DX化が進む成長市場で求められるスキルと働き方のポイント

自動車業界フリーランスエンジニア案件特集|CASE時代の開発をリード!求められる技術とプロジェクト事例

EC業界のフリーランスエンジニア向け案件特集|急成長業界で必要とされるスキルや働き方のポイントもご紹介

セキュリティ業界のフリーランスエンジニア向け案件特集|案件参画で身につくスキルや参画の際に役立つ資格もご紹介

金融業界(Fintech領域)のフリーランスエンジニア向け案件特集|業界未経験でも活躍する方法もご紹介

生成AI分野フリーランスエンジニア案件特集|最先端技術を駆使!注目スキルと開発プロジェクト事例

小売業界フリーランスエンジニア案件|年収アップとキャリアアップを実現!最新トレンドと案件獲得のコツ