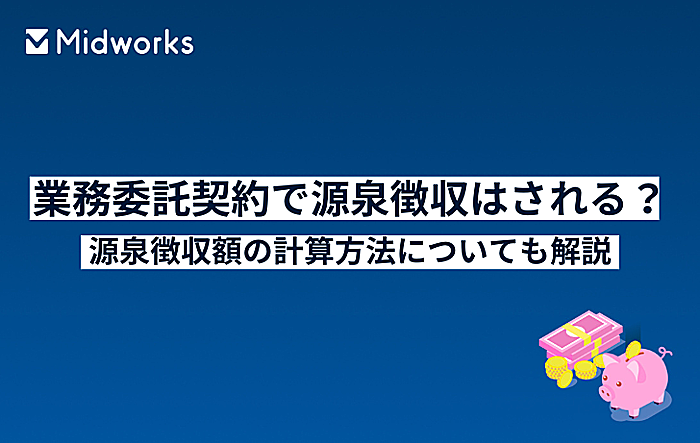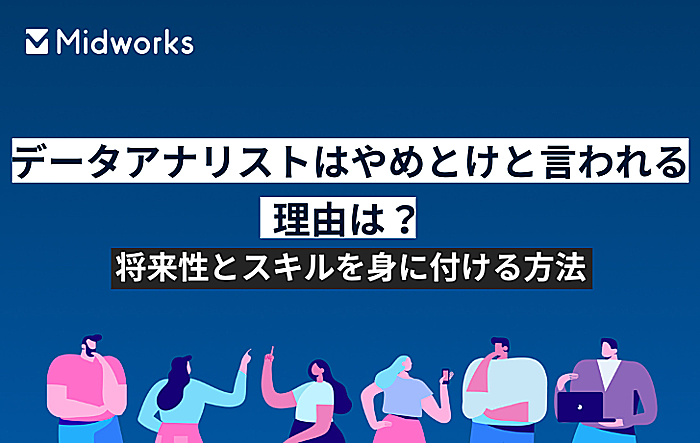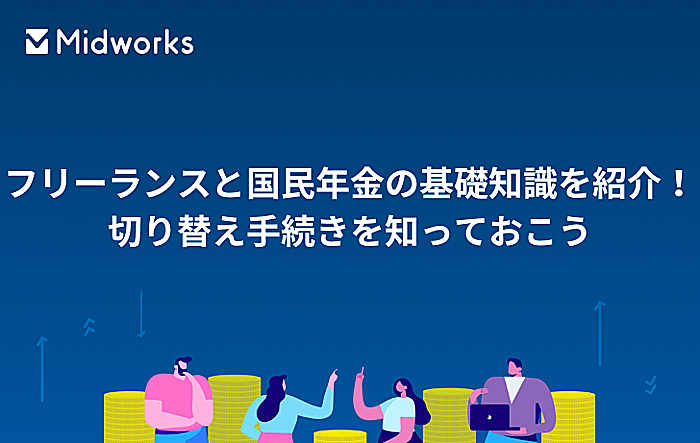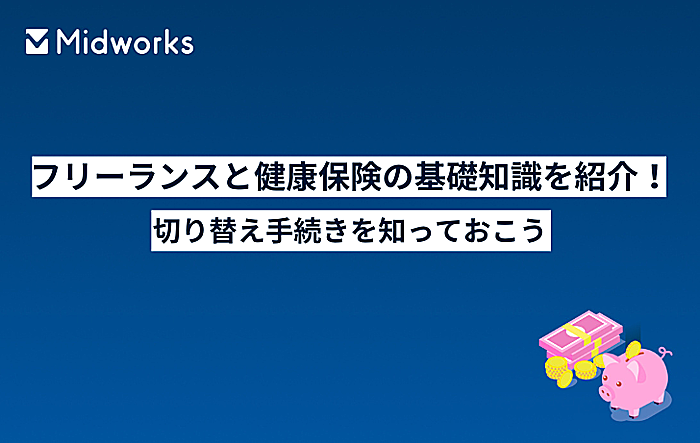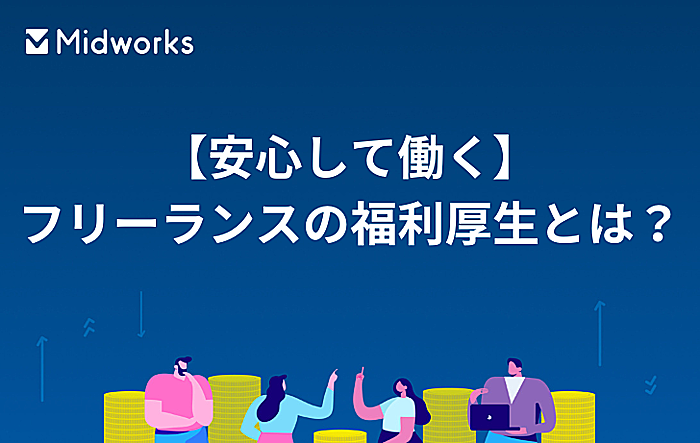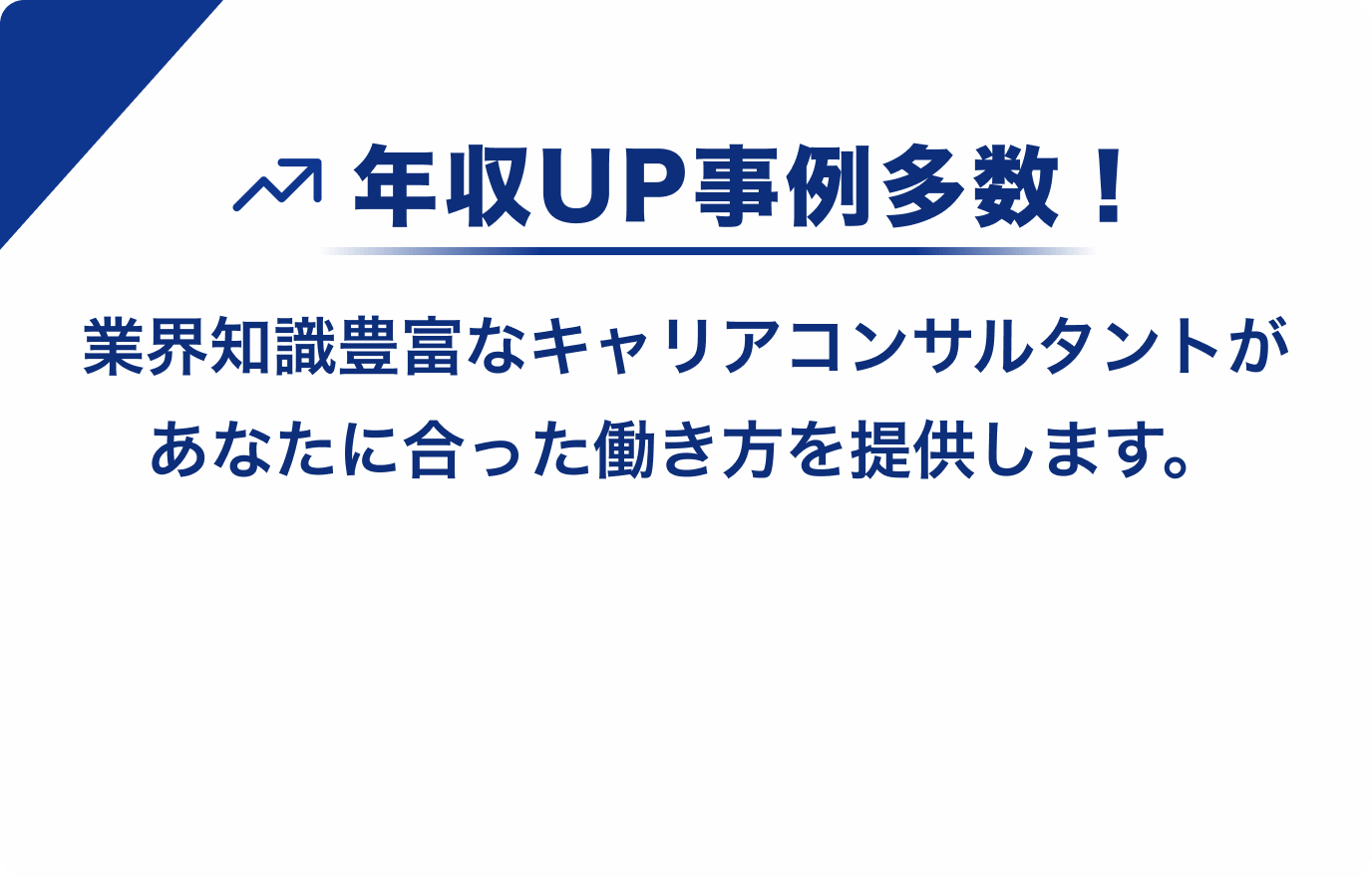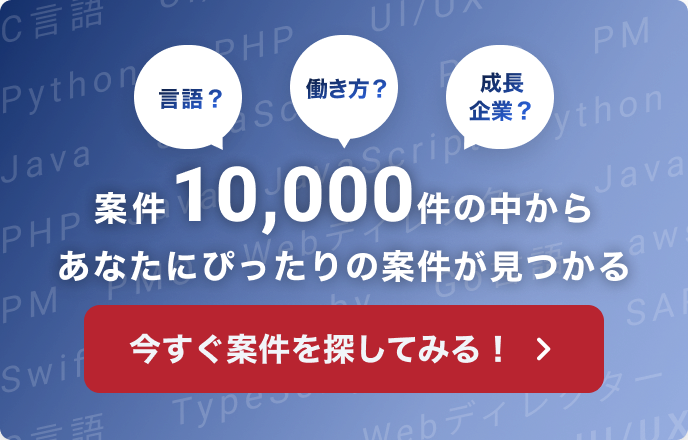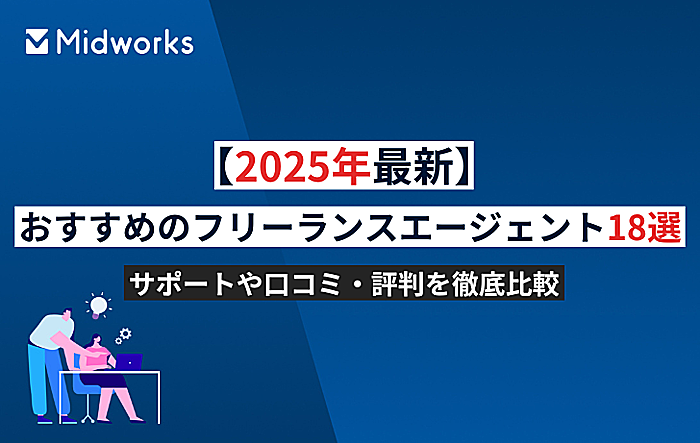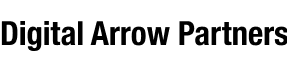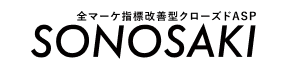その他の保険
フリーランスのキャリア

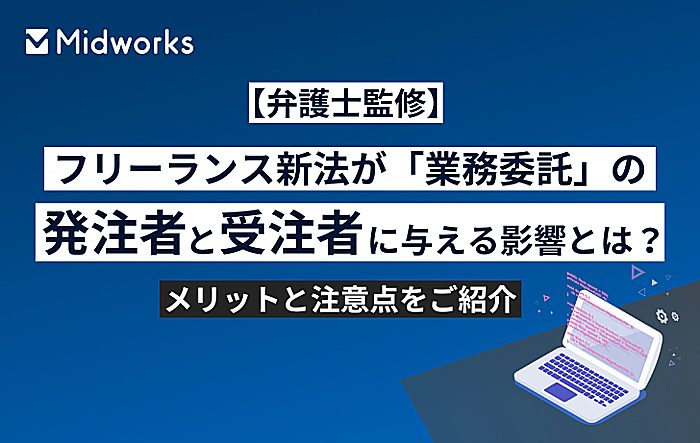
【弁護士監修】フリーランス新法が「業務委託」の発注者と受注者に与える影響とは?メリットと注意点をご紹介
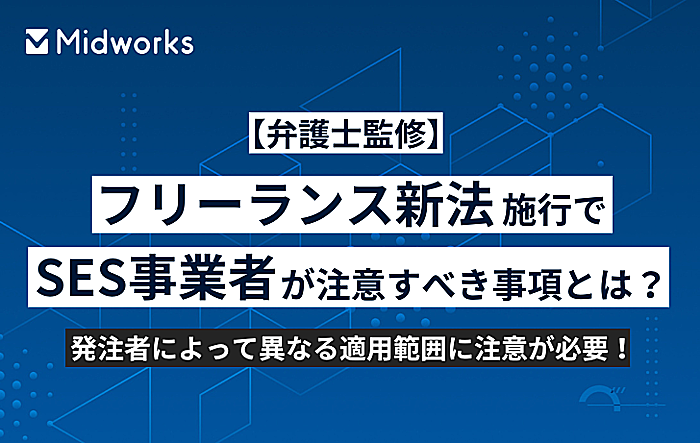
【弁護士監修】フリーランス新法施行でSES事業者が注意すべき事項とは?発注者によって異なる適用範囲に注意が必要!
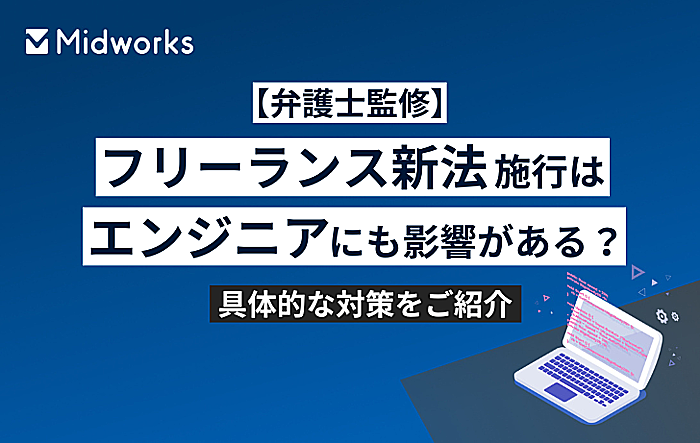
【弁護士監修】フリーランス新法施行はエンジニアにも影響がある?具体的な対策をご紹介
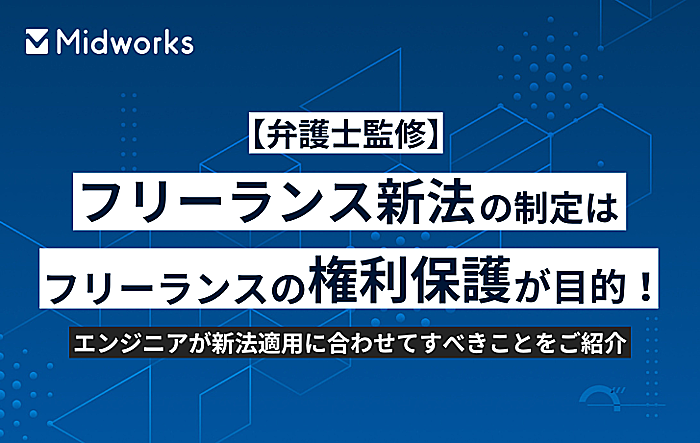
【弁護士監修】フリーランス新法の制定はフリーランスの権利保護が目的!エンジニアが新法適用に合わせてすべきことをご紹介
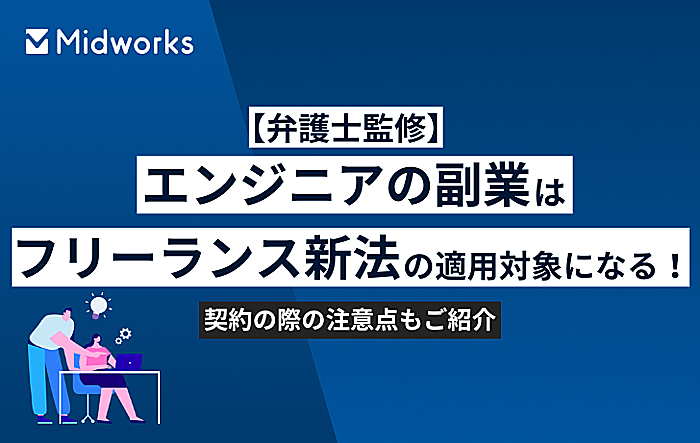
【弁護士監修】エンジニアの副業はフリーランス新法の適用対象になる!契約の際の注意点もご紹介
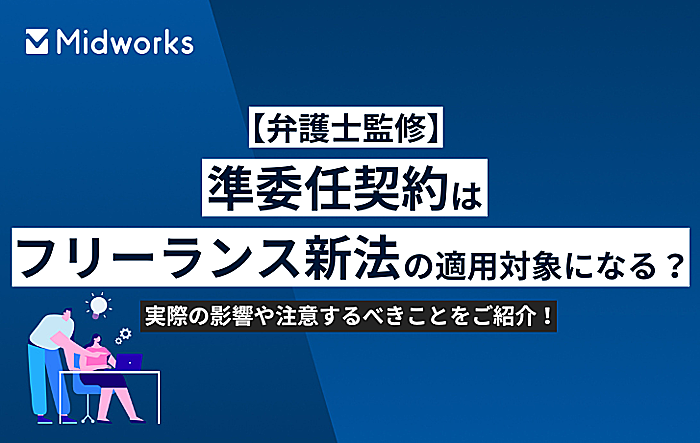
【弁護士監修】準委任契約はフリーランス新法の適用対象になる?実際の影響や注意するべきことをご紹介!

【弁護士監修】フリーランス新法が業務委託の再委託に与える影響とは?再委託する・受ける場合の注意点をご紹介

【弁護士監修】副業での稼働もフリーランス新法の対象になる!実際に注意すべき点をご紹介
インタビュー


フリーランスに転向し収入も生活も向上 アップデートを続けるエンジニアの情報収集方法を公開
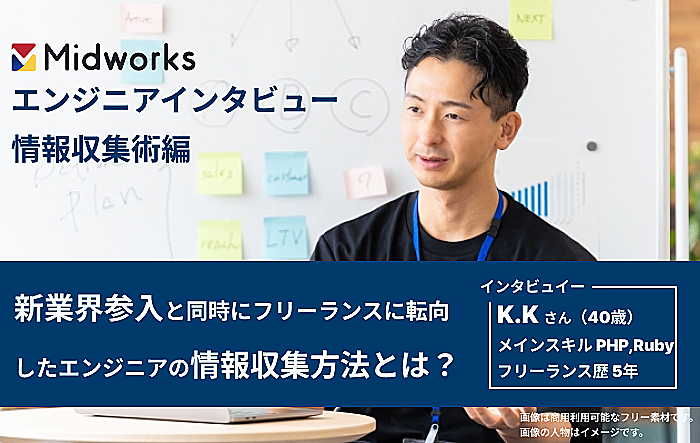
新業界参入と同時にフリーランスに転向したエンジニアの情報収集方法とは?
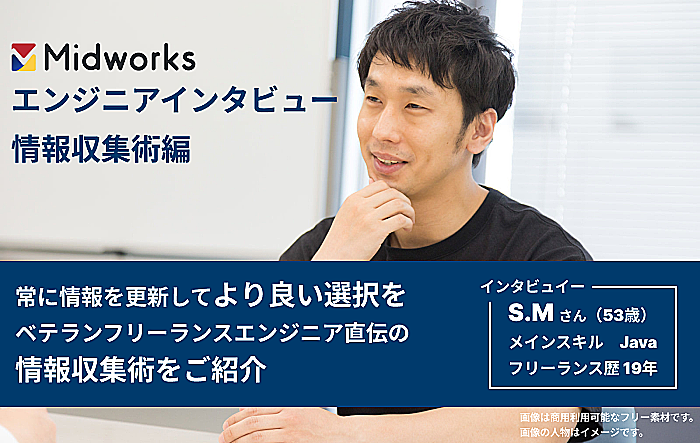
常に情報を更新してより良い選択を ベテランフリーランスエンジニア直伝の情報収集術をご紹介
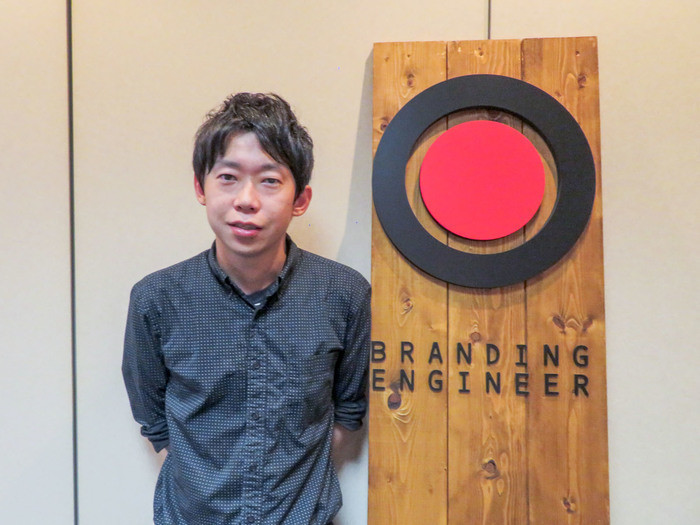
理想的なエンジニア像を描き、自由な働き方を求めてフリーランスへ。

フリーランスになって収入が3倍!全エンジニアに独立は怖くないと伝えたい

評価と報酬を考え、的確な情報を得ながら働けるフリーランスは、自分にあった生き方

専門家としての誇りを持ち、期待に応えてしっかり稼ぐ

思いもかけないフリーランスとしてのキャリア。そこには大きな可能性がたくさん詰まっていた
エンジニアの職種


TechStockの気になる評判は?おすすめポイントや使い方を詳しく解説

【徹底比較】ネットワーク監視のフリーソフトおすすめ10選!できることやメリットをご紹介!

AWSの導入事例17選を紹介!導入するメリットや注意点について解説

デバッカーが「きつい」と言われる本当の理由とは?必要なスキルやおすすめの資格もご紹介!

運用保守が「やめとけ」と言われる理由とは?平均年収や仕事内容から解説!

ネットワークエンジニアは「やめとけ」と言われてしまう理由とは?仕事の魅力やメリットも解説

Linux関係の資格を取得するメリットとは?取得に向けた勉強方法も紹介

【必見】組み込みエンジニアのフリーランス年収とは?将来性や必要なスキルも紹介
エージェント紹介


jo-Beetの気になる評判は?おすすめポイントや使い方を詳しく解説

Voteee Technologiesの気になる評判は?おすすめポイントや使い方を詳しく解説

スカイアーチHRソリューションズの気になる評判とは?おすすめポイントや気をつけたい点を徹底解説!

フリーランスパートナーズの気になる評判は?おすすめポイントや使い方を詳しく解説

アズテックスフリーランスの気になる評判は?おすすめポイントや使い方を詳しく解説

SKILLRY FREELANCEの気になる評判は?おすすめポイントや使い方を詳しく解説

SE BASEの気になる評判は?おすすめポイントや使い方を詳しく解説

Styleeの気になる評判は?おすすめポイントや使い方を詳しく解説
業界特集


医療業界のフリーランスエンジニア向け案件特集|DX化が進む成長市場で求められるスキルと働き方のポイント

自動車業界フリーランスエンジニア案件特集|CASE時代の開発をリード!求められる技術とプロジェクト事例

EC業界のフリーランスエンジニア向け案件特集|急成長業界で必要とされるスキルや働き方のポイントもご紹介

セキュリティ業界のフリーランスエンジニア向け案件特集|案件参画で身につくスキルや参画の際に役立つ資格もご紹介

金融業界(Fintech領域)のフリーランスエンジニア向け案件特集|業界未経験でも活躍する方法もご紹介

生成AI分野フリーランスエンジニア案件特集|最先端技術を駆使!注目スキルと開発プロジェクト事例

小売業界フリーランスエンジニア案件|年収アップとキャリアアップを実現!最新トレンドと案件獲得のコツ